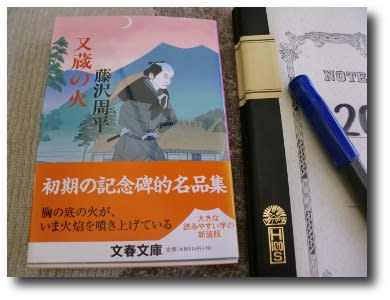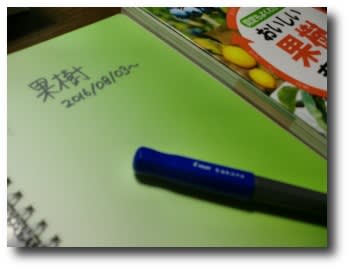行きつけの文具店で、便せんや固形糊などを補充してきたついでに、ステーショナリー・フリーマガジン『Bun2』の2016年8月号(vol.67)をもらってきました。

今号の特集テーマは、「楽しい文具」というものです。例年通り、夏休みらしく手作りホビーなどの情報を集めたもののようです。その中身のほうは、
などとなっていますが、夏休みの宿題とは無縁となった中高年オジサンにはあまり興味を惹かれるものはなさそうです。「消しゴムハンコ」にも「イロモノ文具」にも興味関心が皆無の当方には、文具も夏枯れなのか、今号には注目すべきものはないなあと嘆いていましたら、かろうじて二つほどありました。
「パイロット 蛍光ペン付き三色ボールペン アクロボール・スポットライター 600円」
「リヒト スタンドペンケース(楕円タイプ) 1,200円」
いずれも、三色ボールペンと蛍光ペンを持っていれば用が足りるとか、ペンケースばかり何種類も持っていても、カバンやバッグの空きスペースが問題だ、というように、「今さら」感があるのですが、それでもワケノワカラナイ製品ではないという点で、確実にポイントを稼いでいるようです。
むしろ、次の10月号のほうが、秋の夜長を楽しむ実用の製品や、気の早いダイアリー商戦の前触れ記事などが期待できるでしょう(^o^)/

今号の特集テーマは、「楽しい文具」というものです。例年通り、夏休みらしく手作りホビーなどの情報を集めたもののようです。その中身のほうは、
- アルバム作り
- ぬりえ
- 段ボール甲冑
- 楽描きイベント
- ご当地インク
などとなっていますが、夏休みの宿題とは無縁となった中高年オジサンにはあまり興味を惹かれるものはなさそうです。「消しゴムハンコ」にも「イロモノ文具」にも興味関心が皆無の当方には、文具も夏枯れなのか、今号には注目すべきものはないなあと嘆いていましたら、かろうじて二つほどありました。
「パイロット 蛍光ペン付き三色ボールペン アクロボール・スポットライター 600円」
「リヒト スタンドペンケース(楕円タイプ) 1,200円」
いずれも、三色ボールペンと蛍光ペンを持っていれば用が足りるとか、ペンケースばかり何種類も持っていても、カバンやバッグの空きスペースが問題だ、というように、「今さら」感があるのですが、それでもワケノワカラナイ製品ではないという点で、確実にポイントを稼いでいるようです。
むしろ、次の10月号のほうが、秋の夜長を楽しむ実用の製品や、気の早いダイアリー商戦の前触れ記事などが期待できるでしょう(^o^)/