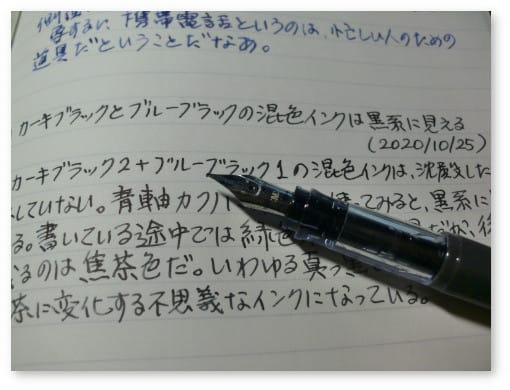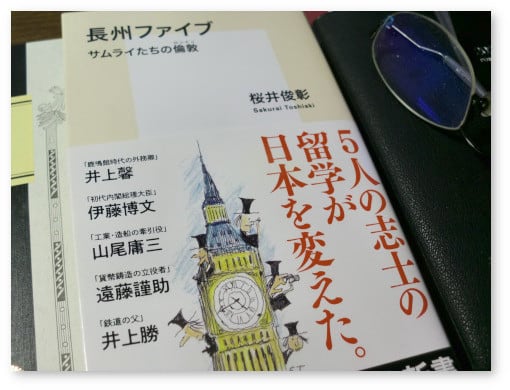まずは痛恨の大失敗から。私の手帳には、15時開演とメモしてあったのですよ。もちろん、私の思い込みによるうっかりミス。老母に晩御飯も作り、万全の態勢で出かけて駐車場に車を入れたのが14時、コンビニでのど飴などを買って、余裕だなと思っていたのです。そうしたら、「まさかの」14時開演! チケットを確認したら、たしかに14時と書いてある。嗚呼!
何の話かというと、妻と二人でプッチーニの歌劇「トゥーランドット」を観に出かけたのです。
気を取り直して、第二幕から入場。新県民ホールはステージ前にオーケストラピットを設け、ステージ両側に日本語字幕、正面上部に英語字幕を準備してあり、原語イタリア語には全く疎い素人音楽愛好家にもわかりやすい配慮です。うん、これなら古いレーザーディスクの字幕よりも大きくて字が読みやすいかも(^o^)/
第一幕のあらすじを簡単に紹介すると、ダッタンの王子カラフは、中国の都・北京で、戦火で離れ離れになっていた父王ティムールと女奴隷の召使リューと再開し、喜びに浸りますが、その頃の北京はなんとも残酷なことになっていました。皇帝の娘トゥーランドット姫に求婚した外国王族の王子は、姫の出す三つの謎に挑戦し、解けない場合は惨殺されるというのです。王子カラフは、姫の美貌にポーッとなり、父とリューの反対にもかかわらず、謎に挑戦することにしてしまいます。

で、第二幕です。三人の大臣ピン、パン、ポンがおかしみのある幕間劇を演じます。今はトゥーランドット姫に求婚し謎解きに敗れた外国の王族の処刑に明け暮れる日々、「こんな仕事やだ〜」「故郷へ帰りたい〜」といった心境でしょうか。
一転して謎解きの場面。何やら三人の女性ダンサーが宙吊りになり、死と亡霊を象徴する怪奇幻想趣味の情緒を漂わせる中でトゥーランドット姫が登場。アリア「この宮殿で、幾千年もの昔」を歌います。そんな大昔の話を持ち出して、求婚する若者を次々に処刑するなんて、私なら先天的に残虐無道な姫なのではなかろうかと疑うところですが、王子カラフは自信満々、謎解きに挑戦し三問とも正解します。姫はうろたえ、「こんな人と結婚するなんて嫌よ!」と父(皇帝)に訴えますが、「約束は神聖」と拒絶され、カラフを憎みます。王子カラフは、逆に「私の名前は?」という謎を出し、夜明けまでを期限に命を投げ出します。姫とカラフの二重唱、地を這うような低音が不気味さを示すオーケストラの響きなどが印象的な第二幕です。
幕間の休憩の後、第三幕です。トゥーランドット姫は住民に恐怖のお触れを出しますが、それは王子の名を明らかにできなければ住民を死刑にするとの無茶苦茶なものでした。三人の大臣は、カラフに財宝や美女など様々な誘惑を持ちかけますが、カラフはこれを拒絶。「誰も寝てはならぬ」を歌い、勝利を確信します。ところが、カラフと一緒に話をしていたという住民の密告があって父ティムールと召使リューが捕らえられ引き立てられてきます。拷問により口を割らせると脅すトゥーランドット、王子の名を知っているが言わない、それは愛ゆえにと「氷のような姫君の心も」を歌い、自ら死を選ぶリュー。カラフよりも父ティムールの悲嘆と哀惜の歌が胸に迫ります。葬送の音楽に続くのは、カラフとトゥーランドットの心理ドラマを描く音楽です。
まあ、王子が接吻すると氷のような姫の心も溶け去るというのは、昔のステレオタイプなロマンス話の定番ですからそれほど呆れはしませんで、荒唐無稽な物語でもちゃんと音楽として成り立たせてしまう全曲の幕切れは立派なものでした。鳴り止まない拍手、カーテンコールでは聴衆が起立して関係した皆さんを讃えます。本当は「ブラヴォー!」の声が多数かかるところですが、「ブラボー・タオル」を掲げて意思表示している方が大勢いました。全く同感、妻と二人で、良かったね〜と話しながらホールを後にしました。

今回の公演は、演出と振付の大島早紀子さんの意図で、コンテンポラリー・ダンスが取り入れられたところが特徴だろうと思います。実際、怪奇幻想小説のような雰囲気を全編に漂わせているところは、手元にあるレーザーディスク(ゼフィレッリ演出)のものとも違う、独自の雰囲気を持ったものだと感じましたし、歌唱も演奏も素晴らしいものでした。ほんとに良かったと思います。
とりわけ心に残ったのは、リューの死を悼む老王ティムールの嘆きです。国を追われ、眼が見えなくなった無力な老人を一途な心で世話をしてくれたリューを、息子の行動で死なせてしまった哀惜と絶望、複雑な感情を隠して歌われる名場面。おそらく私が若い頃だったならば、この嘆きの歌を素通りしてしまっただろうと思いますが、年輪を重ねてはじめて観念としてではなく実感として理解共感できるのではなかろうか。思わずうるっときてしまいました。もしかすると老王ティムールは、女癖の悪い夫プッチーニと不倫をしていると疑った妻が自殺に追い込んだ小間使いを悼む、60代半ばの作曲家自身の姿なのかも。加藤浩子さんによる作品解説から、そんな想像をしてしまいました。