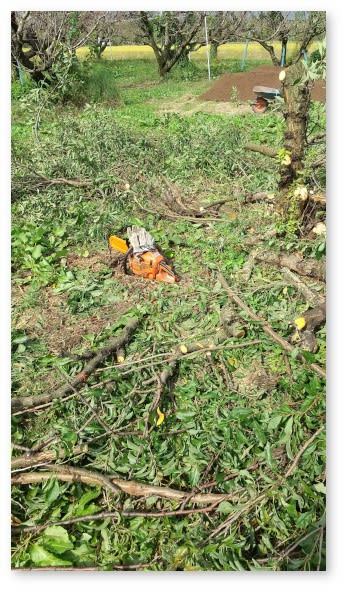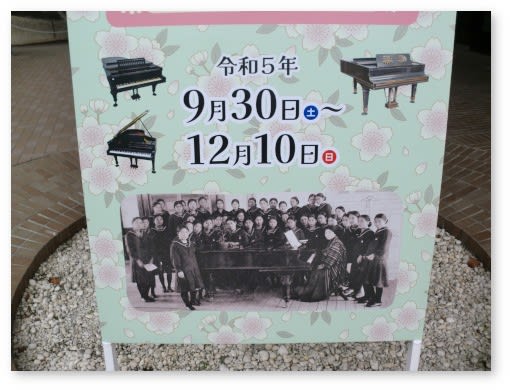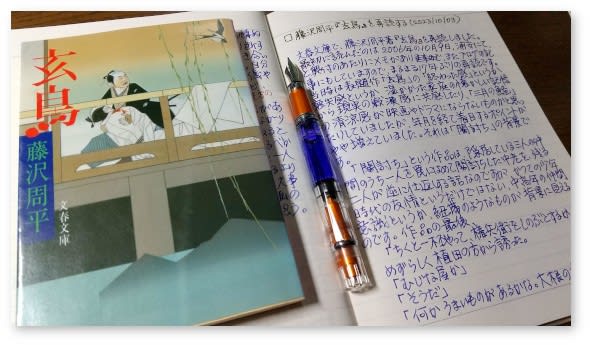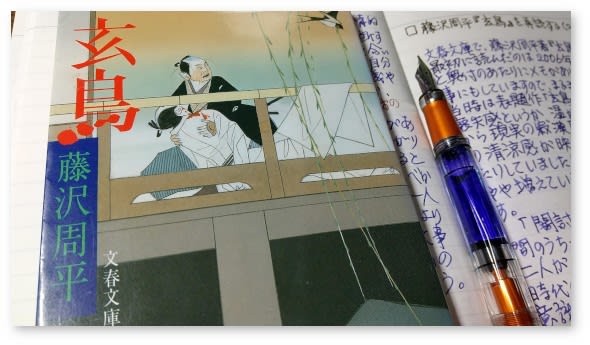秋のまっただ中である10月15日(日)の夜、山形市の県民ホール第一スタジオにて、山形弦楽四重奏団の第89回定期演奏会を聴きました。山形弦楽四重奏団は、山形交響楽団に所属する演奏家が中心となって組織したカルテットで、2000年の結成以来すでに23年の歴史があり、ハイドンの弦楽四重奏曲全曲演奏を達成したほか、日本の近現代の室内楽作品を積極的に取り上げるなど活発な活動を続けています。今回は、山響首席コンサートマスターの犬伏亜里さんを迎えて、モーツァルト、シューベルト、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第1番を取り上げる、というものです。具体的には、
の3曲です。とくに、若いベートーヴェンの作品が大好きな中でも、とりわけこの第1番がお気に入りなので、プログラム発表以来ずっと楽しみにしていました。
会場は長方形のスタジオの短辺側にステージを置いたもので、聴衆は80〜90人は入っていたでしょうか、けっこうぎっしり感があります。楽器の配置は、左から第1ヴァイオリン(犬伏亜里)、第2ヴァイオリン(中島光之)、ヴィオラ(倉田譲)、チェロ(茂木明人)となります。
第1曲、モーツァルトが少年時代のイタリア旅行中に作曲され、ウィーン時代に完成されたという第1番。「ローディ」というのは、宿泊先の地名だそうです。第1楽章:アダージョ、いきなり緩徐楽章から始まりますが、穏やかな中にも音楽に華があると感じられます。第2楽章:モーツァルトらしい活発なアレグロ。第3楽章:メヌエット〜トリオ、高域のヴァイオリンと中低域のヴィオラ・チェロの対比が魅力的です。第4楽章:ロンド、アレグロ。犬伏さん、楽章間のちょっとした合間に、右手で譜面をめくりながら左手の指で弦をはじいて音を確かめています。ハーモニクス?無駄のない合理的な動きで、なんとなく普段からテキパキとした方かもと想像してしまいました(^o^)/
続いて第2曲、シューベルト14歳の作品です。おそらく家庭内で演奏するなどの目的で作られた曲なのでしょうが、私には初体験。意外にも劇的な面もある音楽でした。第1楽章:アンダンテ〜プレスト、ヴィヴァーチェ。間を合わせるのが大変そうですが、力強さや迫力を感じさせます。すでにベートーヴェンを経験していたであろう少年作曲家のかっこいい音楽。第2楽章:メヌエット〜トリオ、一転して弱音器を付けたかわいらしい音で演奏されます。第3楽章:アンダンテ、弱音器を外して演奏される緩徐楽章です。第4楽章:プレスト。再び訴える力のある劇的な音楽となります。後年の室内楽曲の充実しか知りませんでしたが、若い時代の交響曲は全集で耳にしており、若いシューベルトの弦楽四重奏曲も魅力的なものがあるのだなと知りました。得難い経験となりました。
ここで15分の休憩です。
後半は、ベートーヴェンの第1番。1801年に改訂完成とありますので、作曲者が30歳頃の作品です。モーツァルトやシューベルトとは異なり、少年時代のものではなくすでに成熟した大人の作品。しかも、作品18の6曲のうち1番目に来るものとして番号を付けられたものですから、できの良い方を第1番にするというベートーヴェンの流儀からみても、青年期の傑作と言ってよかろうと思います。
第1楽章:アレグロ・コン・ブリオ。ごく自然な始まりです。チェロの中音域の音色が優しい。過度に意味有りげにせずに、演奏の自然なたたずまいは、多くの演奏経験のゆえでしょうか。第2楽章:アダージョ・アフェットゥオーソ・エ・アパッショナート。2nd-Vn、Vla、Vcによる中低音の中に、1st-Vnが悲しげな旋律を奏します。作曲者はロミオとジュリエットの墓場の場面を想像して作曲したのだとか。しだいに表情は穏やかなものに変わっていきますが、たいへん魅力的な音楽を説得力のある演奏で堪能しました。三度の休止が効果的。
第3楽章:スケルツォ、アレグロ・モルト〜トリオ。前楽章からは一転して、青年期ベートーヴェンらしい、活発なスケルツォです。とりわけ 1st-Vn は自信と思い切りの良さが求められるのだな、と感じました。
第4楽章:アレグロ。晴れ晴れとした開放感を感じさせる音楽、演奏です。これですよ、これ! 緊密な響きの中にやわらかな優しさを含みながら、闊達な音楽が広がります。実に若いベートーヴェンらしい、ステキな音楽です。いいなあ! 弦楽四重奏の充実と楽しさを、たっぷりと味わいました。
聴衆の拍手に応えて、アンコールはハイドンの弦楽四重奏曲第1番の第1楽章を。今回は、「1」づくしの回でした。
次回の第90回定期演奏会は、2024年1月22日(月)、19時から、同じ県民ホール・スタジオ1 にて。山響のクラリネット首席の川上一道さんを迎えて、ミュラーのクラリネット四重奏曲第1番ほか。
いよいよ第90回ですか。これはイソ弦楽四重奏団の100回の定期演奏会を超えるのが現実的に見えてきたようです。年4回の定期演奏会であれば25年で100回。ファンとしても応援したい。団員の皆さんのご健康を祈ります。

- モーツァルト 弦楽四重奏曲第1番 ト長調 K.80(73f) 「ローディ」
- シューベルト 弦楽四重奏曲第1番 ト短調 D.18
- ベートーヴェン 弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調 Op.18-1
の3曲です。とくに、若いベートーヴェンの作品が大好きな中でも、とりわけこの第1番がお気に入りなので、プログラム発表以来ずっと楽しみにしていました。
会場は長方形のスタジオの短辺側にステージを置いたもので、聴衆は80〜90人は入っていたでしょうか、けっこうぎっしり感があります。楽器の配置は、左から第1ヴァイオリン(犬伏亜里)、第2ヴァイオリン(中島光之)、ヴィオラ(倉田譲)、チェロ(茂木明人)となります。
第1曲、モーツァルトが少年時代のイタリア旅行中に作曲され、ウィーン時代に完成されたという第1番。「ローディ」というのは、宿泊先の地名だそうです。第1楽章:アダージョ、いきなり緩徐楽章から始まりますが、穏やかな中にも音楽に華があると感じられます。第2楽章:モーツァルトらしい活発なアレグロ。第3楽章:メヌエット〜トリオ、高域のヴァイオリンと中低域のヴィオラ・チェロの対比が魅力的です。第4楽章:ロンド、アレグロ。犬伏さん、楽章間のちょっとした合間に、右手で譜面をめくりながら左手の指で弦をはじいて音を確かめています。ハーモニクス?無駄のない合理的な動きで、なんとなく普段からテキパキとした方かもと想像してしまいました(^o^)/
続いて第2曲、シューベルト14歳の作品です。おそらく家庭内で演奏するなどの目的で作られた曲なのでしょうが、私には初体験。意外にも劇的な面もある音楽でした。第1楽章:アンダンテ〜プレスト、ヴィヴァーチェ。間を合わせるのが大変そうですが、力強さや迫力を感じさせます。すでにベートーヴェンを経験していたであろう少年作曲家のかっこいい音楽。第2楽章:メヌエット〜トリオ、一転して弱音器を付けたかわいらしい音で演奏されます。第3楽章:アンダンテ、弱音器を外して演奏される緩徐楽章です。第4楽章:プレスト。再び訴える力のある劇的な音楽となります。後年の室内楽曲の充実しか知りませんでしたが、若い時代の交響曲は全集で耳にしており、若いシューベルトの弦楽四重奏曲も魅力的なものがあるのだなと知りました。得難い経験となりました。
ここで15分の休憩です。
後半は、ベートーヴェンの第1番。1801年に改訂完成とありますので、作曲者が30歳頃の作品です。モーツァルトやシューベルトとは異なり、少年時代のものではなくすでに成熟した大人の作品。しかも、作品18の6曲のうち1番目に来るものとして番号を付けられたものですから、できの良い方を第1番にするというベートーヴェンの流儀からみても、青年期の傑作と言ってよかろうと思います。
第1楽章:アレグロ・コン・ブリオ。ごく自然な始まりです。チェロの中音域の音色が優しい。過度に意味有りげにせずに、演奏の自然なたたずまいは、多くの演奏経験のゆえでしょうか。第2楽章:アダージョ・アフェットゥオーソ・エ・アパッショナート。2nd-Vn、Vla、Vcによる中低音の中に、1st-Vnが悲しげな旋律を奏します。作曲者はロミオとジュリエットの墓場の場面を想像して作曲したのだとか。しだいに表情は穏やかなものに変わっていきますが、たいへん魅力的な音楽を説得力のある演奏で堪能しました。三度の休止が効果的。
第3楽章:スケルツォ、アレグロ・モルト〜トリオ。前楽章からは一転して、青年期ベートーヴェンらしい、活発なスケルツォです。とりわけ 1st-Vn は自信と思い切りの良さが求められるのだな、と感じました。
第4楽章:アレグロ。晴れ晴れとした開放感を感じさせる音楽、演奏です。これですよ、これ! 緊密な響きの中にやわらかな優しさを含みながら、闊達な音楽が広がります。実に若いベートーヴェンらしい、ステキな音楽です。いいなあ! 弦楽四重奏の充実と楽しさを、たっぷりと味わいました。
聴衆の拍手に応えて、アンコールはハイドンの弦楽四重奏曲第1番の第1楽章を。今回は、「1」づくしの回でした。
次回の第90回定期演奏会は、2024年1月22日(月)、19時から、同じ県民ホール・スタジオ1 にて。山響のクラリネット首席の川上一道さんを迎えて、ミュラーのクラリネット四重奏曲第1番ほか。
いよいよ第90回ですか。これはイソ弦楽四重奏団の100回の定期演奏会を超えるのが現実的に見えてきたようです。年4回の定期演奏会であれば25年で100回。ファンとしても応援したい。団員の皆さんのご健康を祈ります。