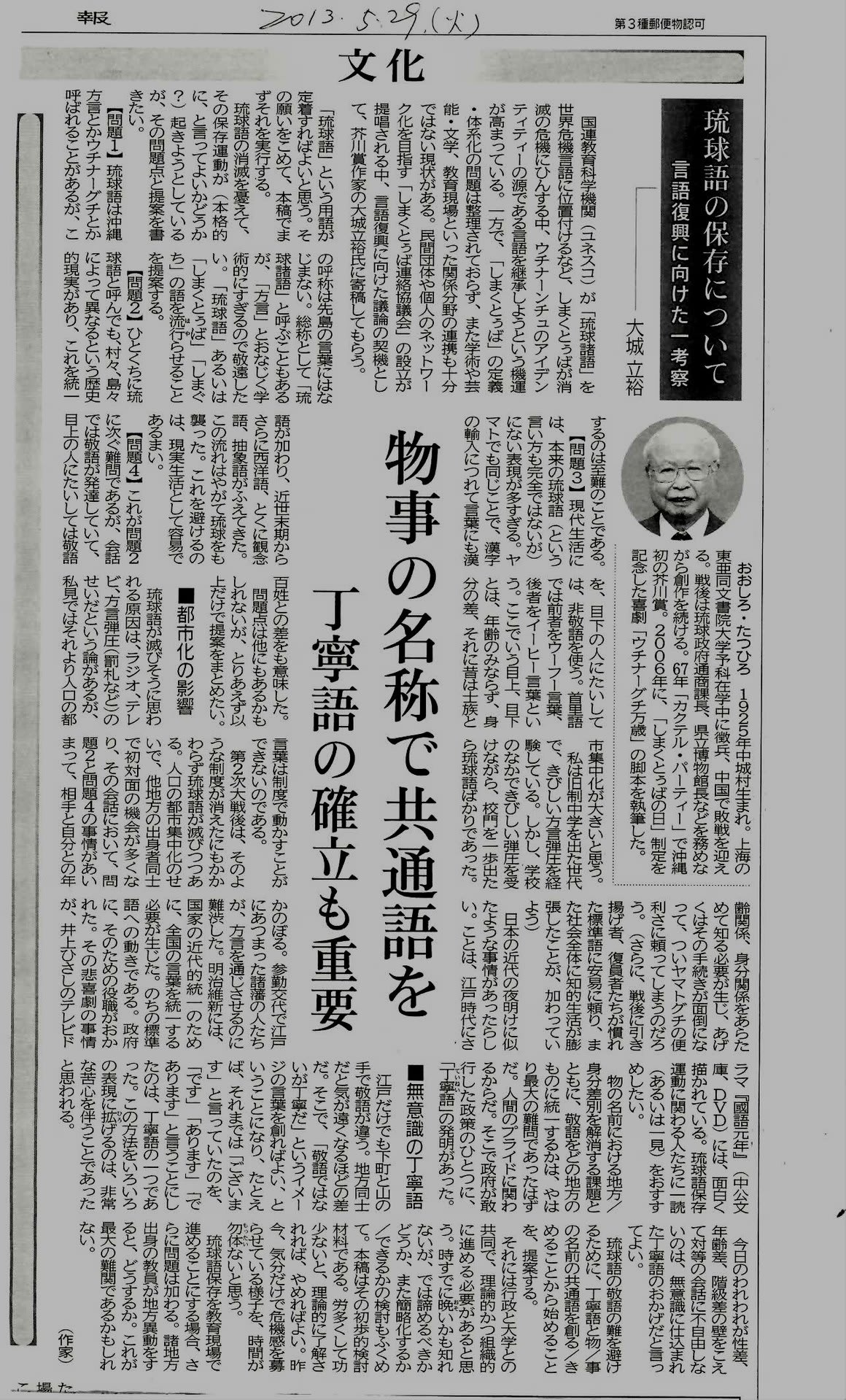
言語学者の本音はやはり首里・那覇を中心とした正書法の確立をして後に琉球諸語の全体に迫る二段階方策だと見える。中軸言語がしっかりしないと、他の諸語も揺れるね。独自の試みは、宮古語、八重山語、奄美語とそれぞれの試みがなされている。組踊や沖縄芝居、現代演劇(現代沖縄芝居)にしても中軸になる言語は琉球語だが、首里・那覇の折衷語である。その中に北谷ことば、糸満ことば、小録ことば、金武ことばなど、また地域によって個性のある言語運用がなされている。面白い。芝居もその言語の差異を喜劇(狂言)に仕立てているのもある。表記された言語と口語との差異もある。その辺の二重性の壁をどう解決するのかも興味深い。そのまま音韻を表記する方法が昨今の形式にも見える。ローマ字表記になるのか、漢字ひらがな表記になるのか、もっと集約されていく必要があるのだろう。独自性や自決権、表現の自由との関係も含め、この軍事植民地沖縄を脱構築する文化運動が緻密に前進することを念じるばかりである。
日米安保体制を支持する多くの日本人が沖縄の恒常的軍事植民地化を容認する姿勢に変化がない限り、沖縄が独立を希求する流れは加速するのだろうか?植民地的差別構造の中に埋没していくのだろうか?全くの同化ですべて日本システムの中の吹き溜まり(ゴミ捨て場)のような位置づけに終始するのではないと思いたい。言語権とその修復の考えはいいね。共通日本語をうまく取り入れた琉球語の体系で成り立った歴史でありそれをもっと効率的に運用していくことも可能かもしれないね。つまり日本語、漢字、琉球語のハイブリッドの共通琉球語の表記を誕生させることは、どうだろう。
先日英語も日本語もウチナーグチも流暢なハワイ4世の方とお話した。沖縄芝居のビデオを見て、また歌・三線をたしなんでウチナーグチをマスターしたのである。びっくり!沖縄芝居をたくさんみると、ウチナーグチは上手になるのです。氏にたくさんお話してほしいと思った。ハワイのウチナーグチの面白表現に腹を抱えて笑った。村田さんのお話はとても愉快で、沖縄中で三線をもって講演してほしいと思う。



















