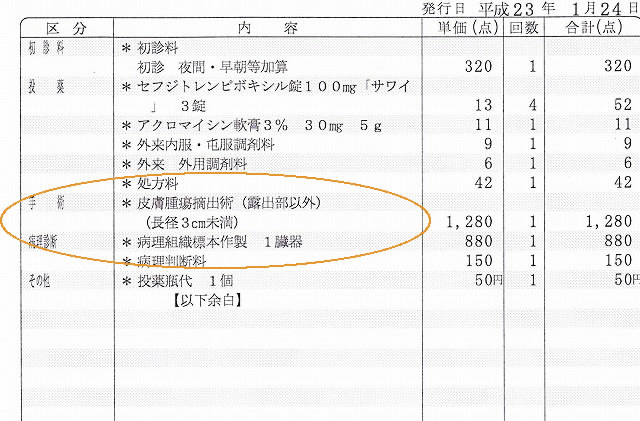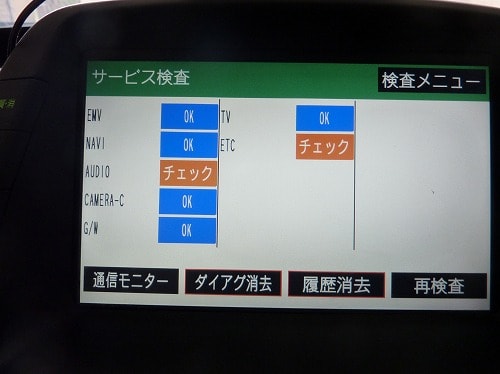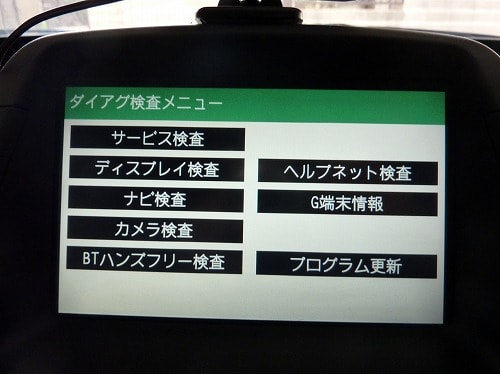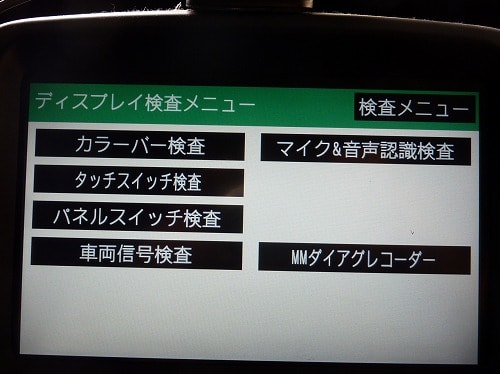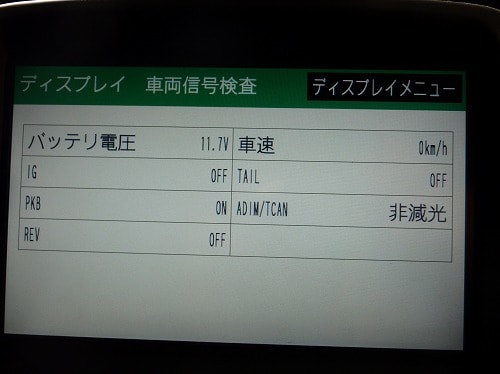蟹江城へ行ってきました。
場所は名古屋の西、海部郡蟹江町のほぼ真ん中です(現地案内板です)。

予習のため、まずは蟹江町歴史民俗資料館へ行きました。
ちなみに、ここの住所は愛知県海部郡蟹江町城です。

同じ建物に、産業文化会館と中央公民館分館が同居しています。
最上部が城を意識したデザインになっています。
資料館は、入場無料でした。
ここでの、予習した成果を紹介します。
現在では、内陸となっているこのあたりですが、戦国時代は海岸線でした。
したがって、桑名(伊勢国)あたりからの攻めに対する防御のために、永享年間(1429~1441)に北条時任が築いたそうです。
この城が脚光を浴びたのは、1584年(天正14年)の蟹江合戦の舞台となったときです。
小牧長久手の戦いで、徳川家康に大敗を喫した羽柴秀吉は、その雪辱と伊勢湾の制海権、そして織田信雄と家康の間を離反させるために挙兵いたしました。
滝川一益を主将に九鬼水軍を伴いいったんは優勢に進んだのですが、支城である大野城(尾張国海東郡)主の山口重政は助力を拒み、織田徳川連合軍の反撃の前に、秀吉は撤退を余儀なくされます。
こうして、秀吉と家康の表だった戦いは終焉を迎えました。
資料館では、蟹江城への道順を記したプリントを配布しています。
路地のような細い道を歩いて数分です。
住宅地の一角に石碑が建っているだけでした。

唯一、本丸の井戸が残っていました。
おそらく、最近まで使っていたのではないでしょうか。
それでなければ、じゃまなので取り壊してしまいますよね。
小さな城の小さな戦いですが、蟹江合戦が後世に与えた影響は大きいです。
まずは、羽柴秀吉と徳川家康
この戦いを最後に軍事的な争いを避けました。
秀吉は得意な外交戦略に方針を変えました。
関白となり家康よりも上の立場となるとともに、妹の旭姫を嫁がせ、母の大政所まで人質に出し、懐柔をはかります。これには家康も折れて、豊臣の政権が樹立することとなりました。
滝川一益
蟹江城主の留守を預かっていた前田長定は、かねて羽柴方の滝川一益に通じており、一益軍を蟹江城へ招き入れてしまいます。
しかしながら、織田・徳川連合軍に包囲された一益は対抗できず、長定の首をはねて降伏
してしまいます。
かつては、織田家有数の武将と言われていましたが、本能寺の変のあたりから凋落し始めた一益にとってこの件は決定的打撃となりました。
「命惜しさに長定の首をはねた卑怯者」と誹られ、以降漂泊・餓死したと伝えられています。
佐治一成・お江
佐治家は、知多半島の大半を領した豪族です。
秀吉は佐治一成を懐柔しようと考え、お市の三女のお江との婚姻をまとめたようです。
しかし、一成は合戦後に家康が三河へ帰陣する途中の佐屋街道の渡において、家康に船を提供し、秀吉の怒りを買ってしまいます。
このため、お江は最初の夫と離縁させられてしまいました。
茶粥
米をほうじ茶または緑茶で炊いたものです。
調べてみると茶粥は奈良・京都・大阪・和歌山で見られる食文化で、北前船の影響で西日本の各地に広がったそうです。
ただし、私の知っている限り尾張にはこの文化が残っていません。
唯一、この蟹江町だけ存在するのです。
これは蟹江合戦の折、連合軍に包囲された場内では、水をくむことも米をとぐことも満足に出来ず苦肉の策として茶の湯に米を入れたのが始まりだそうです。
蟹江町歴史民俗資料館より