前の記事で紹介した吉田俊純著『水戸学の研究 ー明治維新史の再検討』(明石書店)、大変に興味深い内容である。若干の論点を紹介してみたい。
著者は、水戸学が他藩にどのような影響を与えたのかを考証し、水戸学が明治維新に果たした役割が大きかった事実を論証していく。「水戸学と横井小楠」「水戸学と吉田松陰」「水戸学と長州奇兵隊」・・・・といった具合である。
「幕末でもっとも開明的な思想家」とも評価される横井小楠と、長州尊攘派のイデオローグ吉田松陰の水戸学の受容の仕方は対照的なのが興味深い。横井小楠は若いころには水戸学に心酔したが、後にその危険性に気付き、それを徹底的に批判するようになる。逆に吉田松陰は、当初は水戸学に批判的であったが、密航に失敗して萩に幽閉されてから、徹底的に水戸学を受容したテロリストになっていくのである。
横井小楠の尊攘テロリスト批判・神道批判
肥後の横井小楠は、若いころに藤田東湖と交流し、藤田の信奉者になる。しかし、水戸尊攘派が過激化するのを見るにつけ、尊王論と結びついた藤田の「誠」は、手段をわきまえない術策に陥ることは必然であると気づく。小楠は、水戸学の信奉者は「戦国の山師と同様」とまで述べ、尊王攘夷論を批判する。言い換えれば、藤田東湖の「尊王攘夷」とは、「誠」を大義に掲げつつ、そのためには、ありとあらゆる卑劣な手段を講じてもかまわないと考えるテロリズムに帰結することは必定であると批判するようになった。
水戸学は、儒教道徳と神道を結び付けたところに特徴があるが、小楠その危険性を察知して、神道も徹底的に批判するようになる。1864年には井上毅に対して「神道の害は甚だしく、水戸や長州のような神道を奉じる輩は、君父に向かって弓を引くまでの不埒者となった」と述べている。(『沼山対話』。井上毅は、「神道」を伏字にして紹介しているが、著者によれば、伏字の中に「神道」が入ることは明白である)
小楠は、『古事記』の神代神話も含めて全て真理と考えるようなカルト思想が、国際正義に背を向けた偏狭な国粋主義、さらに原理主義テロリズムに発展することを悟り、水戸と長州の過激派批判に転じた。そして、「儒教」の中から国際的に通用する普遍性を抽出し、儒教に基づいて西洋帝国主義も批判するという開明的思想家となった。
小楠と教育勅語
しかしながら、『水戸学の研究』の著者の吉田俊純氏は、小楠の思想の限界性も指摘していて興味深い。すなわち、小楠が神道を批判したとして、水戸学全体を否定したとは言えないからだという。著者は、明治に小楠が生きていたとしても、開明的な方向にのみ進んだとは限らないという疑問を呈し、その根拠として、「教育勅語は、小楠の影響を強く受けた後輩の元田永孚と井上毅によって作られたことも、思い起こすべきである」と述べている。
安倍政権の思想のキーワードでもある「教育勅語」は、国家神道と儒教道徳の混成物で、どちらかというと神道色を薄めて、儒教道徳を前面に出したという点、水戸学的要素がみられる。教育勅語の精神が、軍部の玉砕精神にもつながっているという側面は濃厚である。この教育勅語が、開明的思想家・横井小楠の影響を強く受けた後輩の元田永孚と井上毅によって起草されたという事実は、意味深であると言わねばなるまい。何故そうなってしまったのであろうか?
吉田松陰の水戸学受容とテロリズム
つぎに吉田松陰を見てみよう。吉田松陰は、密航に失敗する前、佐久間象山門下である当時は、水戸学に批判的であった。ペリー来航時の嘉永6年(1853)には、兄宛ての手紙で、「水戸の老公(徳川斉昭)でも阿部閣老(阿部正弘)でも、海外事情を何も知らないのでは戦の仕様がない」と述べている。安政元年(1854)には、やはり兄宛ての手紙で、水戸の会沢正志斎を批判して、「会沢は『新論』で偉そうなことを述べているが、攘夷だなんだと言ってみても、軍艦の作り方一つ知らないではないか」という趣旨の批判をしている。
吉田俊純氏の著作には書いていないが、この松陰の言葉は、佐久間象山の水戸学批判をそのまま展開したものであろう。西洋技術を何も知らない水戸学の学者たちが、「尊王だ攘夷だ」と叫んでみたところで、いざ西洋から侵略されれば、何の役にも立たない空言に過ぎないという批判である。
松陰は象山からそう言われ続けて、オランダ語や物理学など勉強しようとしてみたが、彼は語学も数学も全くダメで、一向に身に付かなかった。彼は思想のセンス的には、完全に藤田東湖的であったのだ。
松陰に、理系的な素養はなかった。頭では、象山の教えが分かっていても、西洋技術を学ぶセンスは自分にはない。それで悩んで、「ならばアメリカに渡ってしまえ」と考えたのかも知れない。(これも私の推測であるが)
周知のように松陰は密航に失敗して萩に幽閉される。そこで佐久間象山のくびきから逃れることができた。やれ「オランダ語を学べ」、それ「物理学も勉強しろ」、「西洋を知らずして西洋に勝てるか」といった小言ばかり述べる口うるさい師匠が目の前からいなくなったのである。
萩の獄中で、松陰は水戸学の著述をむさぼり読み、また本居宣長の『古事記伝』も読破して、『古事記』に書いてあることは神代の神話も含めて、すべて真理であり、疑うことは許されないと考える国家神道の原理主義者になった。佐久間象山がそれを知れば、唖然として松陰を叱ったであろうが、象山はいない。
松陰は水戸学と本居学を折衷させて、自己の思想を確立する。そしてついには、「尊王攘夷」の四文字のお題目を唱えれば道は開ける、身は滅びても魂が残ればよいと、と宗教原理主義的な玉砕テロリズムを鼓舞するようになる。かくして、合理的な思考をしていた象山門下時代の吉田松陰とは全く別人のようになってしまった。
水戸学の思想はテロにつながると危険視した横井小楠の危惧を、まさに体現したのが吉田松陰とその門下生たちであったといえるだろう。
著者は、水戸学が他藩にどのような影響を与えたのかを考証し、水戸学が明治維新に果たした役割が大きかった事実を論証していく。「水戸学と横井小楠」「水戸学と吉田松陰」「水戸学と長州奇兵隊」・・・・といった具合である。
「幕末でもっとも開明的な思想家」とも評価される横井小楠と、長州尊攘派のイデオローグ吉田松陰の水戸学の受容の仕方は対照的なのが興味深い。横井小楠は若いころには水戸学に心酔したが、後にその危険性に気付き、それを徹底的に批判するようになる。逆に吉田松陰は、当初は水戸学に批判的であったが、密航に失敗して萩に幽閉されてから、徹底的に水戸学を受容したテロリストになっていくのである。
横井小楠の尊攘テロリスト批判・神道批判
肥後の横井小楠は、若いころに藤田東湖と交流し、藤田の信奉者になる。しかし、水戸尊攘派が過激化するのを見るにつけ、尊王論と結びついた藤田の「誠」は、手段をわきまえない術策に陥ることは必然であると気づく。小楠は、水戸学の信奉者は「戦国の山師と同様」とまで述べ、尊王攘夷論を批判する。言い換えれば、藤田東湖の「尊王攘夷」とは、「誠」を大義に掲げつつ、そのためには、ありとあらゆる卑劣な手段を講じてもかまわないと考えるテロリズムに帰結することは必定であると批判するようになった。
水戸学は、儒教道徳と神道を結び付けたところに特徴があるが、小楠その危険性を察知して、神道も徹底的に批判するようになる。1864年には井上毅に対して「神道の害は甚だしく、水戸や長州のような神道を奉じる輩は、君父に向かって弓を引くまでの不埒者となった」と述べている。(『沼山対話』。井上毅は、「神道」を伏字にして紹介しているが、著者によれば、伏字の中に「神道」が入ることは明白である)
小楠は、『古事記』の神代神話も含めて全て真理と考えるようなカルト思想が、国際正義に背を向けた偏狭な国粋主義、さらに原理主義テロリズムに発展することを悟り、水戸と長州の過激派批判に転じた。そして、「儒教」の中から国際的に通用する普遍性を抽出し、儒教に基づいて西洋帝国主義も批判するという開明的思想家となった。
小楠と教育勅語
しかしながら、『水戸学の研究』の著者の吉田俊純氏は、小楠の思想の限界性も指摘していて興味深い。すなわち、小楠が神道を批判したとして、水戸学全体を否定したとは言えないからだという。著者は、明治に小楠が生きていたとしても、開明的な方向にのみ進んだとは限らないという疑問を呈し、その根拠として、「教育勅語は、小楠の影響を強く受けた後輩の元田永孚と井上毅によって作られたことも、思い起こすべきである」と述べている。
安倍政権の思想のキーワードでもある「教育勅語」は、国家神道と儒教道徳の混成物で、どちらかというと神道色を薄めて、儒教道徳を前面に出したという点、水戸学的要素がみられる。教育勅語の精神が、軍部の玉砕精神にもつながっているという側面は濃厚である。この教育勅語が、開明的思想家・横井小楠の影響を強く受けた後輩の元田永孚と井上毅によって起草されたという事実は、意味深であると言わねばなるまい。何故そうなってしまったのであろうか?
吉田松陰の水戸学受容とテロリズム
つぎに吉田松陰を見てみよう。吉田松陰は、密航に失敗する前、佐久間象山門下である当時は、水戸学に批判的であった。ペリー来航時の嘉永6年(1853)には、兄宛ての手紙で、「水戸の老公(徳川斉昭)でも阿部閣老(阿部正弘)でも、海外事情を何も知らないのでは戦の仕様がない」と述べている。安政元年(1854)には、やはり兄宛ての手紙で、水戸の会沢正志斎を批判して、「会沢は『新論』で偉そうなことを述べているが、攘夷だなんだと言ってみても、軍艦の作り方一つ知らないではないか」という趣旨の批判をしている。
吉田俊純氏の著作には書いていないが、この松陰の言葉は、佐久間象山の水戸学批判をそのまま展開したものであろう。西洋技術を何も知らない水戸学の学者たちが、「尊王だ攘夷だ」と叫んでみたところで、いざ西洋から侵略されれば、何の役にも立たない空言に過ぎないという批判である。
松陰は象山からそう言われ続けて、オランダ語や物理学など勉強しようとしてみたが、彼は語学も数学も全くダメで、一向に身に付かなかった。彼は思想のセンス的には、完全に藤田東湖的であったのだ。
松陰に、理系的な素養はなかった。頭では、象山の教えが分かっていても、西洋技術を学ぶセンスは自分にはない。それで悩んで、「ならばアメリカに渡ってしまえ」と考えたのかも知れない。(これも私の推測であるが)
周知のように松陰は密航に失敗して萩に幽閉される。そこで佐久間象山のくびきから逃れることができた。やれ「オランダ語を学べ」、それ「物理学も勉強しろ」、「西洋を知らずして西洋に勝てるか」といった小言ばかり述べる口うるさい師匠が目の前からいなくなったのである。
萩の獄中で、松陰は水戸学の著述をむさぼり読み、また本居宣長の『古事記伝』も読破して、『古事記』に書いてあることは神代の神話も含めて、すべて真理であり、疑うことは許されないと考える国家神道の原理主義者になった。佐久間象山がそれを知れば、唖然として松陰を叱ったであろうが、象山はいない。
松陰は水戸学と本居学を折衷させて、自己の思想を確立する。そしてついには、「尊王攘夷」の四文字のお題目を唱えれば道は開ける、身は滅びても魂が残ればよいと、と宗教原理主義的な玉砕テロリズムを鼓舞するようになる。かくして、合理的な思考をしていた象山門下時代の吉田松陰とは全く別人のようになってしまった。
水戸学の思想はテロにつながると危険視した横井小楠の危惧を、まさに体現したのが吉田松陰とその門下生たちであったといえるだろう。














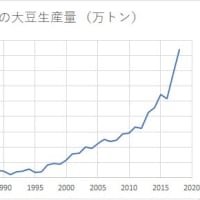

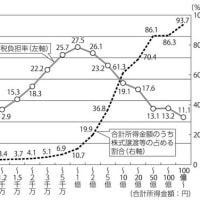



吉田俊純氏の著書は、
『水戸学と明治維新』(2003年、吉川弘文館)
を読んでいましたが、その集大成がご案内の大著なのですね。近々に入手して、私も考えてみたいと思います。
それにしても、松陰の《転向》は、戦時下、「科学的社会主義」の信奉者たちが陸続と《水戸学》に《転向》する姿とダブります。
思想史文脈というよりも、社会学的《幕末youth bulge》との関連を疑わせます。
とても触発される記事で、こちらの頭も動き出した気がします。
玉砕主義の水戸が壊滅したように、長州も本来は同じ途をたどるのが必然だったように思えます。しかし、イギリスがテロリストたちに軍事支援してしまったことが日本の運命を狂わせたといえるでしょうか。
西洋文明に背を向けた国粋主義者たちが、西洋文明の最新鋭の兵器を労せずして手にしてしまったという皮肉・・・・。
決して彼らが正しかったから勝ち取った権力などではないのに、それを根本的に勘違いしているのが安倍政権と言えそうです。
以下、国史大辞典の「原市之進」の項にこうあります。
「文久元年(一八六一)五月東禅寺事件が起って幕府の攘夷派への圧力が強まると、大橋訥庵らとともに老中安藤信正の要撃を謀議した。」
原は、昌平黌に留学した、水戸徳川家で嘱望されたエリートです。その一方で、会沢正志斎に学び、従兄の藤田東湖にも師事しました。後には、慶喜の懐刀として慶喜が徳川宗家を継ぐと「幕臣」目付となり、開国政策を推進しますが、その彼でさえ、テロリストになる寸前だった
過去を有してます。
水戸学の特質だけなのか、それともイスラム過激派テロを連想させるような(アルカイーダなどのテロ実行犯は欧米留学している知的エリートを含む)、社会学的(人口学的)文脈なのか。
攘夷派と公儀派のセクト間の暗闘は、水戸徳川家だけでなく、長州毛利家や薩摩島津家ででさえ(ご著書でご指摘頂いて蒙を開かれました)、この時期どこの家中でも噴出していました。またそれぞれに過激派と穏健派がいて、水戸徳川家など複雑怪奇です。原暗殺の下手人は水戸尊攘過激派でした。
西方キリスト教内部での最大のセクトは、ローマン教会と改革派諸教会ですが、ローマ教会の内部にも多様な会派はありつつ、教皇の下に統一性を保っています。一方、改革派諸教会は教義の微妙な違いで分裂し独立した教会組織になりました。
マルキシズムもその内部のセクト主義は満天下に明らかで、過激派の敵に対するその凄惨なテロリズムはブログ主様の近著でご指摘されているように19世紀の長州テロリズムと酷似しています。
テロリズムの思想というよりは、テロリズムのエートスの解明が必要だと感じます。
そういえば、かの渋沢栄一でさえ、若いころは水戸学にかぶれて、高崎城襲撃や横浜焼き討ちを計画しています。後年の「日本資本主義の祖」としての渋沢の開明的事業の数々を想起すると、にわかに信じられない思いもしますが、事実です。
開明的な原や渋沢や横井小楠ですら、若いころは水戸学の影響下のテロリスト予備軍だったわけですから、まさに水戸学恐るべしと言えるでしょう。
しかし、その誤りに気付いて、そこから脱却した彼らはやはり偉かったと思います。
>社会学的(人口学的)文脈なのか
長州や薩摩は人口増大地域でしたが、貧しかった水戸は人口それほど増えていないと思いますので、人口学のみでテロの原因を説明するのは難しいと思います。西日本の人口増大地域でもテロ思想に感染しなかった地域もあるわけですから。
人口という下部構造の要因と、感染力の強い過激テロ思想という上部構造の要因と分けて考える必要があろうかと思います。
関さん、竹田青嗣氏の『哲学は資本主義を変えられるか』が、ようやくきのう発送されたとのことです。ご示唆によりましてその後いささか考えるところがありますので、到着を待って繰り返し読み、来週末またはその翌週週末に報告をこころみます。
吉田俊純氏の『水戸学の研究は』先の日曜日に到着して一週間取り組みましたが、引用されている和文になじめないことから釈然としないところが多く難儀しております。
ともあれ同書において丁寧に繰り返されている吉田氏のお考えを手触りでたどることはできるように思いますので、題記について些か思いますところを報告いたします。
関さんの一連の御記事に導かれて、これまで見て見ぬふりをしてきました水戸学についてはじめて多少なりとまともに知ることができました。
そして、これまでに印象深く読みかじったものが関連していることを思いだして読み返し、あらためて考えました。煩瑣にわたりますが、いま眼にしている内外の政治経済のシーンにつながるもののように思えますので、一連のものとして無理やりまとめてみます。
『日本宗教史』(岩波新書、2006年)において著者、末木文美士氏(1949年生まれ)は、「幕末の尊皇攘夷のイデオロギー的基盤としては、復古神道ととともに、後期水戸学が大きな役割を果たした。とりわけ会沢安(正志斎、1782ー1863)の『新論』(1825)は尊皇攘夷のバイブルとして、その影響は計り知れない。・・・天皇による祭政一致を求め、西洋諸国の侵略に対する防衛の道を探る本書の基本的な構想は、明治以後の国体論にもそのまま反映することになった」(p175)としています。じつは末木氏の問題意識は;
「『尊皇攘夷』は決して幕末の一時的なイデオロギーではない。一方でアマテラスー天皇の系譜に神話的基盤を置き、他方で欧米の進出の根幹をキリスト教に見て、それへの対抗として神道に拠りどころを求めるのは、まさしく明治になって完成する体制に他ならない。それは一部の支配層のイデオロギーに留まらず、国民全体を巻き込んで、草の根の隅々まで浸透していく。それは、<古層>の「発見」が生み出した新たな<古層>というべきものである。その根深さの由来は、いまだ十分に解明されていない」(p175ー176)
というところにあります。いま眼前に見ているものがこれなのか、にわかに信じがたい思いにかられますが、路傍で見たほぼ不死身のマムシのようにあくまで鎌首をもたげる、自愛心に裏打ちされた無条件の国家自尊意識というべきものの不気味さを思いますと、そうなのかもしれないと絶望感に駆られます。「その根深さの由来」?は、と。
そこでじつは思いますに、「尊皇攘夷」というのは、江戸期という過去の現実のなかから「明治維新」を実現したものであるというよりむしろ、現代における国家意識の古層であり、それがつねに「明治維新」を照らし出すことによって、神話的建国という反駁不可能な古層をよみがえらせるものではないだろうか、それを「長州史観」と枠取って考えていてよいのだろうかと・・・正直恐怖感を抱きます。
末木氏は、「儒教的(ただし日本的に変容された)倫理にもとづく家父長制は前近代的、封建的なものと考えられがちであるが、実際には明治になって教育勅語によって全国民(臣民)の共通の道徳として普及したのである」(p187)と言います。
本人の資質徳性また行動特性とはまったく無関係に皆がひれ伏すという現代の政治シーンを認識するのに、家父長制というのはまことに的確なものではないかとさらに暗い気持ちになりました。
末木氏の引用の最後に、決定的なことを。『古事記』の建国神話について氏は「・・・ここでは国土と神々の生誕は説かれるが、人の生成は説かれないということである。・・・一般の人々はどうやら国土とともに生まれたらしく『青人草』『人草』と呼ばれ、いわば国家の付属物のように扱われている。それ故、その神話はあくまで支配者にとって支配の正統性を語るものであり、一般の人々はまったく問題にされていない」(p17)
と、語っています。かの「明治維新」を代表として、建国を神話とすること自体を完膚なきまで消し去ることを目ざすべきことがよくわかります。
しかし、ここで突然、小島毅氏(1962年生まれ)の『靖国史観』(ちくま新書、2007年)から福井県勝山市にある平泉寺が廃仏毀釈で神社となった白山神社の世襲三代目宮司となった平泉澄について、孫引きとなるものを含めて牽きますと;
「植村和秀氏は、戦後思想の巨人丸山眞男との比較によって、平泉の『歴史神学』の性格をあぶり出している。『歴史的感覚と宗教的感覚こそは、丸山に総体的に乏しかった感覚であった。/そしてまた、神と人との断絶を重視し、近代と中世の相違を重視する丸山は、ヨーロッパ的と呼ぶよりも、むしろやはり反歴史的であり、世俗的にすぎるのである。(『丸山眞男と平泉澄』三二六頁)』(p85ー86)
と。「世俗的」というのは地上的合理性と解してよいと思えますが、歴史神話を破るために何が必要なのか考えさせられます。<古層>と言えど、表層である地殻であるわけで、比喩的に言いまして、その下で流動しているマントル(上部マントル?)を動かすということになるのでしょうか。
吉田俊純氏による水戸学についての議論に入る前に、佐藤弘夫氏(1953年生まれ)の『神国日本』(ちくま新書、2006年)のコア的論点である、中世(鎌倉時代)蒙古襲来を機にネガからポジに転じてピークに達した神国思想に対する「現代における常識的イメージの幻想性」の指摘です:
「まず・・・日本を神国とみなす理念が蒙古襲来を待ってはじめて誕生するものではなかった・・・日本=神国の主張は『日本書紀』時代から近現代に至るまでいつの時代にも見られるものだった。・・・第二点目は、・・・中世の神国思想の骨格は、・・・普遍的存在である仏が神の姿をとって出現したから『神国』なのである。・・・現実のさまざまな事象の背後に普遍的な真理が実在することを説くこうした論理が、特定の国土・民族の選別と神秘化に本来なじまないものであることはいうまでもない。第三番目に、・・・より端的にいえば、神国思想は仏教の土着の過程で生み出された思想だったのである。最後に・・・天皇の存在は神国の目的ではなく、神国が存続してゆくための手段とみなされていた。(p196ー197)
と、いうのが「神風が吹いた」中世の「神国」であったわけですが、近世、江戸期になって世界観が世俗的なものになり、北方民族の征服王朝である清が大陸を制するという「中華の消失」に対応して「日本的華夷秩序」と言うべき自尊意識が高まり、また体制の政治経済的動揺と外圧の高まりに応じて求心力が天皇に帰せられる動きの結果として「明治維新」となり、神仏分離によって「純粋な神々の世界」が近代になって誕生したということになります。(参照:p200−214)
普遍的原理による彼岸(天上)と此岸(地上)の二重構造を持っていた「神国」が、「明治維新」近代化によって特殊国粋原理による世俗地上の「神国」に変貌したことになります。
末木文美士氏が指摘するとおり、「尊皇攘夷」は「明治維新」の、というより大日本帝国の原理であり、奇しくも、りくにすさまにおしえていただいた小倉紀蔵氏(1959年生まれ)による『朱子学化する日本近代』(藤原書店、2012年)の帯にしるされたとおり「明治から、日本の ”儒教化” は始まった」ということになります。
吉田俊純氏(1946年生まれ)は、後期水戸学とりわけて「東湖学」こそが「明治維新」を支えたイデオロギー的背骨であると『水戸学の研究』(明石書店、2016年)において主張しておられます。
維新勢力が、いまだ封建思想である水戸学を運動思想として克服し近代思想に換骨奪胎することができたゆえに「明治維新」が起きたとする従来の考え方に挑戦したものです。
水戸学における封建的要素は、藤田幽谷/会沢安から藤田東湖への以降において克服されたというのが吉田俊純氏のメインの論点であると思えます。
吉田俊純氏の立論構造を強引にまとめますと、引用ばかりになってまことに恐縮ですが:
「後期水戸学の時代的意義は、攘夷論を展開したことにある。しかし、・・・本来は外患の危機は、内憂の危機を解消するための手段でしかなかった。(p35)・・・会沢は『新論』において国体を強調し、神道を通じて権力が民衆の心をとらえることを力説したのである。しかし、幽谷・会沢の段階は民衆に対して激しい不信感を抱いていた。したがって、彼らは統治=教化によって、よき風俗の形成を説いたのである。・・・幽谷の理想としたのは「中世」的な自給自足的な農村であった。一方、幽谷は水戸藩領の農村の現実以上に、商品経済の発展している農村の様子を描き出したが、幽谷の目的は、もちろんこれを否定することにあったのである」(p36)
「東湖によって水戸学が国学に傾斜したとは、・・・第一に、非合理的な古典を信奉することによって、そこに記された古代を、真に理想の社会ととらえたことである。・・・第二に、・・・東湖はこの宣長の見解を採用して、「国体の尊厳」を風俗に帰したのである。風俗という以上は、風俗を形成する絶対多数の民衆を評価しているとみなさざるを得ない。・・・それ以前の水戸学者と違って、民衆への不信感が解消されているのである。・・・より積極的には、東湖は権力の基盤を、民衆に置くようになったとみなすことができる。(p37)・・・「国体の尊厳」を風俗に帰したことは、士農工商の身分制とは、異質な体制を指向していることを意味しているのである。豪農層をはじめとする多数の農民を、水戸藩尊攘派が組織化できた思想的背景には、東湖のこの思想があったとみなすことができるのである。もちろん、東湖によってもたらされた思想的転換は、水戸学が農村と取り組んだ成果でもあったのである」(p38)
「・・・水戸学=東湖の思想は、藩外に多大の影響を与え、明治維新の思想的推進力として作用した。その典型は、長州藩における諸隊の編制である。諸隊の編制によって、権力の側は民衆のエネルギーを汲み取ることができるようになり、藩幕体制を否定し、近代国家を建設することができたのである、(p38)松陰も一月ほど水戸に滞在したとき、・・・藩内を回り、水戸藩尊攘派の基盤がしっかりと農村に根づいていることを観察したのであった。・・・小場村の所伊賀右衛門から斉昭宥免運動に奔走した話を聞き、感動して作った詩は『・・・草莽に豪英を見る』と結ばれているのである。・・・松陰が草莽をとりあげるのは、このとき以降のことである」(p129)
「・・・だからといって、東湖はあくまでも支配者の側に立った思想家であったから、・・・民衆の立場に立って論理を展開したわけではない。もちろんその所説の中心は、・・・人間関係を上下的なものとしてのみとらえる封建的な五倫であった。・・・国体の尊厳を風俗に帰したことは、いわばぎりぎりの到達点であった・・・しかしながら、このぎりぎりの到達点は、幕末から近代の歴史のなかでは、大きな意義を持ったのである。・・・明治維新は。下士と豪農・豪商層の運動によって推進された。近世的な身分制度を打ち破り、民衆的な力を権力が汲み取れるようになったとき、維新は成立したのである。東湖はその思想的基盤を準備したのであった」(p203ー204)
・・・と。ヴィクター・コシュマン『水戸イデオロギー』(ぺりかん社、1998)に対する松岡正剛氏のWeb書評によれば、「尊王攘夷という新しい言葉をつくったのは徳川斉昭であり、『弘道館記』に初出する。・・・斉昭はこう書いた、『我が東照宮、揆乱反正、尊王攘夷、まことに武、まことに文、以て太平の基を開きたまふ』という「尊皇攘夷」を、期せずして徳川打倒の原理にしたのが「東湖学」における「民衆(農民)への依拠」であり、軍事的には「水戸農兵部隊」から「長州奇兵隊」への系譜であったということになります。
じつは、ここで大きくつまづいてしまいました。吉田俊純氏の『水戸学の研究』最終章である「幕末期水戸藩農兵制の展開」で実証的に示されていることは、水戸農兵部隊は野心のある上層農民を編制した藩の軍隊であり、中下層の農民は徴発された人夫であるという事実に思われます。支配層に対して戦う「人民軍」ではありません。吉田俊純氏は「東湖学」とその系譜である「松陰学」が非支配層である民衆に依拠していたと眩惑されているのでしょうか。
「草莽の奇兵隊」は、刀槍を持たず、鎧防具をつけず、元込め銃一挺だけを持って散兵戦術で戦うという、従来の武士には不可能な戦闘を遂行するために編制された正規軍部隊であると思います。
井上勝生氏の論考「奇兵隊は革命軍だったのか」(『日本近代史の虚像と実像1』大月書店、1990年に所収)によれば、1868年に大阪に集結した奇兵隊は薩摩軍から「英式銃陣」を伝習していたとのこと。・・・赤松小三郎のことがアタマに浮かびます。
奇兵隊は人民軍や民衆の海に守られて戦うゲリラ部隊ではなく、個人的野心に駆られたプロフェッショナル軍人の正規部隊でした。あえていえば、現在のISの戦闘部隊に擬することができるかと思います。
これは吉田俊純氏を含んで「明治維新観」の問題に直接かかわることであると思いますが、後期水戸学が「東湖学」となることによって長州による反徳川クーデターとしての「明治維新」に直結したということは、関さんのご指摘のとおりであると思います。
吉田俊純氏は、『水戸学の研究』の「水戸学の影響」の「一 水戸学と横井小楠」において、「小楠は・・・水戸学は『一偏に落入』る『節義を却って失』う学問であり、『利害之私心』により『智術之計策を尊』ぶ『根底無き』学問であると激しく批判したのである」(p274)として、横井小楠が、後期水戸学のファナティシズム、独善的排他性、セクショナリズム、マキャベリズムを冷静に見て取り、「会沢学」と「東湖学」を問わず、吉田松陰のようにそのエキセントリックな特性と一体化することを拒んだことをおそらく共感を含めて指摘しています。
しかし、「儒者であった小楠は身分制を否定しない。・・・そこに欠如していたのは、民衆をいかに組織するかの視点であった」(p282)と、横井小楠が「封建エリート」から出ず、東湖また松陰のように「民衆に依拠する」ことができなかったと指摘しています。つまり「革命性」を欠いたと。
吉田俊純氏は水戸学の専門家である稀少な存在としてやむをえないことかと思いますが、公議政体論というものを視野に入れることはないように思います。したがって、横井小楠について、「開国論者」であると同時にきわめて重要なことである「公議政体論者」であったことに触れられてはおりません。
そこで、また借りもの競走のようになって恥じ入りますが、科学技術史を専門とされる理系の研究者である荒川紘氏(1963年大学卒業)による 「横井小楠の教育・政治思想」愛知東邦大学 東邦学誌 第40巻第1号( 2011年6月)からの引用で埋めつくすことをお許しください。
荒川紘氏は、横井小楠が「開国&公議政体」を主張する「開明論者」であったことと同時に、当時「公議政体論」が主潮であり、反徳川クーデター派が権力奪取時と政権掌握後に「公議政体論」を強く意識し、またそれに「ひきずられた」ことを実証的に示しています。
「小楠は清の魏源が編集した世界地理書の『海国図志』を読み、アメリカをはじめとしてヨーロッパでは『尭舜三代の治』の教育と政治が行なわれているのを学ぶ。それによって、『無道の国』と思われていたアメリカが『有道の国』であることを知って、開国論者に転換する。福井藩主の松平慶永が政事総裁職に就任すると幕府の改革策「国是七条」を建言、大政奉還と公議政体論=議会制の導入による幕政の改革を提唱した。その理想は 富国や強兵に止まらず大義を四海に布く』ことにあった。
「明治維新は、小楠とおなじく水戸学に心酔、尊王論を徹底させて、草莽崛起による討幕を叫び かけた吉田松陰の道を歩んだ。最終的には薩摩と長州を中心とする武力によって討幕は成ったの だが、新政府は発足とともに、大名や公家や有力武士からなる上局と藩の代表者からなる下局という議会をおいた。下局は『公議所』と呼ばれるようになる。その政権の政治的正統性を確保するためには時代の潮流となっていた公議政体論による議会が必要とされたのである。 しかし、版籍奉還と廃藩置県によって天皇親政による有司専制の確立をめざした新政府は、議会の排除にかかる。藩の代表者からなる議会はもとより、大名や公卿からなる議会も廃された。 中央集権による上意下達の体制が政治に浸透し、それは教育をも支配するようになる」
「・・・小楠は『富国論』で、幕府は徳川一家の利益ばかりを考えていて、天下の庶民のためという精 神がないことを批判、公共の精神をもって仁政を布き、信義を守った交易をして、藩と民の利益をうるべきである、という。・・・むしろアメリカやイギリス、ロシアこそが理想の政治のおこなわれているのであり、これらの国と交易をしないのは愚かなことあるという。・・・『アメリカではワシントン以来三大方針を立てたが、その第一は 天地の間に殺し合いほど悲惨なものはないので世界中の戦争を止めさせるというのである。第二は、世界万国から智識を集めて世界を豊かにすること。第三は、大統領の権力を世襲するのではなく、賢人を選んでこれに譲ることである。これによって君臣の関係がなくなり、政治は公共和平をめざし、法律制度から機械技術にいたるまで地球上の善いものはみな採用し活用するという理想的な政治がおこなわれている』とのべる」
「中国で禅譲は尭と舜だけであったが、アメリカではそれが継続して実現しているのである。 それに、「堯舜三代」には、君臣であっても自由に相互に批判し、議論し、教え合っていたが、 ヨーロッパには平等に議論のできる議会がある。すべての人間が従わねばならない法律もある。 ヨーロッパ諸国の政治についての知識は小楠に日本の政治への再検討を促した。徳川家の『私』的な政治から私心を去った『公』的な政治に改めねばならない。
「小楠はこのヨーロッパの政治にかんする知識を『海国図志』から得た。佐久間象山や吉田松陰も読んだ書物である。象山と松陰と小楠は共通して『海国図志』の読者となった。そのなかで象山と松陰は『籌海篇』を中心に読み、軍事技術の導入による富国強兵を唱えた。朱子学者として象山は幕藩体制の 君臣関係は絶対的なもので、徳川幕府の継続を期待した一方で、松陰は水戸学の尊王論を徹底化 して討幕を主張した。それにたいして、小楠は朱子学の真の精神を『書経』の「尭舜三代の治」 にもとめ、『海国図志』のとくにヨーロッパの政治形態を学ぶことで公議政体論の唱道者となった」
「1862(文久2)年には徳川慶喜は将軍後見職に、松平慶永は政事総裁職に就いて、幕政に復権する。政事総裁職というのは大老に相当する。翌年、朝廷の側にも徳川慶喜、松平慶永、山内豊信(容堂)、伊達宗城、松平容保、島津久光をメンバーとする参預会議が設けられた。幕府の老中会議に対応するものだが、時代の潮流となっていた公議政体を先取りしたものでもあった」
「 小楠は7月に幕府の最高責任者となった慶永に幕府の国是として「国是七条」を建言した。7条からなる短いものである。 一、将軍が上洛し、歴代将軍の朝廷にたいする無礼をお詫びせよ。 一、参勤交代は廃止せよ。 一、大名の家族は国に帰せ。 一、外様・譜代を問わず有能な人物を選んで幕政の要路につけよ。 一、意見の交流を自由にして、世論に従って公共の政治を行なえ。 一、海軍を強化せよ。 一、自由貿易を廃して、幕府・藩貿易をおこなえ。第1条は幕府が徳川家の私的政治から万民のための公的政治へ転換するための前提である。小楠は天皇の存在を認めるだけでない、尊王の念が厚かった。第4、5条は公の心をもった大名有志と有能な人物を登用して、公議のもとに公論を形成する公共の政治をおこなうという『公議』重視の政治を提唱する。『尭舜三代の治』とアメリカの議会制を融合したものである。・・・天皇の存在はみとめても、天皇を『公』とは見ない。小楠には『公』は儒教の『天』と重なる観念なのであって、孟子が説くように『公』は 万民の側にある。『国是三論』に見られたものである」
「これらの提言は慶喜と慶永のコンビの幕政のもとで、実行に移される。第1条については翌 1863年の3月に将軍家茂が上洛することで実現した。第2、3について、参勤交代は3年に1回に緩和され、大名の妻子は国元に帰ってよいとされた。第6条では海軍の強化策は直接に軍艦奉 行並であった勝海舟に伝えられ、この年に神戸海軍操練所の設置が決定する(翌年開設)。第7条も横浜、箱館が開港され、生糸、茶の輸出が盛んとなる。第4、第5条にかんしては、つぎにのべるように、幕府内外からの支持が高まり、新政府の成立の過程でもさまざまな形の公議政体として実現した」
「幕府の設置した洋学の研究・教育機関である蕃書調所でも欧米の議会制度が議論されていた。 1861年に2度目の蕃書調所頭取となった大久保忠寛は、その1、2年後に、将軍は大政を奉還して、駿河、遠州、三河の3国の大名にもどるべきであるということ、幕政については全国の問題を議論する大公議会と地方の問題を議論する小公議会によって執り行うべきであることを提言した。 洋学者であった彼らは欧米の議会制度を『尭舜三代の治』よりも優れていると考えている。
「・・・12月8日、西郷隆盛の指揮する薩摩・広島・福井などの兵3千が御所の宮門を押さえ、親幕派の公卿を締め出した宮中で天皇は「王政復古の大号令」を発する。そこでも『公議』をつくすことが宣されていた。翌日の夕方には西郷の兵が厳戒する小御所で総裁・議定・参与の三職会議が開かれた。大久保は岩倉を支持したが、後藤象二郎は慶喜を擁護する容堂を支持、激論と なった。討幕派は劣勢、慶喜を擁護するものが多数を占めた。 その議論の模様を聞いた宮中警備中の西郷隆盛は、短刀一本でかたずくこと、と言ったという。 それが岩倉に伝えられ、それを耳にした後藤から容堂にも伝わると、容堂は沈黙する。以後議論 も採決もない。脅迫で決着した。『公議』の場でのクーデターが成功する。・・・武力討幕派の大久保や岩倉が『公議』の場を設けたのは、討幕の正統性を主張するためにほかならない。幕府の廃止を議論の場での決定事項としたかったのである。公議政体論が幕府内外での支配的な政治思想となっていた。 討幕の正統性のもうひとつの根拠が天皇であった。しかし、当時の討幕派の彼らには尊王の意識は薄かった。16歳の天皇にたいして、討幕派の合言葉は『玉を抱く』『玉を奪う』であった。
「1868年1月、新政府の基本方針の原案が横井小楠の門人である由利公正によって作成された。原案は、
一、庶民志を遂げ人心をして倦まざらしむるを欲す。
一、士民心を一にして盛んに経綸を行ふを要す。
一、知識を世界に求め広く皇基を振起すべし。
一、貢士期限を以て賢才に譲るべし。
一、万機公論に決し、私に論ずるなかれ。
である。『庶民』の参加する民主的な議会が想定されていた。『貢士』というの諸藩から選ばれた 議員のことで、任期がもうけらる。『経綸』は小楠の『国是三条』でつかわれた言葉、『公論』は 『公議』と同義語でつかわれる。土佐藩出身の福岡孝弟は第5条を「列侯会議を興し 万機公論に決すべし」と修正し、それを第1条においた。『公議』にかんして由利は豪農・豪商の参加を考えていたが、福岡孝弟の意図していたのは大名の会議であった。第4条の『賢士』も政府が上から選ぶところの『徴士』に変更した。 そして最終的に木戸孝允は「列侯会議」を一般的な「会議」とし、「徴士」を省くなど、普遍的表現に改めて、「五カ条の誓文」がつぎのように決定し、1868年3月14日、御所の紫宸殿で 参集した公郷と諸侯に示す形で公布された。
一、広く会議を興し万機公論に決すべし。
一、上下心を一にして、盛んに経綸を行ふべし。
一、官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦まざらしめんことを要す。
一、旧来の陋習を破り天地の公道に基くべし。
一、知識を世界に求め大い皇基を振起すべし。
「『五カ条の誓文』の2カ月後の1868年閏4月21日には、福岡孝弟と副島種臣によって『五カ条の誓文』を具体化する『政体書』が起草・発布され、中央政府の太政官下には上局と下局からなる二院制の議政官がおかれた。上局は議定と参与からなり、下局は各府県と藩から送られた貢士からなる(幕府直轄領は新政府の支配下におかれ府と県となるが、大名領は藩のまま)。アメリカ合衆国の憲法や福沢諭吉の『西洋事情』を参考にしたとみられてい る。 議定には三条、岩倉らの公家と山内豊信、松平慶永、鍋島直正(前佐賀藩主)、毛利元徳(長州藩世子)、蜂須賀茂韶(阿波藩主)ら、参与には大久保、西郷のほか、小松帯刀、木戸孝允、 福岡孝弟、副島種臣、それに横井小楠、由利公正らが選ばれた。山内豊信、松平慶永、横井小楠、 由利公正ら公議政体論の支持者が参加していることが注目される」
「9月に上局と下局からなる議政官は廃止された。 翌1869(明治2)年2月に太政官は東京に移転し、天皇が東京に移る。3月7日には前年に廃止された下局が『公議所』と改称されて再発足する。その構成員である『公議人』の大多数はすべての藩から選任された藩の代表者からなる。政府の支配下にあった府と県からの代表者はなく、 その代わり、政府からも『公議人』が選ばれ、それに大学校などの諸学校からの『公議人』が加 わった。議長には高鍋藩主の秋月種樹が就いた。存続したのは1年数カ月であったが、切腹禁止、 廃刀、えたの廃止などの議案を審議している。
「全国的な広がりを見せた自由民権運動を明治政府は弾圧する。国民が平等に政治に参加する議会など認めることができない。支配体制を危うくする。事実、自由民権運動は豪農層から一般農民に拡大した。弾圧は苛烈となる。警察力だけでない、国民皆兵となった軍隊までが動員された。 自由民権運動は『学制』で生まれた小学校の教師に浸透した。教育のもつ力を恐れる政府はそれを危険視、そこで制定されたのが『教育勅語』であった。その第一の目的は教師を自由民権運動から切り離すことにあった」
「『教育勅語』では天皇が原理、天皇は絶対的な存在となる。儒教の徳目で飾られるが、儒教の原理の『天』が説かれるのではない。儒教の核心にある学問修業における個人の主体性が求められるのではない。天皇の絶対化という点では水戸学や吉田松陰と共通するが、水戸学も吉田松陰の教育思想の中心には自己の確立があった。『教育勅語』にはそれがない。あるのは天皇への滅私奉公、『一旦緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし』であった」
すみません。コメントを差し挟む余地のないこと、ご容赦いただきますよう。赤松小三郎への言及があれば、と・・・ため息が出ます。