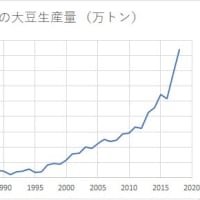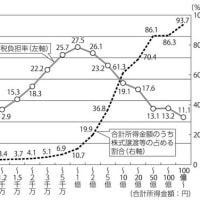堀雅昭著『靖国誕生 ―幕末動乱から生まれた招魂社』(弦書房、2014年)は良書であった。
本書の問題意識は冒頭の次の一節から始まる。
「靖国神社が長州由来なのは意外と知られていない」
長州出身の著者の手によるこの本は、靖国神社という施設が、日本古来の神道とは無縁な長州由来の新興宗教であること、すなわち、巷で言われているように、靖国神社の実態は長州神社に他ならないことを綿密に実証している。
著者自ら冒頭に「暫し政治問題化の喧騒から離れ」と述べているように、著者に靖国を賛美ないし批判するという意図はない。ただ淡々と、長州でなぜ「招魂社(靖国神社の前身)」なる特異な発想の宗教施設が生まれたのかという事実関係を記述していく。本書の主役は、萩の椿八幡宮の宮司から靖国神社の初代宮司となった青山上総介である。
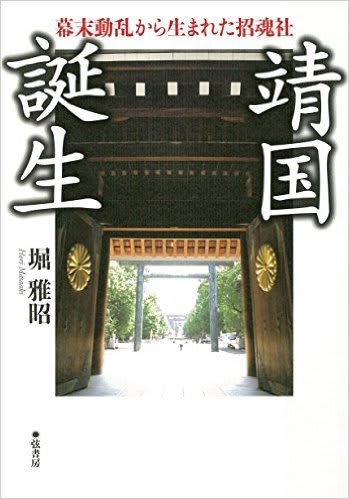
「招魂」の起源
まず、このブログでもたびたび話題になってきた、日本古来の神道にはない、長州起源の「国家」神道の「招魂」という特異な発想はどこからきたのかという問題。
著者によれば起源は、江戸期の国学者・伴信友が『比古婆衣』で記した以下の記述にあるのではないかという。伴信友は「後醍醐天皇、日中行事に、日毎のせうこんの御祭、今は定まれる事なり、とあるせうこんは招魂にて、こは鎮魂にはあらず、陰陽家にて別に招魂祭とて為る方なるべし」と記しているそうである。
著者は、幕末に長州で発生した「招魂祭」は、御醍醐天皇が幕府を調伏するための日中行事として行った陰陽道の「招魂」に由来するのではないかと考える。御醍醐天皇が室町幕府の討幕行事として「招魂」を行ったように、江戸幕府の討幕行事として長州で「招魂祭」が発生したのである、と。
ちなみに以前、このブログでは、朝鮮文化の密接な影響下にある長州で、朝鮮儒教の「招魂(韓国語では「皐復( コボク:고복)」とも)」が伝わったのではないかという説も紹介したことがあった。著者は朝鮮儒教の「招魂」と、靖国の「招魂」の関連性については何も言及していない。むしろ靖国は、キリスト教の影響を受けた、西洋式「神社」であったことを強調する。
南朝主義者の国家改造計画
著者は長州が生んだ「国家」神道は、キリスト教、平田国学、南朝主義などの影響下で成立したと見る。著者は中立的に淡々と記述しているが、彼らの「思想」を読むにつけ、私は随所で悪寒が走るのを禁じ得なかった。
著者が、靖国創建の直接のきっかけとするのが、青山上総介らが文久3(1863)年7月に長州藩政府に提出した「神祇道建白書」であり、その翌年、元治元(1864)年5月25日の楠正成の命日に山口明倫館で斎行された楠公祭であったという。ここで青山らは、吉田松陰、村田清風ら、長州志士17名を「招魂」する。
著者は、楠公祭を「北朝末裔・孝明天皇の否定であり、国家改造の危険な祭事だった。・・・・吉田松陰の遺志を継いだ楠公主義者たちは、北朝体制を根底から否定する国家改造論者になっていった。・・・・国家転覆の神事だったのである」と見る。
この楠公祭に扇動されたのが、長州藩家老の福原越後であり、楠公祭直後の7月に、京都御所を武力で襲撃し孝明天皇を長州に拉致せんとする禁門の変を引き起こすのである。
著者はその可能性について何も述べていないが、もし禁門の変が成功していたら、彼らは何をしたであろうか? この過激な国家改造論者たちは、北朝の末裔を退位させ、南朝の末裔を皇位に就けようとしたであろう。
私は、孝明天皇は暗殺されたと確信をもてるものの、巷で話題の明治天皇すり替え説に関しては、可能性はあるのものの、証拠が十分ではないと見て、これまで何も言及してこなかった。しかし本書を読んで、この過激な南朝主義者たちが権力を握った後、唯々諾々と北朝の末裔に仕えたという事実は何とも解せないという感想を強く持つにいたった。
著者は最後に、靖国の宮司となった青山上総介の晩年に関して、以下のような謎を問いかけて本書を締めくくっている。
「(青山は)どうして一切の思い出を語らぬまま生涯を終えたのか。伊藤博文や山県有朋といった息子ほどの元勲たちの裏も表も知り尽くしながら、・・・・・靖国神社の初代宮司として幽閉されるような生涯を送ったのはなぜか」と。
「明治維新」の闇はまだまだ深い。