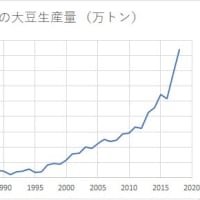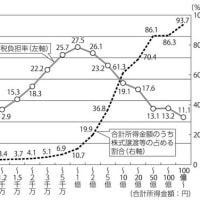以下は、3月18日をもっていったん議論を打ち切られた利根川・江戸川有識者会議に対して私が出した追加意見書です。会議を通して、貯留関数法と総合確率法という、国交省が利根川水系のダム計画の根拠にしている洪水流量の計算方法に、使用には耐えない科学的問題が含まれていることが明らかになりました。この議論が継続されることを強く望みます。国交省におかれましては、ぜひ途中で終わっている会議を再開してください。
昨年9月の第5回から本年3月18日の第11回までの有識者会議での議論を通して明らかになった事実関係の中で、重要と思われる点をまとめたいと思います。
総括的にいえば、今回の会議を通して、「貯留関数法」と「総合確率法」は、河川計画の根拠として使用するには耐えられない欠陥を抱えた手法であることが明らかになりました。とくに貯留関数法を使って算出される大規模洪水の計算流量は、実際の観測値とのあいだのに大きな乖離があることが明確になりました。これは会議の成果であると考えます。
国交省の計算モデル(新モデル)を「妥当」と判断した日本学術会議の「河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会」の論理構成は以下のようなものでした。
①計算値と実測値のあいだには乖離があることを確認した。
②その乖離の理由を科学的に検証することはできなかった。
③しかし計算値は妥当と判断する。
これは科学的推論として成立しません。このような「論理」に科学的正当性はありません。今回の有識者会議での議論の詳細を国民が知れば、大多数の人々は「国交省の計算の仕方に問題があり、それゆえ計算値と実測値のあいだに乖離が生じるのだろう」と結論づけるでしょう。これは利根川に限った話しではありません。貯留関数法を用いて目標流量を定めている全国すべての河川においても同様なのです。
(1)計算値と実測値の乖離が発生する理由の一つは明らかになったこと
今回の会議を通して、国交省の計算モデルは中規模洪水には適合したとしても、大規模洪水の際の流量を予測する際には適用できないことが明らかになりました。
小池俊雄委員は、第11回会議で計算値と実測値のあいだの「乖離を検証することはできていないのは事実」とおっしゃいました。しかし会議の中で、小池委員は、乖離が発生する科学的な理由の一つを明快に説明されておりました。第10回会議で小池委員は「中小洪水で決めたK、Pと、大洪水で決めたK、Pは異なります」と認められたのです。それは中規模の洪水と大規模洪水とでは流出のメカニズムが異なることに起因しており、その説明はじつに明快でした。(注、KとPとは貯留関数法で流域ごとに決まる定数)
乖離の理由の少なくとも一つは、「大規模洪水の際のKとPの値は、中規模洪水から求めたモデルのKとPとは異なるから」という結論になるのは必然です。乖離が発生する理由は他にもあると思われますが、少なくとも乖離の原因の一つはKとPが規模によって異なるからです。
10~20年に1度程度の確率で発生する既存の中小洪水の観測流量をもとに求められたKとPをそのまま用いて、70~80年に1度規模の今回の計画における目標流量や、200年に1度規模の基本高水流量を算出すると、過大な値が算出されます。このことは有識者会議で明確になった事実として確認したいと思います。
(2)総合確率法が科学的根拠薄弱な方法であることが明らかになったこと
日本学術会議の『河川流出モデル・基本高水の検証に関する学術的な評価(回答)』(平成23年9月1日)の18頁では、総合確率法について以下のように説明されています。
「総合確率法では、各洪水ピーク流量に対して、様々な降雨波形に対応してその洪水ピーク流量を生じる降雨総量の超過確率を算定して、その超過確率と降雨波形の生起確率との積を求め、それをすべての降雨波形にわたって加算して、洪水ピーク流量の超過確率を求めている」
小池俊雄委員は第8回会議の場で、「降雨パターンをどういうふうに確率で表現するかということは、実は水文学の中ではものすごく大きな課題で、これは解決しておりません」と明快に述べられました。つまり「降雨波形の生起確率」は不明なのです。
学術会議の回答書にある通り、総合確率法というのは、本来は「降雨波形の生起確率」が求められない限り使えない手法なのです。であるにも関わらず、実際の運用では、降雨波形の生起確率を等確率と仮定して単純平均してしまっています。これは誤った操作です。
降雨波形の生起確率が求められない以上、総合確率法は科学的根拠のない手法であることも明らかになりました。
(3)積み残した論点
その他、積み残した課題には下記のようなものがあります。会議の時間が不十分であったこともあり、残念ながらコンセンサスを得られるまでには至らなかった論点です。これらの論点も、有識者会議の場で議論が継続されることを期待いたします。
• 河川整備計画に財政的な実現可能性の裏付けがないこと。事務局・関東地整の示した事業費見積もりは、明らかに虚偽と思える説明さえありました。関東地整は、河川整備計画の財政規模の見積もり額を当初8,600億円と述べながら、第11回会議の議論の中で、その中にスーパー堤防の費用などが含まれていないことが明らかになりました。スーパー堤防を含めるだけで事業規模はたちどころに見積もり額の2倍以上に増えてしまうことが予想されます。
• 再開前の会議では50 年に1度規模の洪水(当初それは15,000㎥/秒とされていた)が目標流量であったにもかかわらず、その目標流量を上昇させたことへの合理的説明もありませんでした。前述した財政制約や時間的制約、そして環境負荷などの点を考慮すれば、いずれが目標流量として妥当かという議論こそが、「諮問」の役目を担う有識者会議に求められた議論ではなかったのかと考えます。
• 改正河川法の趣旨を踏まえて、環境保全の観点などを含め、幅広く「河川の安全性」を議論することもありませんでした。
• 戦後の森林回復の過程で保水力が向上していることは明瞭であるにも関わらず、森林の保水力向上の効果が計画に考慮されていません。
• 貯留関数法モデルの欠陥として、他にも国交省が「一次流出率0.5、二次流出率1.0」という大雑把な折れ線グラフで流出を近似していることが計算値を過大なものにしている点を指摘しましたが、これも議論を深められませんでした。流出率が0.1、0.3、0.5、0.7…と小刻みに変動する階段型の流出率を設定し、そうしたモデルで計算を行えば、もっと洪水流量の再現性は高くなります。
おわりに
遺憾ながら積み残した論点は多いままですが、「貯留関数法」と「総合確率法」の問題点のいくつかが明確になっただけでも、これまでの会議の成果はあったと思います。
科学的な欠陥を持つ計算モデルを根拠として何千億円の税金を拠出することは納税者の合意を得られません。今後は、全国の河川整備計画を、計算流量ではなく実績流量に基づいて立案することを提案させていただきます。
1947年のカスリーン台風洪水ですら、実際には1万5000㎥/秒しか流れていないことも、今回の有識者会議の議論の中で明らかになった重大な事実でした。既往最大で計画を立案するとしても、1万5000㎥/秒を基準に計画を整備するのが妥当です。その場合、八ッ場ダムは不要になります。
超過洪水対策を別途行う必要があります。超過洪水対策としての堤防の強化策ですが、それはスーパー堤防ではありません。第11回会議で関東地整の方から説明があった通り、スーパー堤防は30年で完成するに足るだけの財政的裏付けがないことが判明しました。超過洪水対策は、財政的に不可能なスーパー堤防ではなく、既存の堤防を強化する「耐越水堤防」の開発と整備によって実行することを要望します。
さらにピーク流量を引き下げる方策については、ダムではなく、流域全体で雨水の浸透と貯留能力を高めるという流域治水の方策で実行するよう要望いたします。それについては3月8日に提出した意見書で述べた通りなので繰り返しません。
最後に、ダム計画が中止になった後の八ッ場の地は、「日本のポンペイ」とも言われる貴重な遺跡群を整備して、吾妻渓谷の自然美とともに野外歴史・自然博物館として整備するよう要望いたします。地域振興と住民の生活再建に最も資する地域資源の裁量の活用法だと考えます。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
追加意見書
有識者会議の議論を通して明らかになったこと
関 良基
昨年9月の第5回から本年3月18日の第11回までの有識者会議での議論を通して明らかになった事実関係の中で、重要と思われる点をまとめたいと思います。
総括的にいえば、今回の会議を通して、「貯留関数法」と「総合確率法」は、河川計画の根拠として使用するには耐えられない欠陥を抱えた手法であることが明らかになりました。とくに貯留関数法を使って算出される大規模洪水の計算流量は、実際の観測値とのあいだのに大きな乖離があることが明確になりました。これは会議の成果であると考えます。
国交省の計算モデル(新モデル)を「妥当」と判断した日本学術会議の「河川流出モデル・基本高水評価検討等分科会」の論理構成は以下のようなものでした。
①計算値と実測値のあいだには乖離があることを確認した。
②その乖離の理由を科学的に検証することはできなかった。
③しかし計算値は妥当と判断する。
これは科学的推論として成立しません。このような「論理」に科学的正当性はありません。今回の有識者会議での議論の詳細を国民が知れば、大多数の人々は「国交省の計算の仕方に問題があり、それゆえ計算値と実測値のあいだに乖離が生じるのだろう」と結論づけるでしょう。これは利根川に限った話しではありません。貯留関数法を用いて目標流量を定めている全国すべての河川においても同様なのです。
(1)計算値と実測値の乖離が発生する理由の一つは明らかになったこと
今回の会議を通して、国交省の計算モデルは中規模洪水には適合したとしても、大規模洪水の際の流量を予測する際には適用できないことが明らかになりました。
小池俊雄委員は、第11回会議で計算値と実測値のあいだの「乖離を検証することはできていないのは事実」とおっしゃいました。しかし会議の中で、小池委員は、乖離が発生する科学的な理由の一つを明快に説明されておりました。第10回会議で小池委員は「中小洪水で決めたK、Pと、大洪水で決めたK、Pは異なります」と認められたのです。それは中規模の洪水と大規模洪水とでは流出のメカニズムが異なることに起因しており、その説明はじつに明快でした。(注、KとPとは貯留関数法で流域ごとに決まる定数)
乖離の理由の少なくとも一つは、「大規模洪水の際のKとPの値は、中規模洪水から求めたモデルのKとPとは異なるから」という結論になるのは必然です。乖離が発生する理由は他にもあると思われますが、少なくとも乖離の原因の一つはKとPが規模によって異なるからです。
10~20年に1度程度の確率で発生する既存の中小洪水の観測流量をもとに求められたKとPをそのまま用いて、70~80年に1度規模の今回の計画における目標流量や、200年に1度規模の基本高水流量を算出すると、過大な値が算出されます。このことは有識者会議で明確になった事実として確認したいと思います。
(2)総合確率法が科学的根拠薄弱な方法であることが明らかになったこと
日本学術会議の『河川流出モデル・基本高水の検証に関する学術的な評価(回答)』(平成23年9月1日)の18頁では、総合確率法について以下のように説明されています。
「総合確率法では、各洪水ピーク流量に対して、様々な降雨波形に対応してその洪水ピーク流量を生じる降雨総量の超過確率を算定して、その超過確率と降雨波形の生起確率との積を求め、それをすべての降雨波形にわたって加算して、洪水ピーク流量の超過確率を求めている」
小池俊雄委員は第8回会議の場で、「降雨パターンをどういうふうに確率で表現するかということは、実は水文学の中ではものすごく大きな課題で、これは解決しておりません」と明快に述べられました。つまり「降雨波形の生起確率」は不明なのです。
学術会議の回答書にある通り、総合確率法というのは、本来は「降雨波形の生起確率」が求められない限り使えない手法なのです。であるにも関わらず、実際の運用では、降雨波形の生起確率を等確率と仮定して単純平均してしまっています。これは誤った操作です。
降雨波形の生起確率が求められない以上、総合確率法は科学的根拠のない手法であることも明らかになりました。
(3)積み残した論点
その他、積み残した課題には下記のようなものがあります。会議の時間が不十分であったこともあり、残念ながらコンセンサスを得られるまでには至らなかった論点です。これらの論点も、有識者会議の場で議論が継続されることを期待いたします。
• 河川整備計画に財政的な実現可能性の裏付けがないこと。事務局・関東地整の示した事業費見積もりは、明らかに虚偽と思える説明さえありました。関東地整は、河川整備計画の財政規模の見積もり額を当初8,600億円と述べながら、第11回会議の議論の中で、その中にスーパー堤防の費用などが含まれていないことが明らかになりました。スーパー堤防を含めるだけで事業規模はたちどころに見積もり額の2倍以上に増えてしまうことが予想されます。
• 再開前の会議では50 年に1度規模の洪水(当初それは15,000㎥/秒とされていた)が目標流量であったにもかかわらず、その目標流量を上昇させたことへの合理的説明もありませんでした。前述した財政制約や時間的制約、そして環境負荷などの点を考慮すれば、いずれが目標流量として妥当かという議論こそが、「諮問」の役目を担う有識者会議に求められた議論ではなかったのかと考えます。
• 改正河川法の趣旨を踏まえて、環境保全の観点などを含め、幅広く「河川の安全性」を議論することもありませんでした。
• 戦後の森林回復の過程で保水力が向上していることは明瞭であるにも関わらず、森林の保水力向上の効果が計画に考慮されていません。
• 貯留関数法モデルの欠陥として、他にも国交省が「一次流出率0.5、二次流出率1.0」という大雑把な折れ線グラフで流出を近似していることが計算値を過大なものにしている点を指摘しましたが、これも議論を深められませんでした。流出率が0.1、0.3、0.5、0.7…と小刻みに変動する階段型の流出率を設定し、そうしたモデルで計算を行えば、もっと洪水流量の再現性は高くなります。
おわりに
遺憾ながら積み残した論点は多いままですが、「貯留関数法」と「総合確率法」の問題点のいくつかが明確になっただけでも、これまでの会議の成果はあったと思います。
科学的な欠陥を持つ計算モデルを根拠として何千億円の税金を拠出することは納税者の合意を得られません。今後は、全国の河川整備計画を、計算流量ではなく実績流量に基づいて立案することを提案させていただきます。
1947年のカスリーン台風洪水ですら、実際には1万5000㎥/秒しか流れていないことも、今回の有識者会議の議論の中で明らかになった重大な事実でした。既往最大で計画を立案するとしても、1万5000㎥/秒を基準に計画を整備するのが妥当です。その場合、八ッ場ダムは不要になります。
超過洪水対策を別途行う必要があります。超過洪水対策としての堤防の強化策ですが、それはスーパー堤防ではありません。第11回会議で関東地整の方から説明があった通り、スーパー堤防は30年で完成するに足るだけの財政的裏付けがないことが判明しました。超過洪水対策は、財政的に不可能なスーパー堤防ではなく、既存の堤防を強化する「耐越水堤防」の開発と整備によって実行することを要望します。
さらにピーク流量を引き下げる方策については、ダムではなく、流域全体で雨水の浸透と貯留能力を高めるという流域治水の方策で実行するよう要望いたします。それについては3月8日に提出した意見書で述べた通りなので繰り返しません。
最後に、ダム計画が中止になった後の八ッ場の地は、「日本のポンペイ」とも言われる貴重な遺跡群を整備して、吾妻渓谷の自然美とともに野外歴史・自然博物館として整備するよう要望いたします。地域振興と住民の生活再建に最も資する地域資源の裁量の活用法だと考えます。
以上、何卒よろしくお願いいたします。