牟田口廉也 「愚将」はいかにして生み出されたのか (星海社新書) 新書 – 2018/7/27 広中 一成 (著)
星3あたりが妥当な評価を与えているかと思われる。
なにしろ、牟田口の評伝というには、あまりに牟田口の情報が少なすぎる。
大部分が世情や軍の状況、戦況の説明に費やされ、はじめてこの手の話に触れるひとにはありがたかろうが、特段珍しいことが書いてあるわけでもないということになる。また、評伝であるからには、そうした事件に接して牟田口がなにをどう思ったか・行動したか、について述べて欲しいところ、そうした属性も薄い。
薄い新書であるにも拘らず、行動原理として「牟田口のプライド」が複数回用いられており(例えばp.248、インパールのクライマックスのところでも;また「彼のプライド」(p.253)の表現も参照)、この点で「牟田口プライド一元論」に傾きがちにすぎる。そうした個人的性向と旧軍の無責任忖度体質が構造的にうまく・へたに絡んでしまって…という理解は、それこそ「何周後れだ」という評価を免れないだろう。
だいたい、現代化するのであれば、河辺と牟田口の熱い無言の対面をボーイズラブを思わせるように描けばいいのであり―『俺の思い、君に届け…!』『なぜだ、なぜ解ってくれないんだ』『ああ! お前がひとこと、たったひとこと、すまん、たすけてくれと言ってくれさえしたら…!』『ダメだ、それだけは言えない…』―それだけで既にアレな組織文化をありありと述べることになる。これは248f.あたりにあり、中国戦線の例とあわせて印象的に描けるところだ。
p.70ころに、牟田口が大隊長を1年しか勤めていないのに在外派遣部隊に「飛ばされ」て、エリートコースから外されてしまった…と簡単にすますが、ここでも大問題があろう。
まずは、牟田口がそうまでの成績上位者でなかったということ(p.43)。いや、真ん中からやや上の25位というのは相当優秀だが。だがそれは、軍中央中枢部でのとんとん拍子の出世を約束するほどのものではなかろう。
しかし近衛の大隊長を拝命したのは、わりと出世が期待できるいいコースかなあ、と思えるのはまあいい。
だが、ここで問題なのは、著者がいう「突然の在外勤務は、左遷に等しかった」(p.70)の判断である。なにしろ通例、将来将軍になるためには、佐官級で二年以上の部隊勤務経験を要するという慣例があったというので、つまり
1) 部隊勤務をさせてもらえるのは、将来の昇進を予定した配置じゃないかな?
2) 前線近くに配置というのは、配置した側にも配置される側にも武勲に対する期待があるのと違うかな?
という疑問から自由でない。とにかく、部隊勤務を さ せ て も ら え る ことへの理解にかけていないか、という論点は持っておいてしかるべきではないか。いや、超優秀すぎるが派閥上の問題で延々部隊勤務に貼り付けられる例もあるにはあり、この場合は左遷といってかまわないだろうが、牟田口はさて、そういえるほど超優秀な成績だっただろうか…という。
ともあれまあ、こんな風に、私程度のゆるい軍オタでも「んう?」と言いたくなる点がぞろぞろあって、どうもうまくない。
例えば最終章に「死に場所を得られなかった「葉隠れ武士」牟田口が最後に懸けたのは、自分は絶対に間違ったことはしていないという強気なプライドであった」(p.258)とあるが、
1) 死に場所というなら、藤原参謀に”勝手に死んでくださいよ”と言われたという、割腹自殺タイミングなんかはアリだよね
2) 所謂「ジンギスカン作戦」の段階で、将兵になれない役牛の扱いを強要するのはともかく、象まで割り振るあたり、既に実現性が乏しく、これでなんで「絶対」を主張できそうか不思議に思ってもいい
あとまあ、外国人からの丁寧な手紙・コメントをもらって感涙するのはいいが、なんか、ありがちなエピソードだよねというのは読書人の大人ならあえて言わずにいる本音をちゃんと持っておいて欲しいよな、とか。
例えば直訳すると「君の見解を尊重する」とか「恐るべきものだ」とかいうコメントが実際あり、まあなんつーか「行間を読んでくれよな!」という場合がわりとあり、相手を怒らせないように丁寧におだてて書く手紙もあるよなあとか思い出してもらえるとよいかもしれない、という。
261頁、非個性的な纏めの文章で「牟田口は一見無謀なようで、実はまじめで忠実な性格の人物であったといえよう」とあるが、いや彼が真面目で(上に)忠実な人物だっただろうことはわりと容易に推測できることで、しかし「無能な働き者」がなにをなしてしまったかなあ、という論点を入れるべきだろうね。
なんか、『別にこれ、未公刊情報を利用したかいがないというか、公刊情報だけ利用という縛りを入れても、僕のほうが興味深くかけそうじゃね?』と思えてしまうあたり、せっかくの牟田口の”名誉回復”の機会、牟田口をめぐって我々が学ぶ機会を浪費してはいないかなあと思えて、これは悲しい読書ではないか、と言いたい。
星3あたりが妥当な評価を与えているかと思われる。
なにしろ、牟田口の評伝というには、あまりに牟田口の情報が少なすぎる。
大部分が世情や軍の状況、戦況の説明に費やされ、はじめてこの手の話に触れるひとにはありがたかろうが、特段珍しいことが書いてあるわけでもないということになる。また、評伝であるからには、そうした事件に接して牟田口がなにをどう思ったか・行動したか、について述べて欲しいところ、そうした属性も薄い。
薄い新書であるにも拘らず、行動原理として「牟田口のプライド」が複数回用いられており(例えばp.248、インパールのクライマックスのところでも;また「彼のプライド」(p.253)の表現も参照)、この点で「牟田口プライド一元論」に傾きがちにすぎる。そうした個人的性向と旧軍の無責任忖度体質が構造的にうまく・へたに絡んでしまって…という理解は、それこそ「何周後れだ」という評価を免れないだろう。
だいたい、現代化するのであれば、河辺と牟田口の熱い無言の対面をボーイズラブを思わせるように描けばいいのであり―『俺の思い、君に届け…!』『なぜだ、なぜ解ってくれないんだ』『ああ! お前がひとこと、たったひとこと、すまん、たすけてくれと言ってくれさえしたら…!』『ダメだ、それだけは言えない…』―それだけで既にアレな組織文化をありありと述べることになる。これは248f.あたりにあり、中国戦線の例とあわせて印象的に描けるところだ。
p.70ころに、牟田口が大隊長を1年しか勤めていないのに在外派遣部隊に「飛ばされ」て、エリートコースから外されてしまった…と簡単にすますが、ここでも大問題があろう。
まずは、牟田口がそうまでの成績上位者でなかったということ(p.43)。いや、真ん中からやや上の25位というのは相当優秀だが。だがそれは、軍中央中枢部でのとんとん拍子の出世を約束するほどのものではなかろう。
しかし近衛の大隊長を拝命したのは、わりと出世が期待できるいいコースかなあ、と思えるのはまあいい。
だが、ここで問題なのは、著者がいう「突然の在外勤務は、左遷に等しかった」(p.70)の判断である。なにしろ通例、将来将軍になるためには、佐官級で二年以上の部隊勤務経験を要するという慣例があったというので、つまり
1) 部隊勤務をさせてもらえるのは、将来の昇進を予定した配置じゃないかな?
2) 前線近くに配置というのは、配置した側にも配置される側にも武勲に対する期待があるのと違うかな?
という疑問から自由でない。とにかく、部隊勤務を さ せ て も ら え る ことへの理解にかけていないか、という論点は持っておいてしかるべきではないか。いや、超優秀すぎるが派閥上の問題で延々部隊勤務に貼り付けられる例もあるにはあり、この場合は左遷といってかまわないだろうが、牟田口はさて、そういえるほど超優秀な成績だっただろうか…という。
ともあれまあ、こんな風に、私程度のゆるい軍オタでも「んう?」と言いたくなる点がぞろぞろあって、どうもうまくない。
例えば最終章に「死に場所を得られなかった「葉隠れ武士」牟田口が最後に懸けたのは、自分は絶対に間違ったことはしていないという強気なプライドであった」(p.258)とあるが、
1) 死に場所というなら、藤原参謀に”勝手に死んでくださいよ”と言われたという、割腹自殺タイミングなんかはアリだよね
2) 所謂「ジンギスカン作戦」の段階で、将兵になれない役牛の扱いを強要するのはともかく、象まで割り振るあたり、既に実現性が乏しく、これでなんで「絶対」を主張できそうか不思議に思ってもいい
あとまあ、外国人からの丁寧な手紙・コメントをもらって感涙するのはいいが、なんか、ありがちなエピソードだよねというのは読書人の大人ならあえて言わずにいる本音をちゃんと持っておいて欲しいよな、とか。
例えば直訳すると「君の見解を尊重する」とか「恐るべきものだ」とかいうコメントが実際あり、まあなんつーか「行間を読んでくれよな!」という場合がわりとあり、相手を怒らせないように丁寧におだてて書く手紙もあるよなあとか思い出してもらえるとよいかもしれない、という。
261頁、非個性的な纏めの文章で「牟田口は一見無謀なようで、実はまじめで忠実な性格の人物であったといえよう」とあるが、いや彼が真面目で(上に)忠実な人物だっただろうことはわりと容易に推測できることで、しかし「無能な働き者」がなにをなしてしまったかなあ、という論点を入れるべきだろうね。
なんか、『別にこれ、未公刊情報を利用したかいがないというか、公刊情報だけ利用という縛りを入れても、僕のほうが興味深くかけそうじゃね?』と思えてしまうあたり、せっかくの牟田口の”名誉回復”の機会、牟田口をめぐって我々が学ぶ機会を浪費してはいないかなあと思えて、これは悲しい読書ではないか、と言いたい。










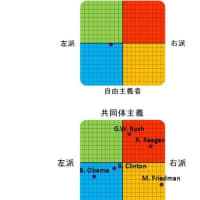

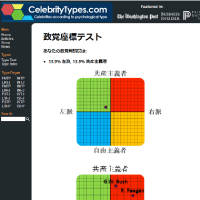






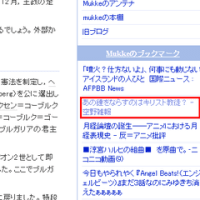





当時の人々の一部には確実にあった傾向であって、特段彼の無能を証明するものではない、とかいいようはあるのでは。
…片倉参謀の霊夢好きは、わたし、ちょっと引いた…。