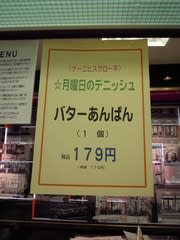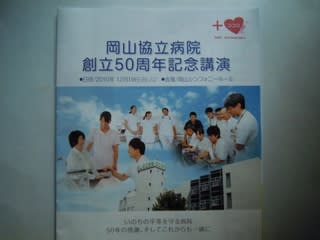以前はどこの庭先でも燃やされていたたき火、ふと「たきび」を口ずさむこの頃
以前はどこの庭先でも燃やされていたたき火、ふと「たきび」を口ずさむこの頃
私が子どもの頃には、どこの家の庭先でも「ドラム缶」がおかれていて、火が燃やされていた。そこで暖まって、それから学校へ行っていたものだ。そこは世間話の場であり、貴重な地域コミュニティの場であった。
ところが、最近は「野焼き」が禁止され、我が柿山の落ち葉や剪定をした枝を燃やすのにも許可がいる時代となり、「たきび」を取り囲む光景が消えている。「井戸端会議」ととも
に、地域の大切なコミュニティが消失していることを残念に思う。
そんなことを考えていた時、先週の土曜日の12月18日の朝日新聞「be」欄には、童謡「たきび」が取り上げられていて、とても懐かしくて一気に読んだ。
そしてその記事を読み、記憶の不確かさをまた知らされる羽目となった。わたしは「たきび」は、「たきびだ、たきびだ、おちばたき。」で歌い始めると思い込んで、口ずさんでいた。しかし、その前に「かきねだ、かきねの まがりかど」の歌詞があることに気がついた。
さてこの童謡「たきび」だが、朝日新聞の記事によると、「昭和41年12月の子ども向けラジオ番組で使いたい」との依頼でつくられたとのこと。そして,12月9日と10日の二日間だけ電波に乗って、以来1949(昭和23)年まで取り上げられず、歌うことが禁じられ封印された歴史があるとのこと。
その理由は、「落ち葉も貴重な資源。フロぐらいはたける。それにたき火は敵機の攻撃目標になる」とのことだ。やはり「たき火」にも歴史はあり、時代とともに変化している。
先の朝日新聞「be」の記事の最後は、「それでも、『たきび』は消えずに残り、歌い継がれてきた」と結ばれている。私もこの童謡「たきび」が、歌い継がれているように、「たき火」を囲む地域コミュニティが復活することを願うものだ。
そんなことを思いながら、「たきびだ、たきびだ、おちばたき」と口ずさんでいる今日この頃だ。