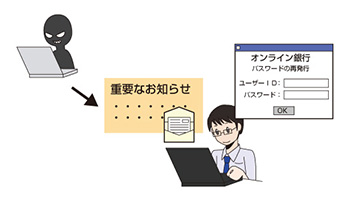前田 健太郎 著
内容紹介
日本では男性に政治権力が集中している。何が女性を政治から締め出してきたのか。そもそも女性が極端に少ない日本の政治は、民主主義と呼べるのか。
客観性や中立性をうたってきた政治学は、実は男性にとって重要な問題を扱う「男性の政治学」に過ぎなかったのではないか。気鋭の政治学者が、男性支配からの脱却を模索する。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
前田/健太郎
1980年、東京都生まれ。2003年、東京大学文学部卒業。2011年、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、博士(法学)。首都大学東京大学院社会科学研究科准教授を経て、東京大学大学院法学政治学研究科准教授。
専攻、行政学・政治学。著書に『市民を雇わない国家―日本が公務員の少ない国へと至った道』(東京大学出版会、第37回サントリー学芸賞(政治・経済部門))(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
私は非体系的にフェミニズムの知識を吸収してきましたが、この本を読んで全て整理されました。自分はまだ男社会の強いところで働いていて、まさに明らかに女性が遭っている「ダブル・バインド」について、マジョリティの男性は「無いもの」として合意形成をしています。
この著作は、規範として取り入れるべき要素が多く含まれており、ジェンダー問題に取り組む全ての方々に闘う武器を与えています。ジェンダーに関する組織改善を図る方々には、効果的で合理的なやり方を示してくれます。
言語化が上手くできなかったフェミニストの方、論破できる自信がないから全面的にフェミニズムを表明してこれなかった潜在的フェミニストの方、フェミニストになりきれないけれどやはり女性差別はあると感じる方、すべての人にオススメします。
まず本の外観で、帯の色が気持ち悪い。黒い国会のような建物におどろおどろしい色使いのキャッチ。赤いカバーとマッチせずに、女性の怨念を男性の視点から表したのかと理解した。女性の書いた本や論文は女性読者が多く、社会では軽視されがちです。男性の手による、男性のための、気づきの本がようやく出ました。新書なので項目が多い分内容が浅いのはやむを得ない。
一般的に、女性は男性より体が小さく、力も弱く、声も小さい。また、生物として一番活動できる期間に、同時に種を残すべく生殖機能も兼ねている。そのために4週間毎に生理があり、時間が連続せずに4週区切りで生きているとも言える。
健康な男性が主体となって築いた社会や文化に、違う時間感覚と身体感覚、感受性を持った女性や多様な人々が寸法の合わない服を着て暮らしている感じである。経済効率の尺度が同じはずはない。合わない服を着ることで、議員や社長になりたいだろうか。
女性の比率が増すだけでは女性としての独自性を活かせない。女性が主体で身の丈に合う社会や文化を築いたなら、全く異なる言語体系や音感で、違う歴史になっていたかもしれないと夢想する。
本書は、社会を良くするには女性の存在が必要である、女性が軽んじられる社会は、弱者も少数派も差別する社会であるとし、そのためにはどうすればよいかを、“ジェンダー視点”から考察した良書である。今、世界の流れは、フィンランドに世界最年少の女性首相が誕生したことに象徴されるように女性の存在感が日増しに高まっているが、日本の現実はというと、世界経済フォーラムが発表した男女格差の報告書の最新版では、日本は153ヵ国のうち、過去最低の121位に低迷している。日本の政治は、先進国の間でも、男性の手に権力が集中している特異な国なのである。
そこで、本書は、なぜ日本には、女性が活躍できる土壌がないのかと、女性も男性も(因みに私は男性です)が漠然として考えていたことを言語化し、極めて平易に事例や表を交えて説明している。ジェンダー問題に取り組んでおられる女性の方にとって、本書は問題解決へのヒントを与えてくれるだろう。
=====================
さて、具体的には次のような点が、ジェンダー問題解決のためのヒントとして印象に残った。
★男性と女性では政策的関心が異なる。男性は、経済政策や安全保障政策など、女性は、社会福祉政策(育児、介護)、児童の教育、女性の職業支援などに関心が深い。→女性の意見を代表する女性議員が求められる。
★男性が参加者の多数を占める集団では、女性は意見を言いにくい。クリティカル・マス理論に従えば、女性議員の数が30%程度になって初めて、女性は本来の力を発揮でき、男性と対等に意見を言えるようになる。フィンランドでは、1906年世界で初めて女性が被選挙権を獲得した。30%という値は、組織において女性が能力を発揮できる下限とされる「クリティカル・マス」として各国の政府機関で用いられているが、1983年、フィンランドが最初にこれを超えた。
★既存の政党が、男性優位の性格を改め、女性を擁立することが必要である。
★日本の女性議員数が先進国よりも低い水準にあるのは、ジェンダー・クオータが導入されてこなかったことにある。これは、女性議員の数を一定数以上に割り当てることである。
★個人モデル/男性稼ぎ主モデルという考え方:北欧のような、個人モデルの福祉国家においては、特定の家族像は前提とされず、夫と妻は対等な存在として、仕事で収入を得るとともに、家事や育児においても協力することが想定される。どちらも自らの資格で社会保険制度に加入し、自らの拠出に基づいて給付を受ける。また、個人モデルの福祉国家はケアを社会化する。即ち、育児や介護を家族で抱え込むのでなく、政府が積極的に社会福祉サービスを共有することで、男女共働きの家族を支える。シングルマザー、ワーキンマザーなどにも福祉を供給する。これに対して日本は、男性稼ぎ主モデルである。
★スウェーデンでは、第二次世界大戦後の経済成長期に労働力不足が生じた際、多くの大陸ヨーロッパ諸国のように移民を受け入れるのではなく、女性の労働参加を促進する道を選択した。その結果、女性の社会進出を支援するために、公営の保育サービスや社会福祉サービスが拡大し、そこで雇用された女性労働者が労働組合に組織化されることを通じて、女性の発言力が強まった。これとは対照的に、日本では高度経済成長期に政府が財政的な事情から公務員数の抑制に乗り出したため、公共部門が女性の社会的進出を後押しするという現象は起きなかった。
★少子高齢化が、男性稼ぎ主モデルの福祉国家の帰結であるだけでなく、それが持続する原因ともなっている。日本は育児支援が充実する前に高齢化が進行し始めたため、政策転換が難しくなっている。これに対して、仕事と育児の両立支援を早い段階で充実させたスウェーデンでは、女性と男性のワークライフバランスを支援する制度が早い段階で整ったことで、少子化の進行が食い止められている。
★社会には、男性は男らしく、女性は女らしくなければならないという、ジェンダー規範と呼ぶ目
に見えないルールが存在する。このジェンダー規範は、決して人間の生物学的な本性を踏まえたも
のではなく、それは何らかの形で社会的につくられたものである。ジェンダー規範は、男性と女性
に異なる社会的な役割を与える(性別役割分業)。男性は、仕事に就き、家族を養わなければならな
い。女性は、家庭において、家事や育児をおこなわなければならない。この規範は、「男は仕事、女
は家庭」といった言い回しに表されてきた(例:良妻賢母)。
★女性はジェンダー規範に従って行動する限り、「ダブル・バインド」に直面する。一方には、積
極性があり、競争的な、「男らしい」行動を求める組織規範があり、他方には優しく、包容力のある、
「女らしい」行動を求めるジェンダー規範がある。
★政治が「社会に対する諸価値の権威的配分」を行う行動だとすれば、男性と女性の地位の不平等
も、大きな争いの種となるはずであるが、重要な政治争点として認識されてこなかった。なぜか?
女性が声を上げてもその力が弱く認識されなかったからである。例えば、非正規雇用を巡る問題は、
それが女性の問題である間は争点化されなかったが、2000年代に若手男性の非正規化が進んで初
めて争点化した。。
★男女の不平等が長く政治の争点となってこなかったことの原因の一つは、マスメディアがアジェ
ンダ設定を行ってこなかったからである。本やSNSがジェンダー争点化を後押ししてきたことは
間違いない。#MeTo 運動はその一つ。この影響は日本では今のところ限られている。
=================
最後に、本書に関連して、今後女性の活躍が一層望まれるが、八木芳昭著『尊ぶべきは、小さな社
会と細やかな心~Small is Beautiful~』(book Trip社)には、多くの分野で女性が活躍している事
例を掲載されていて大変に参考になった。https://amzn.to/2PtlpUZ 一読をお勧めしたい。
民主主義に女性が少ないのはなぜか??
とてもわかりやすかったです。
政治というジャンルの本を読んだのは、恥ずかしながら初めてですが、わかりやすく読めました。
「日本の社会保障は、男性を通じて享受する構造になっている。」というのが、自分が感じていたモヤモヤを言語化されていてスッキリしました。
私も男性社会で働くなかで、ジェンダー規範に苦しめられ、子供を産んでさらに、娘にはそのような辛い思いをさせたくないけれど、「一体どこに問題があるのだろう?」と漠然と考えていました。
「女性」というタイトルに食わず嫌いせず、広い層の人に読んで欲しいです。
ただ、特に、フェミニストと呼ばれる方達にこそ読んで欲しい。
「kutoo」とか「女性だからといってなぜ化粧しなきゃいけないのか?」とか献血ポスターとか、目の前の問題をひとつひとつ片付けることも大切ですが、そういう人たちこそ、日本の政治、構造そのものに目を向けて、声をあげていって欲しいなと思います。
最初に目次と全体をぱらぱらと見て、啓蒙的な感じのするタイトルに反して固そうな本だなと思った。個人的にはなぜ日本には女性政治家が極端に少ないかその理由に切り込んでいくことを期待して読んでみたのだが、あまり筆者のそういう分析は開陳されておらず(特に文化面での分析は皆無。日本には根強い男尊女卑が根底にあり、社会保障もそれに則っているということ自体は、誰だって分かっているのでそれを聞かされてもしょうがない)、各国の女性国会議員数の推移やら、この問題に関する既存の研究書や政治学的専門用語の紹介が中心。地道な学者的データ整理を成した本というべきだろうか。それはそれで価値があるのかもしれないが。
○読了までの時間:120-180分
この本は、「なぜ日本には女性の政治家が少ないのか」というリサーチ・クエスチョンを土台に、政治や民主主義、政治史に至るまで、平易な文章で書かれた良書である。また、適切なポイントで政治学の主流派の理論を紹介しているため、政治学に関わりの薄い人であっても読み進められるように、配慮がなされている。
とはいえ、本書のねらいは、そうした従来の主流派理論が、ジェンダーあるいは女性の視点を全く欠いていることを、さまざまなデータや文献を用いて実証することを目的としている。筆者としては、もはや故意に女性を排除してきたのではないかと思えるほど、これまでの政治が「男性の政治」としてつくられている点に納得した。
結論としては、女性の候補者が少ないことが、日本に女性政治家が少ない大きな原因である。これは一見当然の帰結のように見える。だが、根本的な問題は、女性政治家の立候補を阻んでいる何かが存在することである。それは、われわれの社会の底流にある「女性蔑視」、あるいは「男性優位」である。こうした概念は、教育・就職活動・仕事・日常生活など、いたるところで、「無意識に」行われている。したがって、それを指摘したところで、「そんなことはない」と一蹴されてしまう。だからこそ、何百年もの間、女性は男性の影に隠されてきた。そして、何もしなければ、これからもそれは続いていくに違いない。
国立国会図書館による「近代日本人の肖像」というWebページの掲載人物を見ると、女性はほんの数名しかいない。われわれが政治家と聞いてイメージするのは、スーツを着た男性(しかも老人ばかり)ではないか。これで、本当に女性の意思が社会に反映されてきたと言えるだろうか。野球をやったことのない人が野球を語るには限界があるように、女性ではない人が、女性について知りうることにも限界がある。
本書が、「男性優位」「女性蔑視」というメタナラティブを突き崩すための、最初の一槌になることを、筆者は確信している。