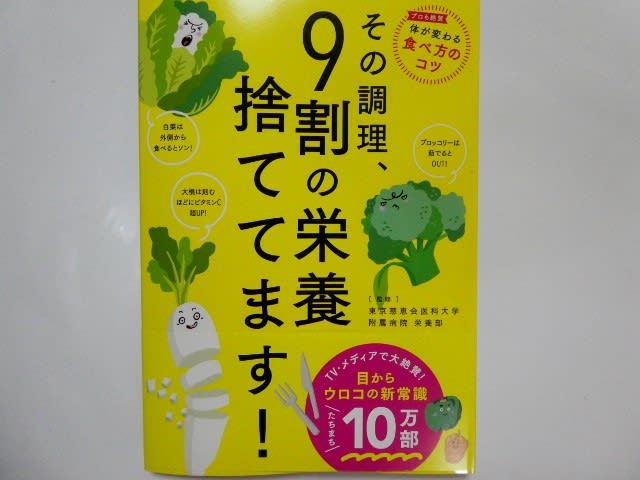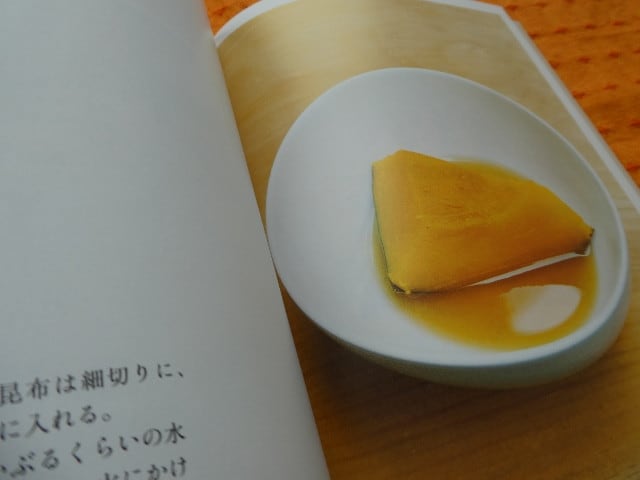夫が釣りに出掛けたので、まとまった時間が取れました。
そんなわけで、やっと読書。(^-^)
この2冊を読みました。

右の「医者が教える食事術 最強の教科書」は、
文字も大きいし、大切な個所はカラーで線が引かれているので
読みやすいはずなんだけど・・・。
ひとつの項目を読むたびに、本を置いて休憩したくなる。
読み進めることが難しい本でした・・・。(?_?)
まるでテレビの健康情報番組を見ているみたいで、
「で、何をどう食べると何に効くんだっけ?」
と、情報ばかり多くて何も残らないと言う・・・。
もう一冊の「世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事」は、
先の一冊に比べると、文字は小さいのだけれど、
目が疲れても、どんどん先を読みたくなる!!
一言一言が、するすると頭に入ってくる。
エビデンスに基づいた内容だから、よどみがない。
野菜ソムリエの勉強をしている時、「青果物と健康」という授業がありましたが、
そう、まさにその授業を受けた時のような満足感があります。
数多くの信頼できる研究によって、
本当に健康に良いと現在考えられている食品は、次の5つだそうですよ。
1魚
2野菜と果物(フルーツジュース、じゃがいも含まない)
3茶色い炭水化物
4オリーブオイル
5ナッツ
大切なのは、食品に含まれる「成分」ではなく、食品や食生活全般。
ものすごく納得した一冊でした。