2007年07月06日17時30分(アサヒコム)
昨年1年間に一審が終了した民事訴訟の平均審理期間は7.8カ月で、10年前と比べて2.4カ月短くなったことが最高裁のまとめで分かった。約14カ月だった30年ほど前からみると、ほぼ半分に近づいている。扱う内容や難しさの度合いに応じて長引く訴訟もあるものの、総じて短縮化の歩みが続いている。
裁判の「迅速化」は一連の司法制度改革の大きな柱のひとつ。03年施行の裁判迅速化法では、すべての訴訟の一審を2年以内で終わらせることが目標とされている。
最高裁が06年に判決や和解などの形で終了した14万3321件を集計したところ、平均審理期間は7.8カ月。96年は10.2カ月だった。
内訳をみると、「6カ月以内」だった訴訟が63.94%を占め、96年の58.63%に比べて増加。一方、「2年以上」は5.53%で96年の10.56%より大幅に減少した。
ここ10年間の改善を後押ししたのは、98年施行の改正民事訴訟法だ。訴状段階で紛争の実情が分かる書類を当事者に早く出させるようにしたほか、裁判所が証人の数や聴く内容を絞る「集中証拠調べ」を原則化したり、当事者の手持ちの証拠を入手するために「文書提出命令」を出せるケースを増やしたりした。
全体に当事者が多くいる訴訟や医療や建築など専門性の高い分野の訴訟は審理が長くなる傾向がある。裁判所も態勢を見直し、医療や建築の訴訟を専門に扱う集中部を創設するなどして短縮化を図っている。
最高裁民事局は「弁護士の態勢や双方の主張を十分聞くことを考えると迅速化は限界がある。ただ、裁判員制度が導入されて刑事裁判が劇的に短くなると、民事訴訟はまだ長すぎると言われるかも知れない」と話す。
迅速化法では終了した訴訟を分析して2年ごとに報告書を出すことを求めている。最高裁は、法曹三者や学者がメンバーとなった検討会で迅速化に向けた検証を進めており、05年に続いて2回目となる報告書を近く公表する予定だ。
昨年1年間に一審が終了した民事訴訟の平均審理期間は7.8カ月で、10年前と比べて2.4カ月短くなったことが最高裁のまとめで分かった。約14カ月だった30年ほど前からみると、ほぼ半分に近づいている。扱う内容や難しさの度合いに応じて長引く訴訟もあるものの、総じて短縮化の歩みが続いている。
裁判の「迅速化」は一連の司法制度改革の大きな柱のひとつ。03年施行の裁判迅速化法では、すべての訴訟の一審を2年以内で終わらせることが目標とされている。
最高裁が06年に判決や和解などの形で終了した14万3321件を集計したところ、平均審理期間は7.8カ月。96年は10.2カ月だった。
内訳をみると、「6カ月以内」だった訴訟が63.94%を占め、96年の58.63%に比べて増加。一方、「2年以上」は5.53%で96年の10.56%より大幅に減少した。
ここ10年間の改善を後押ししたのは、98年施行の改正民事訴訟法だ。訴状段階で紛争の実情が分かる書類を当事者に早く出させるようにしたほか、裁判所が証人の数や聴く内容を絞る「集中証拠調べ」を原則化したり、当事者の手持ちの証拠を入手するために「文書提出命令」を出せるケースを増やしたりした。
全体に当事者が多くいる訴訟や医療や建築など専門性の高い分野の訴訟は審理が長くなる傾向がある。裁判所も態勢を見直し、医療や建築の訴訟を専門に扱う集中部を創設するなどして短縮化を図っている。
最高裁民事局は「弁護士の態勢や双方の主張を十分聞くことを考えると迅速化は限界がある。ただ、裁判員制度が導入されて刑事裁判が劇的に短くなると、民事訴訟はまだ長すぎると言われるかも知れない」と話す。
迅速化法では終了した訴訟を分析して2年ごとに報告書を出すことを求めている。最高裁は、法曹三者や学者がメンバーとなった検討会で迅速化に向けた検証を進めており、05年に続いて2回目となる報告書を近く公表する予定だ。



















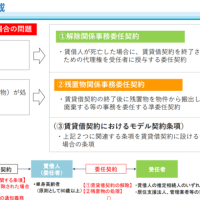






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます