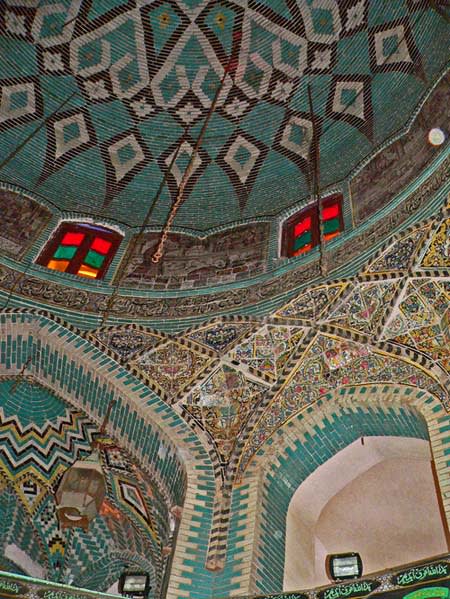9月朔日
新しい月に移り、心新たに散歩にいかんと、二時間以上をただひたすら歩く。
これまでに数度ほど訪れた事があるであろう廣瀬大社へと向かう。
廣瀬大社の歴史は古く、『日本書紀』にも記述がある。
『日本書紀』によれば、次のような内容
日本書紀天武天皇四年四月十日(675年)に、小錦中間人連大蓋を遣わし、大山中曽根連韓犬を斎主として大忌神を廣瀬の河曲に祀られたことが記されていて、これが毎年四月四日と七月四日に行われた大忌祭の始まりと伝えられる。
廣瀬大社につくと「月次祭」と記された紙とお神酒が備えられていた。

月次祭(つきなみのまつり) Wikipedia▼
月次祭(つきなみのまつり)とは、神道における祭礼のひとつ。伊勢神宮では6月・12月の月次祭と神嘗祭の3つの祭礼を三節祭(さんせつさい)、三時祭(さんじさい)と称される。
歴史
古くは毎月行われたようであるが、『延喜式』において6月と12月の11日に行うことが規定され、朝廷と伊勢神宮で行われた。
朝廷では、神祇官が11日の朝に、畿内304座の神の祝部(はふりべ)に幣帛を分け与えた(班幣)
また、夜には中和院(ちゅうかいん)の神嘉殿で、前年に収穫した穀物(旧穀)を天皇が神と一緒に食する「神今食」(じんこんじき)が行われた。
その後、班幣は伊勢神宮のみとなり、室町時代に入ると応仁の乱などにより班幣は廃されるようになったが、明治以降に復活した。
なお現在では、全国の多くの神社でも毎月一定の日を決めて月次祭が行われている。
神今食 【じんこんじき】とは 世界大百科事典 第2版▼
〈じんごじき〉〈かむいまけ〉ともいう。
上代より中世まで,毎年6月11日,12月11日の月次(つきなみ)祭班幣の夜,
宮中神嘉殿において,天皇がみずから皇祖天照大神に神饌を供し,みずからも食する祭り。
祭儀は新嘗祭(にいなめさい)と同様だが,神饌の数量は新嘗祭より少なく,後儀の豊明節会(とよのあかりのせちえ)はなかった。この祭りは祈年祭,新嘗祭,相嘗祭などとともに,稲作文化の祭りといえる。新嘗祭,相嘗祭は新穀による神饌を供するのに対して,神今食は新穀ではなく旧穀を用い,また1年12ヵ月を2期に分けて行われたことは月次祭と同様の意がうかがわれる。
月次祭 三省堂 大辞林 ▼
つき なみの まつり 【月次▽祭】
陰暦6月と12月の11日に神祇官で行われた祭り。
国家安泰と天皇の福運を祈る。本来は月ごとに行われるべき祭りであった。
伊勢神宮その他の諸社でも行われたが一時衰微し,明治初期に復活した。
2016年9月1日


























 )
)