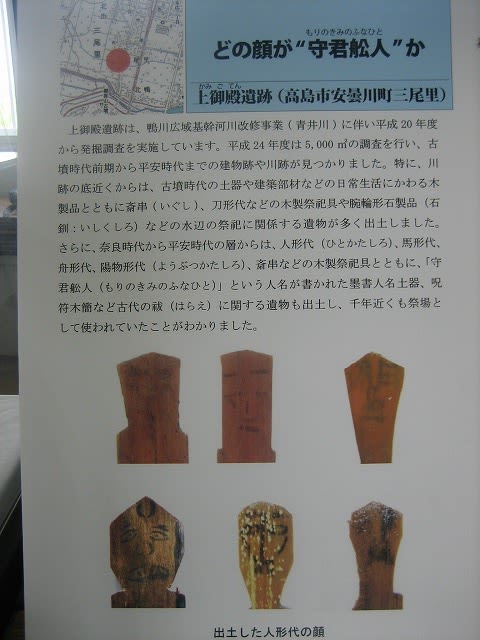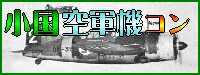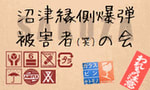小学生低学年から はじめたプラモデルの製作 文房具屋さんの
ショウケースに置いてある 三和のピーナッツシリーズが
最初だった 胴体と主翼、一枚の水平尾翼を差し込んで
足を付けると 出来上がりです。色はまだ 塗る事を知らなかった。
それから半世紀の あいだに模型飛行機にかかわることを
色々してきました。
それらをまとめて まだまだ稚拙な作品ですが、作品展を
開かせてもらいます。 飛行機が主ですが、1/700 の艦艇や
箱絵 雑誌 資料 写真 なども 一緒に置かせてもらいます。
日時 2013年10月26日 (土)AM.11:00~PM.6:00
27日 (日)AM.10:00~PM.4:00
場所 堺市立美原文化会館 5階研修室 072-363-6868

ご都合がつきましたら、どんなんかなと 思って来場いただけると 嬉しい限りです。
PS これらの準備の為に プラモの製作はしばらく進まない状況に
なりそうですので、ブログ更新も間があきそうです。
猛暑の中 皆さん こまめな水分補給をして 体調維持に努めてくださいませ。
ショウケースに置いてある 三和のピーナッツシリーズが
最初だった 胴体と主翼、一枚の水平尾翼を差し込んで
足を付けると 出来上がりです。色はまだ 塗る事を知らなかった。
それから半世紀の あいだに模型飛行機にかかわることを
色々してきました。
それらをまとめて まだまだ稚拙な作品ですが、作品展を
開かせてもらいます。 飛行機が主ですが、1/700 の艦艇や
箱絵 雑誌 資料 写真 なども 一緒に置かせてもらいます。
日時 2013年10月26日 (土)AM.11:00~PM.6:00
27日 (日)AM.10:00~PM.4:00
場所 堺市立美原文化会館 5階研修室 072-363-6868

ご都合がつきましたら、どんなんかなと 思って来場いただけると 嬉しい限りです。
PS これらの準備の為に プラモの製作はしばらく進まない状況に
なりそうですので、ブログ更新も間があきそうです。
猛暑の中 皆さん こまめな水分補給をして 体調維持に努めてくださいませ。