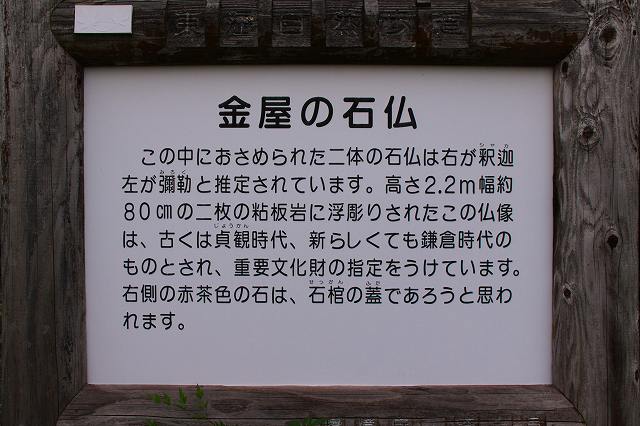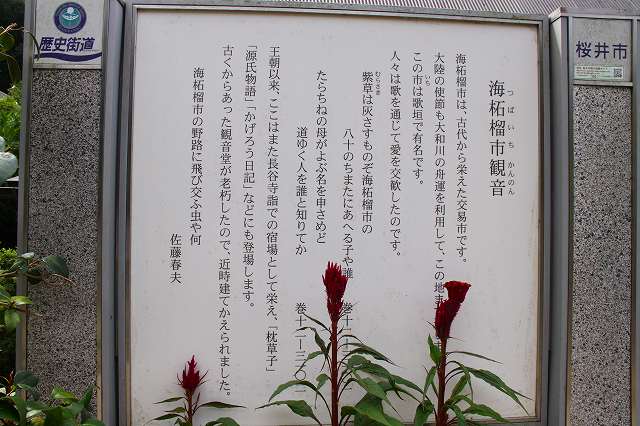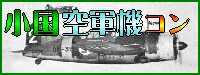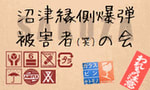筆塗り講座に持っていったもう片方の
フロッグ 72 ドボアチンD520 はフランス迷彩で仕上げます
塗装図はプロファイルの表紙にしました しかし筆書きには
あまりにもハードルが高すぎました。






ラウンデルも真円にならずに枠がかっちりときまってません この辺りが
今後の課題になります 垂直尾翼のDewoitine D520 N277
を書き込むのが出来ませんでした
それと部隊マークの顔マークがあまりのも似ていません

次はチョッとハードルを下げないといけません 少しずつきっちりと
仕上げるようにしていきます
フロッグ 72 ドボアチンD520 はフランス迷彩で仕上げます
塗装図はプロファイルの表紙にしました しかし筆書きには
あまりにもハードルが高すぎました。






ラウンデルも真円にならずに枠がかっちりときまってません この辺りが
今後の課題になります 垂直尾翼のDewoitine D520 N277
を書き込むのが出来ませんでした
それと部隊マークの顔マークがあまりのも似ていません

次はチョッとハードルを下げないといけません 少しずつきっちりと
仕上げるようにしていきます