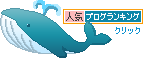ここまで記したので、
こんなポンチキ記事に最後までお付き合いして頂いた
貴重なる皆様への御礼として、
おそらくネットだろうが、本だろうが、なんだろうが、
きっとどこにも記されていないであろう
「神魂神社の穴」についての話を、もう一回、
次回の「5」で記しておこうかと思います......
この穴、なんかヤベェェーーー!?( ̄д ̄;)ッス。

この穴。
「ビンカン」な人であれば誰しもが気になり、惹かれ、
時におののき、時に畏怖し。
どこかしら暗く、強く、得体の知れない何かが潜んでいる!?
様にも感じられちゃうようで。
それで、
「この穴ってなんなのですか!?」
と神社の方々に聞いてみるも、
答えは決まって
「意味はありません」
「ただの穴です」
「わかりません」
と帰ってくるのだそうです。
宮司さんや禰宜(ねぎ)さん、社務所の巫女さん......
どなたに聞いても、だそうです。
となると、きっと、
「そう答えるように......」
という約束事にもなっているのだと思います。
ただ、そんな答えが逆に、尚更、
多くの人の好奇心を刺激してしまうようでもあって。
この神社を訪れた方々の間では
常にお決まりの話題ともなっているようなのです。
「謎の穴」
「でもなんかズゲー!」
「意味ありげ!」
「なんなんだろ!?」
と。

この穴は境内の山肌に掘られている?のですが......
この感じ......
なんか、知ってる......
なんだったろ......コレ.......多分、知ってる......
なんだったかな......
ジーーーーット.......見つめるに......感じるに......
アチキには、一つ、
ピン!と浮かんでくるモノがあります。
それが関東、千葉県、
房総半島の突端にある安房国一宮(あわこくいちのみや)
「安房神社=あわじんじゃ」
その境内や神体山のあちこちにある穴。
ソコでなんらかの祭祀に使われていたであろう色んな穴。
その在りようや神社との混じり方、
アナの雰囲気や空気感がそっくりなのです。

御神木の後ろのほーに......いくつかの穴......



境内のど真ん中、厳島社も.....穴......

この道の先の穴は.....
とてもカメラを向けれるシロモノではなかったです......

そして、さらにもう一つ。
そんな神魂神社(かもすじんじゃ)と安房神社の穴のイメージと
重なってくるモノが他にもアルことに気付かされます。
それは、沖縄を始めとする列島南方の島々特有の聖地の在りよう。
イワユル「御嶽=うたき」なるもの。
有名どころでは世界遺産でもある
「斎場御嶽(セイファウタキ)」などもそうです。
巨大な岩壁や山のえぐれた部分や穴、
その前に祭壇が設けれれているような姿。
その空気。

例によって古い携帯写真ですが......


沖縄本島の中央、
浜比嘉島の「シルミチュー」などは深い洞窟になっていて。
もう、とてもじゃないですけど、
シロートのワタクシメには入る気すらも起きません。
沖縄や宮古島には他にも沢山そんな聖地が点在していますが、
「カモスの穴」といつのは、
そんな聖地の穴や構造にも似ている気がします。

ここまで記すと、
もうお分かりの方もいるかとは思いますが......
これら全てに共通するもの。
それは......
「忌部氏(いんべし、いむべし)」
天太玉命(アメノフトダマ ノ ミコト)を祖神とする
古代朝廷の祭祀を司っていた一族。
神魂神社(かもすじんじゃ)は、
ある時期以降、一時期......おそらくは今も、
この忌部氏との関わりが深い神社の様に思います。
境内の「穴」からは、僕はそれを感じるのです。
忌部氏(いんべし)とは、
記紀が編纂(へんさん)されていた頃の古代大和朝廷において、
祭祀関連の権限を中臣氏(なかとみし)と二分する力を持っていた一族。
古代天皇の側近中の側近。
「斎部」とも書きます。
祭祀関連とは、今で言えば総務省、外務省、財務省、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、宮内庁......
などの省庁をひっくるめたようなもので、
そこに占術までついてくる。
その長ともなれば、まさに内閣官房長官的なもの。
物部氏などの軍産複合派閥、省庁で言えば防衛省、警察庁、国土交通省......
などの体育会系!?グループと双璧をなす文化系最重要ポスト。
その権力の座を巡り中臣氏と長い間争い続け、
徐々にズルズルと後塵を拝していき。
その後「藤原氏」となって栄華を極めていった中臣氏の裏や
影のような存在となっていった氏族です。
歴史の表舞台に多数登場する豪華絢爛たる藤原氏の面々とは
対極の地位に甘んじていたため、
その功績は教科書などにもナカナカ書かれませんが、
とても偉大な氏族さんなのです。
ソモソモ、
列島に稲作が広まる前からこの国にあった重要な穀物
「ひえ=稗」「アワ=粟」
その栽培方法なども忌部氏が伝えた、教えた、とされています。
更に、その他多くの作物の栽培法から、
着物の原料であった麻や綿、絹の作り方、
服の織り方や作り方に至るまで。
民の暮らしに深く関わるあらゆる産業をリードしていた氏族だとも思われます。
なので、忌部氏の祖先は多くの人々から敬われた農業や産業、
商売の神様ともなって行きました。
全国各地で開かれる「酉の市=とりのいち」などは、
元を辿れば、実は、
「天日鷲神(あめのひわしのかみ)」
という忌部氏の祖先神の一柱に辿り着き。
さらには、
伊勢神宮のある地を古くから護ってきた「度会氏(わたらいし)」や、
あの「織田信長」さん迄も、
この忌部氏の血統が後ろにチラつくのです。
記紀(きき)の神話においても、
かの有名な「天岩戸(あまのいわと)」において、
岩戸に隠れてしまった太陽神、
天照大神(アマテラスオオミカミ)を外の世界に引っ張り出す時には、
中臣氏の祖先である天児屋命(あめのこやねのみこと)と、
太玉命の二人で鏡を差し出した......と記されています。
神話では、
双方の祖先神の活躍がとても重要な立ち位置で記されています。
このあたりにも国家の祭司職を巡る2氏族のライバル関係の匂いが漂い、
もっと深く読み込めば、
記紀神話(古事記&日本書紀)というのは、
この2氏族が話し合いながら書き上げていったのではないか?
というような感じすらもしてきます。
そして、
そんな見識を持った上で「記紀」の内容を改めて見てみるに、
先行する「古事記」を記していた頃は、
中臣、忌部の両氏族はまだ諸事をしっかりと二分し、
コミュニケーションも密に計りながら編纂をしていた様に感じます。
が、後発の「日本書紀」の頃には、
そのバランスは大きく中臣氏に偏って編集されたように思えます。
「古語拾遺(こごしゅうい)」
という古書があるのですが、それは、
そんな「日本書紀」に対抗するために、
斎部広成(いんべひろなり)が独自に記したものです。
しかしながら、
強大であった忌部氏の足跡は今も日本各地に
神社や地名などでシッカリと残っていて。
そんな氏族の大きな拠点としては
「出雲(島根県)」
「紀伊(和歌山県)」
「阿波(あわ、徳島県)」
「讃岐(香川県)」
「安房(あわ、千葉、房総)」
あたりとなるのでしょうか。
それらの本拠として奈良県、橿原市の地にも
忌部という名前が残っています。
この中で、
出雲と奈良に関しては天皇や朝廷の命に従ったり、
付き添う形での移住だとも考えられるので、
その他の地域をよくよく見てみると、
忌部氏が列島にやってきた経路が浮かび上がっても来ます。
それは明らかに、太平洋側、
黒潮の海流に乗って移動して来たであろうことが手に取るように浮き出て来るのです。
ちなみに、中臣氏は......
長崎県、対馬との繋がりが深い様にも思います。
......戻りますが......
そんなワケで、
沖縄を中心とする列島南方の島々に見られる祭祀の形が、
忌部氏に縁が深い神社には「所々」見て取れるというわけで。
忌部氏が「ひえ」や「アワ」などの穀物の知識も詳しく持っていて、
海洋航海技術などもとても優れていた......
ということにも納得がいくのです。
忌部氏の移り住んだ場所の地名に
「アワ」とう名前がつけられている要因も、
穀物の神というコトでよく分かりますし、
神話の中にも
「アワシマ=淡島」は神々が最初に造った島、
と書かれていたりもします。
古事記の編纂者として今に伝わる「稗田阿礼 (ひだのあれ)」の苗字部分が
「稗(ひえ)の田」となっているところにも、
この人物が忌部氏の関連であろうと、僕には想像出来るのです。
神話において忌部氏の祖先神が英雄的に書かれていることも
ここで理解できるのです。
この国の文化や文明の「基礎」の部分には、
遠く南方洋から伝わってきたモノモノも
色濃く組み合わされていたりすると思うのですが、
それらは忌部氏の影響がとても大きい様に思えます。
沖縄の創造神、太陽の女神がアマテラスと似た名の
「アマミキヨ」だったりするのも、なんとなく、
神話作家陣の一部でもあった忌部氏との関係性を
思い計ったりもしてしまいます。
記録では、
忌部子人(いんべおびと、いんべこびと)という人は、
朝廷から「出雲守」として、
征服した出雲の民が反乱を起こさぬように、
出雲で謀反の動きがアレば早めにチェックするように、と、
「朝廷のお目付け役」として出雲に派遣された、と記されています。
その時に住んだ場所が、今の松江市「忌部町」であり。
移住後すぐに、その地域の最重要地であった神魂神社を押さえ。
ソコに自らの祭祀の流儀を被せながら管理もしていった。
そんな痕跡が神魂神社の穴......なのか......
全て、数奇なるおとぎ話、個人的想像譚......ですが、
静謐(せいひつ)なる神魂神社(かもすじんじゃ)の穴の前に立つと、
その穴の奥からは、僕にはこんな物語が流れ出してくるのです。
きっと、忌部氏もまた、
古代日本の「8を巡る旅」における「呪」の旅人なのではないのか?
と、思っていたりもします。
しかし、
今回のこの記事......
書くのがメタクタ大変で......
色々と......飛んで来て!?
タイヘンす。(@_@)
こんなメンドくさくて胡散臭い、
難解な記事を最後まで読んで頂き、本当に感謝です。
ありがとうございます。
「8を巡る旅」のシリーズ記事は以下のテキストリンクで。
おやすみなさい。(^^)
「8を巡る旅」「2」「3」「4」
「6」以降。
こんなポンチキ記事に最後までお付き合いして頂いた
貴重なる皆様への御礼として、
おそらくネットだろうが、本だろうが、なんだろうが、
きっとどこにも記されていないであろう
「神魂神社の穴」についての話を、もう一回、
次回の「5」で記しておこうかと思います......
この穴、なんかヤベェェーーー!?( ̄д ̄;)ッス。

この穴。
「ビンカン」な人であれば誰しもが気になり、惹かれ、
時におののき、時に畏怖し。
どこかしら暗く、強く、得体の知れない何かが潜んでいる!?
様にも感じられちゃうようで。
それで、
「この穴ってなんなのですか!?」
と神社の方々に聞いてみるも、
答えは決まって
「意味はありません」
「ただの穴です」
「わかりません」
と帰ってくるのだそうです。
宮司さんや禰宜(ねぎ)さん、社務所の巫女さん......
どなたに聞いても、だそうです。
となると、きっと、
「そう答えるように......」
という約束事にもなっているのだと思います。
ただ、そんな答えが逆に、尚更、
多くの人の好奇心を刺激してしまうようでもあって。
この神社を訪れた方々の間では
常にお決まりの話題ともなっているようなのです。
「謎の穴」
「でもなんかズゲー!」
「意味ありげ!」
「なんなんだろ!?」
と。

この穴は境内の山肌に掘られている?のですが......
この感じ......
なんか、知ってる......
なんだったろ......コレ.......多分、知ってる......
なんだったかな......
ジーーーーット.......見つめるに......感じるに......
アチキには、一つ、
ピン!と浮かんでくるモノがあります。
それが関東、千葉県、
房総半島の突端にある安房国一宮(あわこくいちのみや)
「安房神社=あわじんじゃ」
その境内や神体山のあちこちにある穴。
ソコでなんらかの祭祀に使われていたであろう色んな穴。
その在りようや神社との混じり方、
アナの雰囲気や空気感がそっくりなのです。

御神木の後ろのほーに......いくつかの穴......



境内のど真ん中、厳島社も.....穴......

この道の先の穴は.....
とてもカメラを向けれるシロモノではなかったです......

そして、さらにもう一つ。
そんな神魂神社(かもすじんじゃ)と安房神社の穴のイメージと
重なってくるモノが他にもアルことに気付かされます。
それは、沖縄を始めとする列島南方の島々特有の聖地の在りよう。
イワユル「御嶽=うたき」なるもの。
有名どころでは世界遺産でもある
「斎場御嶽(セイファウタキ)」などもそうです。
巨大な岩壁や山のえぐれた部分や穴、
その前に祭壇が設けれれているような姿。
その空気。

例によって古い携帯写真ですが......


沖縄本島の中央、
浜比嘉島の「シルミチュー」などは深い洞窟になっていて。
もう、とてもじゃないですけど、
シロートのワタクシメには入る気すらも起きません。
沖縄や宮古島には他にも沢山そんな聖地が点在していますが、
「カモスの穴」といつのは、
そんな聖地の穴や構造にも似ている気がします。

ここまで記すと、
もうお分かりの方もいるかとは思いますが......
これら全てに共通するもの。
それは......
「忌部氏(いんべし、いむべし)」
天太玉命(アメノフトダマ ノ ミコト)を祖神とする
古代朝廷の祭祀を司っていた一族。
神魂神社(かもすじんじゃ)は、
ある時期以降、一時期......おそらくは今も、
この忌部氏との関わりが深い神社の様に思います。
境内の「穴」からは、僕はそれを感じるのです。
忌部氏(いんべし)とは、
記紀が編纂(へんさん)されていた頃の古代大和朝廷において、
祭祀関連の権限を中臣氏(なかとみし)と二分する力を持っていた一族。
古代天皇の側近中の側近。
「斎部」とも書きます。
祭祀関連とは、今で言えば総務省、外務省、財務省、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、宮内庁......
などの省庁をひっくるめたようなもので、
そこに占術までついてくる。
その長ともなれば、まさに内閣官房長官的なもの。
物部氏などの軍産複合派閥、省庁で言えば防衛省、警察庁、国土交通省......
などの体育会系!?グループと双璧をなす文化系最重要ポスト。
その権力の座を巡り中臣氏と長い間争い続け、
徐々にズルズルと後塵を拝していき。
その後「藤原氏」となって栄華を極めていった中臣氏の裏や
影のような存在となっていった氏族です。
歴史の表舞台に多数登場する豪華絢爛たる藤原氏の面々とは
対極の地位に甘んじていたため、
その功績は教科書などにもナカナカ書かれませんが、
とても偉大な氏族さんなのです。
ソモソモ、
列島に稲作が広まる前からこの国にあった重要な穀物
「ひえ=稗」「アワ=粟」
その栽培方法なども忌部氏が伝えた、教えた、とされています。
更に、その他多くの作物の栽培法から、
着物の原料であった麻や綿、絹の作り方、
服の織り方や作り方に至るまで。
民の暮らしに深く関わるあらゆる産業をリードしていた氏族だとも思われます。
なので、忌部氏の祖先は多くの人々から敬われた農業や産業、
商売の神様ともなって行きました。
全国各地で開かれる「酉の市=とりのいち」などは、
元を辿れば、実は、
「天日鷲神(あめのひわしのかみ)」
という忌部氏の祖先神の一柱に辿り着き。
さらには、
伊勢神宮のある地を古くから護ってきた「度会氏(わたらいし)」や、
あの「織田信長」さん迄も、
この忌部氏の血統が後ろにチラつくのです。
記紀(きき)の神話においても、
かの有名な「天岩戸(あまのいわと)」において、
岩戸に隠れてしまった太陽神、
天照大神(アマテラスオオミカミ)を外の世界に引っ張り出す時には、
中臣氏の祖先である天児屋命(あめのこやねのみこと)と、
太玉命の二人で鏡を差し出した......と記されています。
神話では、
双方の祖先神の活躍がとても重要な立ち位置で記されています。
このあたりにも国家の祭司職を巡る2氏族のライバル関係の匂いが漂い、
もっと深く読み込めば、
記紀神話(古事記&日本書紀)というのは、
この2氏族が話し合いながら書き上げていったのではないか?
というような感じすらもしてきます。
そして、
そんな見識を持った上で「記紀」の内容を改めて見てみるに、
先行する「古事記」を記していた頃は、
中臣、忌部の両氏族はまだ諸事をしっかりと二分し、
コミュニケーションも密に計りながら編纂をしていた様に感じます。
が、後発の「日本書紀」の頃には、
そのバランスは大きく中臣氏に偏って編集されたように思えます。
「古語拾遺(こごしゅうい)」
という古書があるのですが、それは、
そんな「日本書紀」に対抗するために、
斎部広成(いんべひろなり)が独自に記したものです。
しかしながら、
強大であった忌部氏の足跡は今も日本各地に
神社や地名などでシッカリと残っていて。
そんな氏族の大きな拠点としては
「出雲(島根県)」
「紀伊(和歌山県)」
「阿波(あわ、徳島県)」
「讃岐(香川県)」
「安房(あわ、千葉、房総)」
あたりとなるのでしょうか。
それらの本拠として奈良県、橿原市の地にも
忌部という名前が残っています。
この中で、
出雲と奈良に関しては天皇や朝廷の命に従ったり、
付き添う形での移住だとも考えられるので、
その他の地域をよくよく見てみると、
忌部氏が列島にやってきた経路が浮かび上がっても来ます。
それは明らかに、太平洋側、
黒潮の海流に乗って移動して来たであろうことが手に取るように浮き出て来るのです。
ちなみに、中臣氏は......
長崎県、対馬との繋がりが深い様にも思います。
......戻りますが......
そんなワケで、
沖縄を中心とする列島南方の島々に見られる祭祀の形が、
忌部氏に縁が深い神社には「所々」見て取れるというわけで。
忌部氏が「ひえ」や「アワ」などの穀物の知識も詳しく持っていて、
海洋航海技術などもとても優れていた......
ということにも納得がいくのです。
忌部氏の移り住んだ場所の地名に
「アワ」とう名前がつけられている要因も、
穀物の神というコトでよく分かりますし、
神話の中にも
「アワシマ=淡島」は神々が最初に造った島、
と書かれていたりもします。
古事記の編纂者として今に伝わる「稗田阿礼 (ひだのあれ)」の苗字部分が
「稗(ひえ)の田」となっているところにも、
この人物が忌部氏の関連であろうと、僕には想像出来るのです。
神話において忌部氏の祖先神が英雄的に書かれていることも
ここで理解できるのです。
この国の文化や文明の「基礎」の部分には、
遠く南方洋から伝わってきたモノモノも
色濃く組み合わされていたりすると思うのですが、
それらは忌部氏の影響がとても大きい様に思えます。
沖縄の創造神、太陽の女神がアマテラスと似た名の
「アマミキヨ」だったりするのも、なんとなく、
神話作家陣の一部でもあった忌部氏との関係性を
思い計ったりもしてしまいます。
記録では、
忌部子人(いんべおびと、いんべこびと)という人は、
朝廷から「出雲守」として、
征服した出雲の民が反乱を起こさぬように、
出雲で謀反の動きがアレば早めにチェックするように、と、
「朝廷のお目付け役」として出雲に派遣された、と記されています。
その時に住んだ場所が、今の松江市「忌部町」であり。
移住後すぐに、その地域の最重要地であった神魂神社を押さえ。
ソコに自らの祭祀の流儀を被せながら管理もしていった。
そんな痕跡が神魂神社の穴......なのか......
全て、数奇なるおとぎ話、個人的想像譚......ですが、
静謐(せいひつ)なる神魂神社(かもすじんじゃ)の穴の前に立つと、
その穴の奥からは、僕にはこんな物語が流れ出してくるのです。
きっと、忌部氏もまた、
古代日本の「8を巡る旅」における「呪」の旅人なのではないのか?
と、思っていたりもします。
しかし、
今回のこの記事......
書くのがメタクタ大変で......
色々と......飛んで来て!?
タイヘンす。(@_@)
こんなメンドくさくて胡散臭い、
難解な記事を最後まで読んで頂き、本当に感謝です。
ありがとうございます。
「8を巡る旅」のシリーズ記事は以下のテキストリンクで。
おやすみなさい。(^^)
「8を巡る旅」「2」「3」「4」
「6」以降。