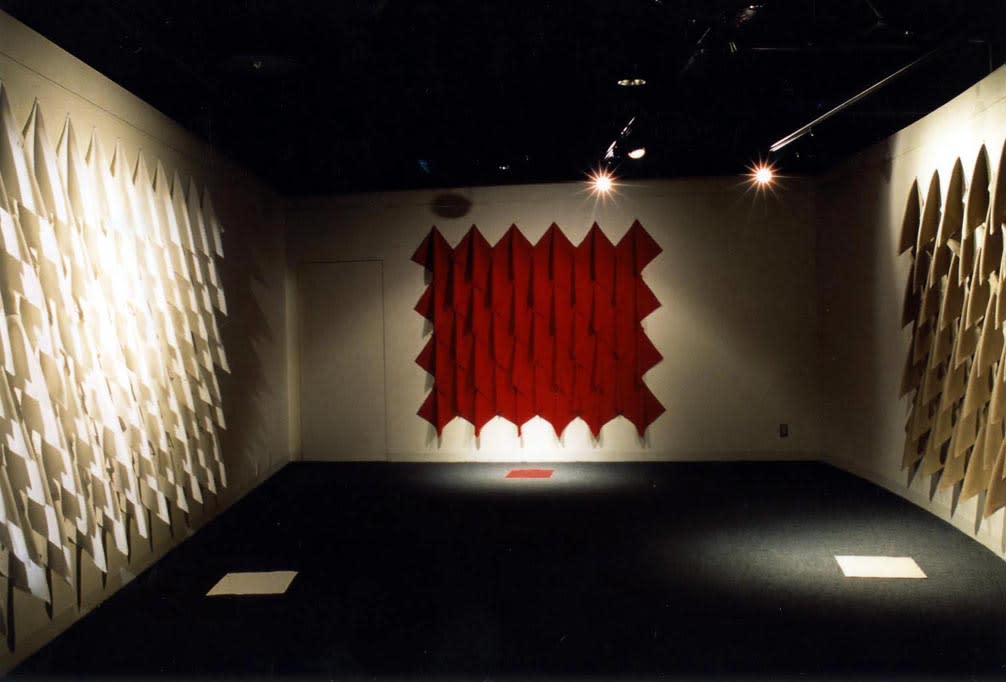1996年9月25日発行のART&CRAFT FORUM 5号に掲載した記事を改めて下記します。
木綿染め研究グループ報告
天然染料による下染めの比較検討(2)
-赤をより赤く染めるために-
富田和子
※ 実習担当者:大方悦子・太田晴美・工藤いづみ・近藤由巳・酒井和美・富田和子・久常久美子・矢部淑恵・米倉伸子
6.バリ島トゥガナン村の染色
前回報告した実習の際に、一緒に試し染めをしたバリ島の糸は驚くほど濃く赤く染まった。その糸はすでにクミリで下染めされていて、たっぷりと油を含みベトついた手触りで糸の色は黄変していた。果してこれはどのようにクミリで下染めされたのだろうか。1996年3月現地で調べてみた。
バリ島東部に島の先住民であるバリ・アガ族の人々が暮らす集落のうちのひとつ、トゥガナン・プダリンシンガン村がある。この村では「グリンシン]と呼ばれる木綿の経緯絣が織られている。東南アジアの広い地域に渡って経絣や緯絣が織られている中でも、経緯絣に関してはバリ島のこの村でしか織られていない。また、かってバリ島内の他の地域で盛んに織られていた緯絣が、今では紡績糸を化学染料で染め、飛抒装置を備えた高機で量産されているのに比べ、トゥガナン村では村の閉鎖的な独自性とともにグリンシンの染織技法は守られ、受け継がれてきた。
グリンシンを織るための糸は、バリ島の東南すぐ近くに浮かぶプニダ島で作られる手紡ぎの単糸を使う。糸は先ずクミリで下染めされるが、そこで登場したのは何と油だった。その油は村内の他の家で作られていて、殻を取ったクミリの実をモーターの付いた木製の機械で粉砕し、小型の圧搾機で油脂分だけを搾り出したものだった。クミリの油と灰汁を3対5の割合で混合した液に糸を浸し、42日間浸けておき、日に干す。何日干すのかという質問に乾くまでという答が返ってきたが、1970年代に調査された資料によれば、再び42日間竿に掛けて干し太陽や夜露に晒すと書いてある。さらにこのあと数枚分の経糸を整経し、緯糸を準備し、絣括りをしなければならず、糸が染められるまでにはまだ暫く日数がかかる、絣括りを終えると別の村へ糸を運び、まず藍で染めた後、いよいよトゥガナン村で赤色を染める。赤く染める部分の絣括りを解き、バリ島ではスンテイと呼ばれているヤエヤマアオキにクプンドゥンという媒染剤の役割を果たすと思われる樹皮を加え、気に入った色に染まるまで何回も染め重ねていく。染めへのこだわりは人によって違い、数カ月の人もいれば数年間費やす人もいる。いずれにせよそんなゆったりとした時間の流れの中で木綿糸は染められているのだった。
7.正体は「油」
驚くほど鮮やかに染まったバリ島の糸の正体は「油」だった。「油+何か」が必要なはずだと思い込んでいた私にとってこの結末は驚きであった。確かに実習の結果を見ても油で下染めをした糸が最も濃く染まっていた。
では、なぜ油が良いのだろうか…。いったい油はどんな役割を果たすのか…。資料を探しているうちに木綿に赤色を染める時に油を用いる方法が古来よりの常法であることを知った。
※『西洋茜の根から採れるアリザリンを染着させるのに古代では非常に厄介な方法が使用されていた。西洋茜と藍とは何世紀もの間、最も重要な染料として用いられてきた。トルコ赤(Turkey red)と呼ばれる色を出すために、昔は次の方法を行っていた。すなわち木綿をまず石灰の入った酸敗したオリーブ油に浸し、次に硫酸アルミニウム溶液で処理し、最後に蒸気をあてる。このようにして媒染した布を染料を水に細かく懸濁させた液で処理する。コロイド状の金属水酸化物が繊維にくっっき、それが染料分子と結合して錯塩すなわちレーキを形成するわけである。トルコ赤で染色する昔の方法では完成するまでに4カ月もかかったがオリーブ油のかわりに硫酸化ひまし油(ロート油、Turkey-red oilともいう)を使用する今日の方法では5日位しかかからない。』(*1)
※ 『六葉茜の主成分のアリザリンはアルミニウム塩と少量のカルシュウムを含むことにより緋色を出し堅牢であるが、溶解力が悪くそのままでは染まりにくいため媒染剤を用いて染める。植物繊維を染める場合、媒染剤としては通常ミョウバンが用いられるが、定着を良くするためにアルカリを加え塩基性ミョウバンとする。それに布を浸け急激に乾かないよう湿った部屋でこれを干し、酸化アルミニウムにする。さらにこのアルミニウムの定着をよくするためには、ミョウバンに浸ける前に、牛乳あるいは遊離した脂肪酸を含む酸敗した油を乳化して引く。』 (*2)
『トルコ赤』の染色はトルコやギリシヤの様々な地域で行われ、17世紀~18世紀にはトルコ赤で染めた糸は高価であるにも関わらず、ヨーロッパでは飛ぶように売れるようになり織物や刺繍や縫製作業のために欠くことのできないものになったという。しかし『トルコ赤』の染色法にあるオリーブ油とインドネシアで用いられているクミリの油との繋がり、また油の果たす役割については、資料の中から見つけることはできなかった。
8.木綿繊維について
天然染料の場合、一般的に動物繊維の絹や羊毛に比べ植物繊維の木綿や麻は染まりにくい。絹は主にフィブロイン、羊毛は主にケラチンという、アミノ酸から構成されるタンパク質でできている。 タンパク質には、アミノ基・カルボル基といった酸性や塩基性の基が多数残っているため各種の染料の物質とは塩を形成して結合、染着性にすぐれている。また媒染剤の金属塩やその他の物質を吸収したり、反応する性質に富んでいる。木綿はほとんど中性のセルロース分子から構成されていて、タンパク質のような性質を持っていない。さらに、木綿繊維の構造上からも染まりにくい点を持っているようである。
※ 『セルロースは、グルコース分子がβ結合で数千個以上つらなってできた鎖上高分子である。このような鎖上高分子が多数束になって集まり、ところどころには整然とならんでミセルとよばれる微結晶の部分をつくっている。ミセルを構成するセルロース分子の束は。さらにいくつかが集まって、やっと電子顕微鏡で見える程度の束になる。このように多数の分子鎖が集合をくりかえしてわれわれが目にする綿の繊維ができているのである。』(*3)
繊維はその種類に関わらず、細長い形をしている繊維の分子が多数集まって、さらに細長い束をつくり、目に見える1本の繊維となっている。「糸が染色されている」と言える のは、色素が繊維の内部まで浸透し、化学的に結合をしているか、もしくはある程度以上の堅牢度を持つ状態であるという。木綿の場合は繊維の束のところどころにある微結晶部分には染料が浸透しにくいこと、また、木綿にはイオン性がないためイオン結合による染着ができないことが、「苦労を伴う木綿の草木染め」となっている。
木綿を天然染料でより濃く堅牢に染めたい時には染色と媒染を繰り返して行う方法が一般的だが、それでは濃く染めることができない染料もある。その代表的なものが赤色を染める染料ということになる。また、今回の実習で使った茜類は先にアルミニウム塩を繊維に吸着させる媒染法で染めなければならない。木綿はそのままでは媒染剤を吸着しにくいので、いかにして木綿に処理を施し、染料が染着されるような塩基性または酸性の基を繊維に定着させるかというイオン化方法に関して古来より先人達は知恵を絞ってきたのだった。
9.実習の分析結果
『油』が木綿に媒染剤を吸収させるために有用であるらしいことはわかったが、疑問は解決しなかった。そこで「長野県情報技術試験場・繊維科学部」に実習結果の糸サンプルを送り分析を依頼したところ、同試験場の堀川先生より次のようなご教示を頂いた。
『まず、インド茜で着色した糸についてですが、クミリによる下地は、油の酸敗によって生成した脂肪酸が染着を促しているのではないかと考え、糸に少量の水を付け、そのpHを調べましたが、着色前、着色後ともに中性であり、促染効果があるほどのPHにはなっていないと判断されました。次に着色された糸を顕微鏡で観察してみますと、次のような状態に見えました。(*顕微鏡の倍率は40~400倍)
(1)バリ島で入手のクミリで下地をした糸……繊維全体ではなく、部分的にしか色が着いていない。さらに拡大すると、表面の付着物に色が着いているにすぎないことがわかる。
(2)クミリで下地をした糸……バリ島で人手のものよりさらに顕著であり、繊維にはほとんど色が着いておらず、繊維の表面あるいは隙間にある付着物が着色しているだけである。この付着物は、繊維の太さよりもかなり大きいものもある。
(3)くるみで下地をした糸……(2)と同様。
(4)オリーブ油で下地をした糸……クミリ下地よりはなめらかに繊維を覆っており、一見染まっているようにも見える。しかし、まわりに惨み出し、カバーグラスを汚してしまう。(5)タンニン酸で下地をした糸……むらではあるが、繊維全体が着色されている。
以上の結果からみて、染色されていると評価できるのはタンニン下地のものだけでありあとのものは繊維の表面または隙間に入り込んだ油脂等に色が着いているにすぎないと判断されます。糸の撚りを戻してみてください。着色していない部分が現れるでしょう。白い布でこすってみてください。白布に簡単に色が移り、ついには赤い糸の色がほとんどなくなるでしょう。ただ、バリ島で入手のものは、付着物の粒子が小さく、実習でクミリ下地したものよりもかなり工夫されたものと思われます。また、通常、油汚れは、リグロインまたはエタノールで溶かし出せますが、バリ島で入手のものはほとんど溶け出しません(オリーブ油下地のものは溶け出します。)この点でもかなり工夫を重ねた方法だと思われます。』
また、こちらからの質問に対して次のような回答を頂いた。
Q:油は木綿繊維に対しどの様な状態で存在しているのか。
A:このクミリやオリーブ油の場合については、繊継の表面を覆うか、隙間に入り込んでいるだけだとみなされる。
Q:アルミニウムの定着をよくするために油を使うとあるが、この場合の定着とはどのような状態なのか。アルミニウム塩と油は化学的に結合しているのかどうか。
A:糸への浸透を促すためではないか。
Q:遊離した脂肪酸を含む酸敗した油を乳化して使用するというのはどういう意味・必要性があるのか。
A:遊離した脂肪酸を促進剤として利用し、乳化は均一化し、むらを防ぐためではないか。ただし、実習のクミリ下地の場合はそのような効果はみられない。
Q:油に灰汁を加えて使用することの意味は何か。
A:反応のためのpH調整と、含まれる金属成分を発色に利用するためではないか。
Q:資料を調べていくうちにロート油で媒染をする「油媒」という方法があることも知ったが、タンニン酸や豆汁・牛乳のタンパク質を利用するのに比べなじみがないのは何故なのか。
A:このクミリの下地を見ての推測ですが、油を使った着色は摩擦による色落ちが著しく、日本の生活では白い襖や青畳を汚してしまい、なじまなかったのではないか。
10.おわりに
指摘されたように、実習した糸サンプルの撚りを戻し、細い繊維一本ずつが見えるようにほぐしてみると、確かにタンニン酸下地以外の糸は染まらずに残っている白さが目立っている.残念ながら私たちの実習結果は糸を染めたとは言えない状態であった。分析して頂いた結果からもわかることは種実をそのまま潰して使うよりも、やはり油の方が適しているようである。しかし油ならば良いというわけではない。リグロインまたはエタノールで溶け出してしまうオリーブ油下地のものと、溶け出すことのないバリ島のクミリ下地のものとの違いは何なのだろうか。油の成分、灰の成分、灰汁に使う雨水、灰汁の作り方、そして費やされる月白…。全てが違っていたといえばそれまでだが、このバリ島の糸の「工夫されたもの」が一体何であるのか、謎はなかなか解きあかすことができない。
当初は、油を用いる下地染めは、赤色を染めるためにこそ必要なのだと思い込んでいた、しかし、京田誠先生よりメキシコでの貝紫染めに「牛脂石鹸」を下地に使ったという体験談をお聞きした。木綿糸を貝紫で染める前にセボ・デ・バカ(牛脂)の石鹸でよく洗い、乾かして染めると良いと教わったことを精錬の意味だと解釈し、糸を石鹸で洗いきれいにすすいだ。ところがその糸の染まり具合は良くなかった。実は‥・
※『貝の染液は、糸に何の細工(処理)をしなくても紫色に先着発色はするが、濃いきれいな紫色に染めるにはセボ・デ・バカで洗った後、すすがずにそのまま糸を乾かして染めるという“秘訣”があったのである。彼等、染め人達にとっては、このことは公然の秘密、いや常識になっているのだろうが、ドンルイス村で最初に出会った染め人ビクトリオもセボ・デ・バカのことは一言もいわなかった。』(*4)というものである。
色素の染着しにくい木綿糸が堅牢に生き生きと染まりあがるために、その土地にふさわしい方法で「工夫」は必ず行われているのだった。糸を染める時にはまず精練をして、染色のじゃまになる脂肪分やその他の不純物を取り除かなければならない、とインプットされていた私の頭には、未精練の糸にしかも油を付けるなどとはとんでもないということが常識であった。実習は糸を確実に染めるという点では不十分に終わったが、常識というものがくつがえされたことは実に興味深かった。インドネシアの染め方に習って始めた今回の研究であったが、自然と向き合って生きてきた人々の知恵に、今の私たちはまだまだ追いつけずにいる。簡単に堅牢に染色するためには化学染料を使った方が良いことも確かだが、天然染料から化学染料へと移り変わる中で、私たちが見捨ててきてしまった価値あるものも確かに存在するのである。
バリ島のトゥガナン村で作られる「グリンシン」の染色で、本当に良い色を染め出すためには数年間を費やすという。そうして染めた糸で織られた布は年月が経つほどに濃く、深く、すばらしい色になっている。村人たちは50年物、80年物といったグリンシンを誇らしげに、ひろげて見せてくれた。そんな時の流れ方を私たちはすでに失ってはいないだろうか。(終わり)
[引用文献]
(*1)『フィーザー有機化学(下)』 P.876 丸善(1971)
(*2)吉岡常雄『天然染料の研究』 P.164 光村推古書院(1974)
(*3)『原色現代科学大事典(9-化学)』p.191 学研(1968)
(*4)京田誠・星野利枝『貝紫染紀行』P.94~98 染織と生活 第25号
染織と生活社(1979)
[参考文献]
(1)『フィザー有機化学(下)』 丸善(1971)
(2)『原色現代科学大事典(9-化学)』 学研(1968)
(3)前川悦朗『天然染料の不思議を考える(上)』 染織& NO.184染織と生活社(1996)
(4)高橋誠一郎『木綿の草木染-その特性と技法』染織& NO.54染織と生活社(1985)
今回の研究報告の執筆にあたり、長野県情報技術試験場 繊維科学部 堀川精一先生、名古屋工業大学名誉教授 前川悦朗先生には多くのご教示を頂きました。この紙面を借りまして心より御礼申し上げます。
木綿染め研究グループ報告
天然染料による下染めの比較検討(2)
-赤をより赤く染めるために-
富田和子
※ 実習担当者:大方悦子・太田晴美・工藤いづみ・近藤由巳・酒井和美・富田和子・久常久美子・矢部淑恵・米倉伸子
6.バリ島トゥガナン村の染色
前回報告した実習の際に、一緒に試し染めをしたバリ島の糸は驚くほど濃く赤く染まった。その糸はすでにクミリで下染めされていて、たっぷりと油を含みベトついた手触りで糸の色は黄変していた。果してこれはどのようにクミリで下染めされたのだろうか。1996年3月現地で調べてみた。
バリ島東部に島の先住民であるバリ・アガ族の人々が暮らす集落のうちのひとつ、トゥガナン・プダリンシンガン村がある。この村では「グリンシン]と呼ばれる木綿の経緯絣が織られている。東南アジアの広い地域に渡って経絣や緯絣が織られている中でも、経緯絣に関してはバリ島のこの村でしか織られていない。また、かってバリ島内の他の地域で盛んに織られていた緯絣が、今では紡績糸を化学染料で染め、飛抒装置を備えた高機で量産されているのに比べ、トゥガナン村では村の閉鎖的な独自性とともにグリンシンの染織技法は守られ、受け継がれてきた。
グリンシンを織るための糸は、バリ島の東南すぐ近くに浮かぶプニダ島で作られる手紡ぎの単糸を使う。糸は先ずクミリで下染めされるが、そこで登場したのは何と油だった。その油は村内の他の家で作られていて、殻を取ったクミリの実をモーターの付いた木製の機械で粉砕し、小型の圧搾機で油脂分だけを搾り出したものだった。クミリの油と灰汁を3対5の割合で混合した液に糸を浸し、42日間浸けておき、日に干す。何日干すのかという質問に乾くまでという答が返ってきたが、1970年代に調査された資料によれば、再び42日間竿に掛けて干し太陽や夜露に晒すと書いてある。さらにこのあと数枚分の経糸を整経し、緯糸を準備し、絣括りをしなければならず、糸が染められるまでにはまだ暫く日数がかかる、絣括りを終えると別の村へ糸を運び、まず藍で染めた後、いよいよトゥガナン村で赤色を染める。赤く染める部分の絣括りを解き、バリ島ではスンテイと呼ばれているヤエヤマアオキにクプンドゥンという媒染剤の役割を果たすと思われる樹皮を加え、気に入った色に染まるまで何回も染め重ねていく。染めへのこだわりは人によって違い、数カ月の人もいれば数年間費やす人もいる。いずれにせよそんなゆったりとした時間の流れの中で木綿糸は染められているのだった。
7.正体は「油」
驚くほど鮮やかに染まったバリ島の糸の正体は「油」だった。「油+何か」が必要なはずだと思い込んでいた私にとってこの結末は驚きであった。確かに実習の結果を見ても油で下染めをした糸が最も濃く染まっていた。
では、なぜ油が良いのだろうか…。いったい油はどんな役割を果たすのか…。資料を探しているうちに木綿に赤色を染める時に油を用いる方法が古来よりの常法であることを知った。
※『西洋茜の根から採れるアリザリンを染着させるのに古代では非常に厄介な方法が使用されていた。西洋茜と藍とは何世紀もの間、最も重要な染料として用いられてきた。トルコ赤(Turkey red)と呼ばれる色を出すために、昔は次の方法を行っていた。すなわち木綿をまず石灰の入った酸敗したオリーブ油に浸し、次に硫酸アルミニウム溶液で処理し、最後に蒸気をあてる。このようにして媒染した布を染料を水に細かく懸濁させた液で処理する。コロイド状の金属水酸化物が繊維にくっっき、それが染料分子と結合して錯塩すなわちレーキを形成するわけである。トルコ赤で染色する昔の方法では完成するまでに4カ月もかかったがオリーブ油のかわりに硫酸化ひまし油(ロート油、Turkey-red oilともいう)を使用する今日の方法では5日位しかかからない。』(*1)
※ 『六葉茜の主成分のアリザリンはアルミニウム塩と少量のカルシュウムを含むことにより緋色を出し堅牢であるが、溶解力が悪くそのままでは染まりにくいため媒染剤を用いて染める。植物繊維を染める場合、媒染剤としては通常ミョウバンが用いられるが、定着を良くするためにアルカリを加え塩基性ミョウバンとする。それに布を浸け急激に乾かないよう湿った部屋でこれを干し、酸化アルミニウムにする。さらにこのアルミニウムの定着をよくするためには、ミョウバンに浸ける前に、牛乳あるいは遊離した脂肪酸を含む酸敗した油を乳化して引く。』 (*2)
『トルコ赤』の染色はトルコやギリシヤの様々な地域で行われ、17世紀~18世紀にはトルコ赤で染めた糸は高価であるにも関わらず、ヨーロッパでは飛ぶように売れるようになり織物や刺繍や縫製作業のために欠くことのできないものになったという。しかし『トルコ赤』の染色法にあるオリーブ油とインドネシアで用いられているクミリの油との繋がり、また油の果たす役割については、資料の中から見つけることはできなかった。
8.木綿繊維について
天然染料の場合、一般的に動物繊維の絹や羊毛に比べ植物繊維の木綿や麻は染まりにくい。絹は主にフィブロイン、羊毛は主にケラチンという、アミノ酸から構成されるタンパク質でできている。 タンパク質には、アミノ基・カルボル基といった酸性や塩基性の基が多数残っているため各種の染料の物質とは塩を形成して結合、染着性にすぐれている。また媒染剤の金属塩やその他の物質を吸収したり、反応する性質に富んでいる。木綿はほとんど中性のセルロース分子から構成されていて、タンパク質のような性質を持っていない。さらに、木綿繊維の構造上からも染まりにくい点を持っているようである。
※ 『セルロースは、グルコース分子がβ結合で数千個以上つらなってできた鎖上高分子である。このような鎖上高分子が多数束になって集まり、ところどころには整然とならんでミセルとよばれる微結晶の部分をつくっている。ミセルを構成するセルロース分子の束は。さらにいくつかが集まって、やっと電子顕微鏡で見える程度の束になる。このように多数の分子鎖が集合をくりかえしてわれわれが目にする綿の繊維ができているのである。』(*3)
繊維はその種類に関わらず、細長い形をしている繊維の分子が多数集まって、さらに細長い束をつくり、目に見える1本の繊維となっている。「糸が染色されている」と言える のは、色素が繊維の内部まで浸透し、化学的に結合をしているか、もしくはある程度以上の堅牢度を持つ状態であるという。木綿の場合は繊維の束のところどころにある微結晶部分には染料が浸透しにくいこと、また、木綿にはイオン性がないためイオン結合による染着ができないことが、「苦労を伴う木綿の草木染め」となっている。
木綿を天然染料でより濃く堅牢に染めたい時には染色と媒染を繰り返して行う方法が一般的だが、それでは濃く染めることができない染料もある。その代表的なものが赤色を染める染料ということになる。また、今回の実習で使った茜類は先にアルミニウム塩を繊維に吸着させる媒染法で染めなければならない。木綿はそのままでは媒染剤を吸着しにくいので、いかにして木綿に処理を施し、染料が染着されるような塩基性または酸性の基を繊維に定着させるかというイオン化方法に関して古来より先人達は知恵を絞ってきたのだった。
9.実習の分析結果
『油』が木綿に媒染剤を吸収させるために有用であるらしいことはわかったが、疑問は解決しなかった。そこで「長野県情報技術試験場・繊維科学部」に実習結果の糸サンプルを送り分析を依頼したところ、同試験場の堀川先生より次のようなご教示を頂いた。
『まず、インド茜で着色した糸についてですが、クミリによる下地は、油の酸敗によって生成した脂肪酸が染着を促しているのではないかと考え、糸に少量の水を付け、そのpHを調べましたが、着色前、着色後ともに中性であり、促染効果があるほどのPHにはなっていないと判断されました。次に着色された糸を顕微鏡で観察してみますと、次のような状態に見えました。(*顕微鏡の倍率は40~400倍)
(1)バリ島で入手のクミリで下地をした糸……繊維全体ではなく、部分的にしか色が着いていない。さらに拡大すると、表面の付着物に色が着いているにすぎないことがわかる。
(2)クミリで下地をした糸……バリ島で人手のものよりさらに顕著であり、繊維にはほとんど色が着いておらず、繊維の表面あるいは隙間にある付着物が着色しているだけである。この付着物は、繊維の太さよりもかなり大きいものもある。
(3)くるみで下地をした糸……(2)と同様。
(4)オリーブ油で下地をした糸……クミリ下地よりはなめらかに繊維を覆っており、一見染まっているようにも見える。しかし、まわりに惨み出し、カバーグラスを汚してしまう。(5)タンニン酸で下地をした糸……むらではあるが、繊維全体が着色されている。
以上の結果からみて、染色されていると評価できるのはタンニン下地のものだけでありあとのものは繊維の表面または隙間に入り込んだ油脂等に色が着いているにすぎないと判断されます。糸の撚りを戻してみてください。着色していない部分が現れるでしょう。白い布でこすってみてください。白布に簡単に色が移り、ついには赤い糸の色がほとんどなくなるでしょう。ただ、バリ島で入手のものは、付着物の粒子が小さく、実習でクミリ下地したものよりもかなり工夫されたものと思われます。また、通常、油汚れは、リグロインまたはエタノールで溶かし出せますが、バリ島で入手のものはほとんど溶け出しません(オリーブ油下地のものは溶け出します。)この点でもかなり工夫を重ねた方法だと思われます。』
また、こちらからの質問に対して次のような回答を頂いた。
Q:油は木綿繊維に対しどの様な状態で存在しているのか。
A:このクミリやオリーブ油の場合については、繊継の表面を覆うか、隙間に入り込んでいるだけだとみなされる。
Q:アルミニウムの定着をよくするために油を使うとあるが、この場合の定着とはどのような状態なのか。アルミニウム塩と油は化学的に結合しているのかどうか。
A:糸への浸透を促すためではないか。
Q:遊離した脂肪酸を含む酸敗した油を乳化して使用するというのはどういう意味・必要性があるのか。
A:遊離した脂肪酸を促進剤として利用し、乳化は均一化し、むらを防ぐためではないか。ただし、実習のクミリ下地の場合はそのような効果はみられない。
Q:油に灰汁を加えて使用することの意味は何か。
A:反応のためのpH調整と、含まれる金属成分を発色に利用するためではないか。
Q:資料を調べていくうちにロート油で媒染をする「油媒」という方法があることも知ったが、タンニン酸や豆汁・牛乳のタンパク質を利用するのに比べなじみがないのは何故なのか。
A:このクミリの下地を見ての推測ですが、油を使った着色は摩擦による色落ちが著しく、日本の生活では白い襖や青畳を汚してしまい、なじまなかったのではないか。
10.おわりに
指摘されたように、実習した糸サンプルの撚りを戻し、細い繊維一本ずつが見えるようにほぐしてみると、確かにタンニン酸下地以外の糸は染まらずに残っている白さが目立っている.残念ながら私たちの実習結果は糸を染めたとは言えない状態であった。分析して頂いた結果からもわかることは種実をそのまま潰して使うよりも、やはり油の方が適しているようである。しかし油ならば良いというわけではない。リグロインまたはエタノールで溶け出してしまうオリーブ油下地のものと、溶け出すことのないバリ島のクミリ下地のものとの違いは何なのだろうか。油の成分、灰の成分、灰汁に使う雨水、灰汁の作り方、そして費やされる月白…。全てが違っていたといえばそれまでだが、このバリ島の糸の「工夫されたもの」が一体何であるのか、謎はなかなか解きあかすことができない。
当初は、油を用いる下地染めは、赤色を染めるためにこそ必要なのだと思い込んでいた、しかし、京田誠先生よりメキシコでの貝紫染めに「牛脂石鹸」を下地に使ったという体験談をお聞きした。木綿糸を貝紫で染める前にセボ・デ・バカ(牛脂)の石鹸でよく洗い、乾かして染めると良いと教わったことを精錬の意味だと解釈し、糸を石鹸で洗いきれいにすすいだ。ところがその糸の染まり具合は良くなかった。実は‥・
※『貝の染液は、糸に何の細工(処理)をしなくても紫色に先着発色はするが、濃いきれいな紫色に染めるにはセボ・デ・バカで洗った後、すすがずにそのまま糸を乾かして染めるという“秘訣”があったのである。彼等、染め人達にとっては、このことは公然の秘密、いや常識になっているのだろうが、ドンルイス村で最初に出会った染め人ビクトリオもセボ・デ・バカのことは一言もいわなかった。』(*4)というものである。
色素の染着しにくい木綿糸が堅牢に生き生きと染まりあがるために、その土地にふさわしい方法で「工夫」は必ず行われているのだった。糸を染める時にはまず精練をして、染色のじゃまになる脂肪分やその他の不純物を取り除かなければならない、とインプットされていた私の頭には、未精練の糸にしかも油を付けるなどとはとんでもないということが常識であった。実習は糸を確実に染めるという点では不十分に終わったが、常識というものがくつがえされたことは実に興味深かった。インドネシアの染め方に習って始めた今回の研究であったが、自然と向き合って生きてきた人々の知恵に、今の私たちはまだまだ追いつけずにいる。簡単に堅牢に染色するためには化学染料を使った方が良いことも確かだが、天然染料から化学染料へと移り変わる中で、私たちが見捨ててきてしまった価値あるものも確かに存在するのである。
バリ島のトゥガナン村で作られる「グリンシン」の染色で、本当に良い色を染め出すためには数年間を費やすという。そうして染めた糸で織られた布は年月が経つほどに濃く、深く、すばらしい色になっている。村人たちは50年物、80年物といったグリンシンを誇らしげに、ひろげて見せてくれた。そんな時の流れ方を私たちはすでに失ってはいないだろうか。(終わり)
[引用文献]
(*1)『フィーザー有機化学(下)』 P.876 丸善(1971)
(*2)吉岡常雄『天然染料の研究』 P.164 光村推古書院(1974)
(*3)『原色現代科学大事典(9-化学)』p.191 学研(1968)
(*4)京田誠・星野利枝『貝紫染紀行』P.94~98 染織と生活 第25号
染織と生活社(1979)
[参考文献]
(1)『フィザー有機化学(下)』 丸善(1971)
(2)『原色現代科学大事典(9-化学)』 学研(1968)
(3)前川悦朗『天然染料の不思議を考える(上)』 染織& NO.184染織と生活社(1996)
(4)高橋誠一郎『木綿の草木染-その特性と技法』染織& NO.54染織と生活社(1985)
今回の研究報告の執筆にあたり、長野県情報技術試験場 繊維科学部 堀川精一先生、名古屋工業大学名誉教授 前川悦朗先生には多くのご教示を頂きました。この紙面を借りまして心より御礼申し上げます。