中P連の総会が無事終わった。
総会は前年度の報告と新年度の承認事項があるから、当然この時期に集中する。
で、私の場合は前年度は小学校のPTA会長、今年度は中学校のPTA会長になるんで双方に参加。
さらに、前年度は小学校が南区の理事校、今年度は中学校が下京・南支部の理事校ってんで、それぞれの支部の総会も参加。
おまけに、前年度は小P連の役員、今年度は中P連の役員ってんで、その総会も…
ただ参加ってだけなら、総会を構成する権利者のひとりとして、あれこれの総会に参加し、報告をしっかり聞かせていただくということもある。
が、今回に限っては、上記のすべてが壇上で報告したり承認されたりの立場(笑)
当然、その当日だけ参加すればいいってことではなく、事前に何度も会議を開いて会計や事業のチェックが必要になる。
そのほかにも、地域などでの役割として参加する総会もいくつかある。
いやぁ、いい経験させていただきました。
(あとひとつ、来月に残ってるのもあるんですが)
こう書くとPTA会長って無茶苦茶負担があるように思われますが(いや、確かに時間的金銭的負担はいっぱいあります 笑)この立場だからこそ参加できる講演会や研修会があり、そこで受ける刺激は時間やお金の負担に換算できない、充実を与えてくれます。
(今までいろんな講演で受けて刺激もいっぱいアップしてますので、探してみてください)
昨日も総会に引き続いての研修会で素敵なお話を聞かせていただきました。
講師は藤田裕之京都市副市長
私がPTA会長になる前に「教育委員会生涯学習部長」をされており、また行政区区長として地域のかかわりを肌に感じて来られた、PTAとは縁の深い方。
今回の研修会講師をどなたにお願いするかの会議の中で、副市長就任直後でお忙しいだろうが、もし時間のご都合が合えばぜひお願いしたいということで、なんとかご都合をつけていただけた。
テーマは「地域ぐるみの人づくり・まちづくり ~PTA活動に期待すること~」と、まさに藤田氏だからこそ語っていただける、私が今一番聞いておきたいこと。
PTA仲間でPTAについて語り合うことはとても楽しいし、多くの学びになるけれど、べつの視点からもらえる”気づき”がないと、枠が狭くなる。
お話はPTAをめぐるところで多岐にわたっていた。
子どもをめぐる現状であったり、近年話題になる教育委員会のあり方であったり、それらもただ現状を憂いたり問題提議するのではなく、「そこにPTAがどう関わっていくのか」ということを投げかけてくださる。
ちょうど、この春の卒業式や入学式で祝辞を贈らせていただくとき、またいろんな総会で挨拶をさせていただくときにいつも話させていただいた「規範ということは親がまずわが身を振り返り、子どもの手本となることを考えなければ」ということについても、藤田氏の口からしっかりと聞かせていただいた。
自分の思いとリンクすると、単純にうれしい気持ちになるのと共に、それは独善ではなく大事なことを聞かせてもらい伝えさせてもらっていることが確認できる。
学校や先生の批判を家庭ですると、子ども自身も不信を持ってしまうし、結果として学力向上の妨げになる。
PTAとして学校という教育環境に関心を持ち思いを伝えていくことは、なんでも学校任せにするよりは大事なことではあるけれども、自分の考え方を押し付けることになれば困ったことだし、それが批判・否定になってしまえば、学校と家庭の関係が難しくなるだけではなく、子どもたちに悪影響を与えてしまう。
そこに、家庭という個の単位でなくPTAという形で「いろんな考え方がある」ことを見聞きしていくことの意味は大きい。
単なるイベントをこなすための活動ではなく、子どもに繋がっていく活動だということは言いつづけていたが、その具体的な意味が藤田氏のお話でストンと腑に落ちた気がした。
あと、私がPTA活動に取り組みだしたときにすでに出来上がっていたいろんな仕組みが、それを作り出すことに関わってきた藤田氏から聞かせてもらうと、「形だけのこの活動はどうなんだろう?」と思っていたものの意味と、作り上げるときの思い・熱が伝わってきた。
根本を知らないから「形だけ」と思ってしまったが、その役割を考えて活用すれば、私自身が「こういう活動はできないだろうか?」と考えることを実現する器として用意されていたことがわかった。
当たり前のように思っていた「子どもを共に育む京都市民憲章」にしても、親としてPTAとして、この憲章をどう見るかによって大きく意味合いが変わってくる。
私の少し前の先輩方がそういう作り上げられていく熱のさなかに居られたが、その熱は伝わってきてもいまひとつノリ切れない感もあった。
出来上がっているものを、そのなぜ作る必要があったかから知っている人と、出来た物だけ見ている人。
その温度差を今回のお話でつないでもらった気がした。
そう、東北震災のことでも、話だけ聞いていた段階と、現地を訪れて肌で感じてからでは、私の中の意味合いが大きく変わったように。
本当は、話していただいた中身をそのままお伝えすることが大事なんだとは思うが、このブログはかなり私の考えが混じっているものと理解してください。
最後に、中身ではなく、その立ち居振る舞いというところで。
まずは話し慣れて居られる感じからの安心感が強かった。
おそらく、声のトーンや話す速度、間の取り方が私の感覚にあうのだろう。
そして、資料としてはパワーポイント用に作成されているが、パワーポイントは使わずに話をされたこと。
以前のエントリーで話題にしたこともあったが、スクリーンを見やすくするために暗くして講演者の
顔が見えないのはとてもさびしい。
しっかりお顔を拝見しながら、その中身を話してくだされば、資料を見る必要はない。
そういう意味でも、終始藤田氏と会場が繋がってる状態でお話を聞かせてもらえたのはうれしい。
まだまだ余韻が残っていて、いろいろ語りたくなるけれど、何日かして私の中で熟成されたり、他の話題とリンクしたりしたらまた書くかもしれない。
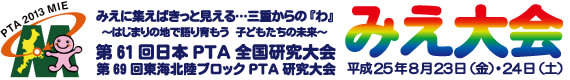











 第61回日本PTA全国研究大会 三重大会に参加してきました。
第61回日本PTA全国研究大会 三重大会に参加してきました。
