蚕が桑の葉をたくさん食べて育つ頃なのだそうです。生き物がどんどん成長する時期ですね。
小さな株でも桑の実は熟しています。
桑はとてもたくましい植物で、その実を鳥などが食べてタネが運ばれるのだと思いますが
私の散歩道にも住宅街のちょっとした空き地にも、そちこちで桑の木を見かけます。
あっという間に育ってすぐに実をつけるようになります。

そんな生命力あふれる桑は、葉だけでなく実も枝も根も生薬です。
桑の葉:桑葉(そうよう)辛凉解表薬(疏散風熱 清肺潤燥,止咳 平肝陽 明目)
桑の成熟した実:桑椹(そうじん)補益薬(滋陰補血 生発烏髪 生津)
桑の根皮:桑白皮(そうはくひ)化痰止咳平喘薬(瀉肺平喘 利水消腫)
桑の若枝:桑枝(そうし)袪風湿薬(袪風湿 通絡 利関節 行水退腫)
部位によってこれほど使い分けして利用されるなんて素晴らしいですね。















 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
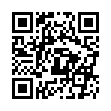


 漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック
漢方家ファインエンドー薬局フェイスブック





 虎が吼えれば風が生まれ、
虎が吼えれば風が生まれ、 龍が昇れば雲が起こる
龍が昇れば雲が起こる


 「すっきり晴れると鼻やノドがカサカサになっちゃって。潤う食べ物って何があります?」
「すっきり晴れると鼻やノドがカサカサになっちゃって。潤う食べ物って何があります?」 果物なら梨、食材ならレンコンとかシロキクラゲ・・・・
果物なら梨、食材ならレンコンとかシロキクラゲ・・・・
 「西風粛殺、これに感ずるものは多く風燥を病む」
「西風粛殺、これに感ずるものは多く風燥を病む」 枯れてくる
枯れてくる 中高年は
中高年は で、このところの新型インフルエンザ。
で、このところの新型インフルエンザ。 これまで子供が危ないといわれていたのに、中高年もその渦に巻き込まれている様子。
これまで子供が危ないといわれていたのに、中高年もその渦に巻き込まれている様子。
 つまり丑年は季節で言えば冬の最後、何が飛び出すかわからないけど、
つまり丑年は季節で言えば冬の最後、何が飛び出すかわからないけど、 月の光が冴え渡ってましたね。
月の光が冴え渡ってましたね。
 そこで中国古代の養生書、黄帝内経(こうていだいけい)素問の四気調神大論から
そこで中国古代の養生書、黄帝内経(こうていだいけい)素問の四気調神大論から 冬の養生法をご紹介。
冬の養生法をご紹介。
 立冬からの3か月は「閉蔵(へいぞう)」の季節。
立冬からの3か月は「閉蔵(へいぞう)」の季節。 冬眠しませんが、できることなら
冬眠しませんが、できることなら

 は禁句。
は禁句。 ビールで、心も体も涼しく、が好みだ。
ビールで、心も体も涼しく、が好みだ。 夏の三か月は、
夏の三か月は、 天地の気は盛んに行き交い、万物は
天地の気は盛んに行き交い、万物は 花咲き実をつける季節。
花咲き実をつける季節。 すこし遅くに寝てもいいが、朝は
すこし遅くに寝てもいいが、朝は が外にあふれるように気持ちよく過ごす。
が外にあふれるように気持ちよく過ごす。

 暗くなってくる。(ちなみに千葉では日の出6:45 日の入り16:30)
暗くなってくる。(ちなみに千葉では日の出6:45 日の入り16:30) 師匠でも
師匠でも 走ってしまう、おまけに勉強もろくにできず
走ってしまう、おまけに勉強もろくにできず 陽(よう)の力が一年で最も弱まる日ながら、
陽(よう)の力が一年で最も弱まる日ながら、 一陽来復の日として尊ばれたそう。
一陽来復の日として尊ばれたそう。