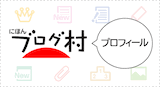今元日に生じた、北陸能登震災。懸念の通り、犠牲被害各位の人数は 日を追う毎に増えている様だ。未だ孤立を余儀なくされる地区もあるやに聞くし、その事から 震災被害の全貌も捉え切れていない様でもある。
改めての犠牲各位への弔意と 被災各位へのお見舞いを表す次第だが、警察、消防、自衛隊や海保、在日米軍などは支援の手を拱いている訳では決してなかろう。現に近く、被災地の損壊道路復旧などで国の補助が増やせる 激甚災害指定が行われる見通しと聞く。
対自衛隊は(左からの)風当たりが強い様で、初動が遅いとか 部隊の逐次投入などへの疑問も寄せられているやに聞くが、妥当な出方なのか?以下 今日の TBS NEWS DIGネット記事を引用して、みて参る事に。
「自衛隊 5400人態勢に ”逐次投入”指摘に 木原防衛大臣『活動可能な地域では全力で実施した』能登半島地震」
木原防衛大臣は 能登半島地震の自衛隊災害派遣について、きょうは人員を 400人増強し、5400人(規模の)態勢で捜索救助活動を行うと発表しました。
木原防衛大臣「生活支援の質および量の向上なども踏まえ、さらに部隊を増強させていく考えです」
自衛隊はきょう ▼人員 5400人(規模) ▼捜索犬 12頭 ▼航空機 約 30機 ▼艦艇 9隻を投入して 捜索救助活動や生活支援活動にあたります。
また 木原防衛大臣は自衛隊の災害派遣活動をめぐり「逐次投入している」「初動が遅い」といった指摘が出ていることに触れ ▼被災地が半島という地理的特性や ▼中でも(能登半島)北部の被害が大きいこと ▼道路が寸断され インフラ(社会資本)網が途絶えていることなどを挙げました。
その上で「初期の段階では 空中機動力を重視した航空機を活用した被害状況の把握に努めていた」と説明しました。さらに「活動可能な地域においては 捜索、救助、被災者支援を全力で実施した」と強調しました。(引用ここまで)
拙者がここまで拝見してきた 北陸能登震災報道などから、数年前の熊本震災並みかそれ以上に道路の損壊が深刻な印象を受ける。又 これまでに例をみなかった執拗に続く余震の多さも、被災各位の心理面や救難活動に影を落としている事だろう。
立憲民主党などの指摘では、熊本震災時には 10000人超の自衛隊部隊の速やかな出動があった由だが、その理由としては 熊本地方近くに自衛隊の大規模部隊が駐屯し、前述規模の速やかな出動が可能だった事による様だ。
それに比べ今回震災は、多数に上る主要道路損壊により 復旧に要する大型重機の現場接近が容易にできず、これが復旧遅れの一因ともなっている様だ。つい昨日か一昨日、自衛隊がホバー・クラフトなどをも動員して 大型重機の海からの揚陸を図る光景は象徴的といえるのではないか。
予算予備費からの 40億円余りの当面の救難費用にしても「少ないのでは?」との疑念もある様だが、これにしても あくまで当初の費用分であり、状況によっては必要に応じての積み増しもあり得よう。拙者は決して 震災救援に取組む岸田政権を全面支持する訳ではないが、野党側の批判も追及も 一応でも現場側や実務側の実情を調べた上での表明にすべきだろう。
思い返せば、熊本震災に伴う自衛隊の大規模出動は 第二次安倍政権時ではなかったか。「その時並みに動かせ」と要求するなら、立憲民主は終始目の敵にしていた安倍政権の震災救援策を容認した事になる。
「アベ政治を許さない」と息巻いていた糾弾姿勢と明らかに矛盾の「ダブスタ」にならないか。事実ともなれば、立憲民主党の信頼性は 更に低下して「地に堕ちる」線もありだが。
とに角、被災各自治体とも連携の自衛隊救難活動は 相当に地元の被災状況など実情も汲んだ上での計画に基づいて行われているはずだ。その所も留意の上、まずは我々も静かに見守る位の姿勢が必要ではないか。むしろその方が、被災各位や日本及び日本人の利益にも資すると愚考する者だが。
今回画像は、富山市内の基地を拠点に 関西と北日本を結ぶ日本海縦貫線を主戦場とする JR貨物の主力電機機関車の一つ、EF510型機の当地愛知周辺での活動ぶりを。主に交流電化路線向けの赤基調外装が多いが、一部に以前首都圏と北海道を結んだ長距離夜行特急向けの青基調、銀基調の車両もありまして。