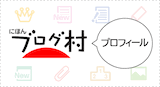8月27日 水場への道に並んで咲いていた ダイモンジソウ。
同じ花のように見えるが右の花と左の花には違いがある。
花弁の形状 左の花には鋸歯のような切れ込みがあるが 右の花にはそれが無い。
葯の色 左の花は黄色 右の花は赤。
昔 調べたときには 左は キレベンダイモンジソウ 右の花は ミヤマダイモンジソウ だった。
今 Yリストで調べると キレベン・・・は該当無し ミヤマ・・・は只の ダイモンジソウ だ。
ダイモンジソウ の咲く頃は稜線の草原では 高山蝶の ベニヒカゲ が目立つ季節だ。
人なつっこい・・と表現されることもあるこの蝶は汗の香に寄ってくる。
蝶の姿を見つけカメラに一脚を取り付けようとしたら・・・。
汗臭いから・・ jokichi の履いているゴム長にも。
毎年観察していた ベニヒカゲ だがこの日は変わった個体の何頭かに出会った。
後翅の裏側に太い白線がある蝶が笹の葉で休んでいた。
イワショウブ に訪れたこの蝶にも白い帯が。
蝶のハイアマチュアである I 氏にこの話をしたらすぐ調べて教えてくれた。
「ベニヒカゲ の♀ は秋になると白い帯があらわれる・・」と。
それにしても13年も観察して気付かなかったのに 14年目に気付くとは・・・・・。
今更ながら 自然の奥深さを知らされた一件でした。
二週間も前の事でしたが・・・・・。
モミジカラマツ の葉陰の ヒメミヤマカラマツ を撮っていたときの事。
足元に何やら小さな紅いものが見えた。
ハクサンコザクラ の花ガラかな・・・と思ったが
老眼鏡をかけ直して良く見ると 初めて見る ラン科の花だ。
花を正面から拡大。
横顔も。上部の花は虫害?で無くなっているようだ。
名前も分からなかったこの花。帰宅後調べてみると ニョホウチドリ のようだ。
ニョホウチドリ は環境省のレッドデータブックでは 準絶滅危惧種 に指定されている。
だが 新潟県のレッドデータブックには記載が無い。
と言うことは新潟県では公式の生息記録が無いのではないだろうか・・・・・。
とすれば これは大発見なのかもしれない。
たくさんの花を見事に咲かせた ミヤマホツツジ をガードするかのように ミヤマウイキョウ が咲いていた。
ミヤマホツツジ の花弁は三枚 雌蘂はクルリと上に向いて曲がる。
ミヤマウイキョウ を拡大すると小さな蠅が。
草原に咲き残っていた キンコウカ。
水場への道に咲いていた イワオトギリ。
登山道では盛りを過ぎた アキノキリンソウ。
スゲの葉をかき分けて顔を出した エゾシオガマ はまだ新鮮だ。
雪融けの遅い場所では イワイチョウ が咲き残っている。
まもなく黄葉して 銀杏 の様な葉色になる頃なのに・・・。
その白い花の花弁は 長雨が続くと透明になる。
数年に一度の開花年だった コバイケイソウ は花期を終え葉は黄色く色づき始めたが・・。
所によっては まだ 咲き残っている株もある。