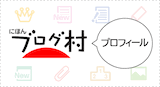里山から高山までの尾根筋に見られる アカミノイヌツゲ は名前の通り丸くて赤い実がかわいい常緑の灌木だ。
樹形は湿地を好む ハイイヌツゲ そっくりで実がついていないとどっちなのか判断しにくい。
葉の鋸歯の僅かの違いで区別はつくのだが生育条件等での個体差もあり判断の難しい樹だ。
アカミノイヌツゲ も ハイイヌツゲ も「雌雄異株」と図鑑等には記載されている。
フィールドで観察する限りではその通りだと理解していた。
正確には最近までそう理解していた。両性花と思われる花を着ける株に出会って疑問を持つようになった。
三十数年前 アカミノイヌツゲ の株の下に芽生えた長さ4cm程の実生苗を見つけて一本だけ採取した。
その時点では雌雄異株であることを知らず 赤い実を期待して鉢植えで大事に育てたが開花にはいたらなかった。
業を煮やして鉢から出して池畔に地植えしてからもすでに十数年が経過した。
昨年からその アカミノイヌツゲ が実を着け始めた。そして今年もいくつかの実を着けた。
昨年は開花を期待していなかったから撮りもしなかったが今年は撮っておいた。(5月30日)
ピンボケ写真だが拡大してみると子房ははっきり分かるし柱頭がぬれているようにも見える。
結実したんだから雌花であろうが 雄蕊もある。花粉こそ確認できないが5本の雄蕊には葯もみえる。
jokichi の池畔から アカミノイヌツゲ の自生地までは直線距離で3kmは離れている。
そこから花粉が供給されたと考えるよりこの花を両性花と考えた方が自然のようだ。
自生地の生育条件に比べると保護されている池畔は格段に好条件下で生育できる。
充分な栄養は本来は眠っている筈の雄蕊も目覚めさせて両性花になったのではないだろうか。
そんなことを考えながら尾根に咲く アカミノイヌツゲ の写真を探してみた。
標高1900mの尾根に咲く アカミノイヌツゲ です。(2013年7月21日)
この花も池畔の花と同様に 5本の雄蕊もそれぞれの葯も確認できます。
となると アカミノイヌツゲ には雌雄異株のものと雌雄同株のものの二種類があるのだろうか。
いままであまり気にしていなかったことだが来春からはもっと アカミノイヌツゲ にこだわってみよう。