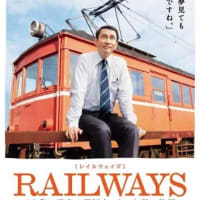中山道は東海道と共に江戸時代の五街道(甲州道・奥州道・日光道)であるが、その前身を東山道とも呼んで古代から中世にかけて西国と東国を結ぶ重要な街道であった。温暖な太平洋岸に面していたために次第に整備され始めた東海道に対し、東山道はしばらくは裏道的な存在として生きてきた。やがて、戦国時代に入り、群雄割拠の時代には小田原北条氏が倉賀野・高崎・板鼻・安中・松井田・坂本の六宿を創設、また下諏訪・塩尻・洗馬・贄川・奈良井・薮原・福島の七宿は武田氏が人馬継立(旅行者は各宿場の人足会所・馬会所で宿場ごとに馬や人足を雇いながら旅行した。東海道では五十三ヶ所の宿駅でこうした継立をしたので「東海道五十三次」と呼ばれたのである)を行っているなど、東山道から中山道への移行期にはすでに宿駅が設けられ始めていた。さてこうして発展した中山道六十九次は、東海道とともに江戸と京を結ぶ重要幹線として生き続けた。現代の地名なら東京日本橋を起点に大宮・熊谷・軽井沢・和田峠・下諏訪・塩尻・上松・妻籠・馬籠・中津川・鵜沼・関が原・彦根・大津を経由して京都三条大橋が終点である。
今須宿(いますじゅく)は中山道の五十九番目の宿場で岐阜県不破郡関が原町と昔、長久寺という七堂伽藍の立派なお寺があったところからその寺名が名となっている滋賀県米原市長久寺の境が、寝物語の里である。昔から国境(今の県境)とされてきた幅五十センチばかりの溝川をはさんで美濃側に両国屋、近江側に亀屋という宿が軒を連ねていた。中山道を行き来する旅人たちが、それぞれの宿屋に休みながら、寝床の布団に包まり、壁越しに隣国の宿屋の人と話し合えたというのが寝物語の里のいわれだとされている。今から700年ほど前、源義経が兄の頼朝と仲が悪くなり、奥州へ逃げていくとき、義経をしたって、家臣の江田源蔵が後を追いかけてきた。源蔵は、泊まった宿の主人に、源平合戦での義経のはなばなしい働きぶりを話した。偶然、国境をはさんで近江側に宿を取っていた義経の妻の静御前がその声を聞き、再会を喜び合い、二人はうれしさのあまり、寝ることも忘れて壁ごしに話をして夜を明かしたという伝説がある。
通常の国境は人の住まない山の尾根や大河の真中とか海である。関が原は養老山系と伊吹山系の狭間で交通の要衝であったから、山中に宿場が出来た結果、国境が町の中に出来てしまった。県レベルでは境があるが、日本国の視点なら境は無いのである。渡り鳥には国境が無いのと同じである。渡世人の「フーテンの寅」には、国境は無いのである。愛する車寅次郎は東京都民でなくて、日本国民なのである。
今須宿(いますじゅく)は中山道の五十九番目の宿場で岐阜県不破郡関が原町と昔、長久寺という七堂伽藍の立派なお寺があったところからその寺名が名となっている滋賀県米原市長久寺の境が、寝物語の里である。昔から国境(今の県境)とされてきた幅五十センチばかりの溝川をはさんで美濃側に両国屋、近江側に亀屋という宿が軒を連ねていた。中山道を行き来する旅人たちが、それぞれの宿屋に休みながら、寝床の布団に包まり、壁越しに隣国の宿屋の人と話し合えたというのが寝物語の里のいわれだとされている。今から700年ほど前、源義経が兄の頼朝と仲が悪くなり、奥州へ逃げていくとき、義経をしたって、家臣の江田源蔵が後を追いかけてきた。源蔵は、泊まった宿の主人に、源平合戦での義経のはなばなしい働きぶりを話した。偶然、国境をはさんで近江側に宿を取っていた義経の妻の静御前がその声を聞き、再会を喜び合い、二人はうれしさのあまり、寝ることも忘れて壁ごしに話をして夜を明かしたという伝説がある。
通常の国境は人の住まない山の尾根や大河の真中とか海である。関が原は養老山系と伊吹山系の狭間で交通の要衝であったから、山中に宿場が出来た結果、国境が町の中に出来てしまった。県レベルでは境があるが、日本国の視点なら境は無いのである。渡り鳥には国境が無いのと同じである。渡世人の「フーテンの寅」には、国境は無いのである。愛する車寅次郎は東京都民でなくて、日本国民なのである。