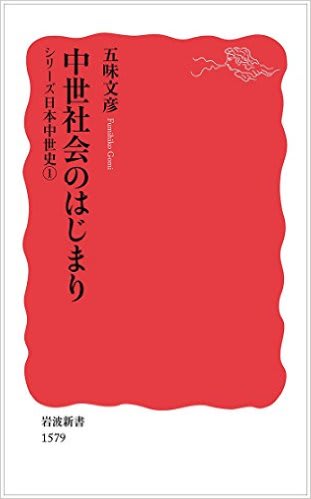
岩波新書の古代史シリーズはたいそう面白かった。少壮の学者が、アジア史の枠組みの中でとらえ直した日本の古代のようすは、通説を覆す論考に充ち満ちていて、たいそうスリリングだった。
翻って本書である。中世の始まりを九世紀末、貞観の大地震のころから説き起こしているので仮に中世の終焉を徳川幕府開府までとしたなら、ぬあんと七百年の出来事を新書四冊にまとめるという荒業である。
本書では室町幕府ができるところまでなので、約四百年余り、登場人物が多く、出来事は綾織りのように絡まり合い、最近とみに老化の激しい私の頭脳では流れを追って行くのがやっとという、誠に情けない読書体験でした。
さりながら、せっかく苦労して読んだので、切れ切れの印象をしたためます。
まず、中世の始まりを摂関政治の開始に置いたのが目新しかった。隋、唐で整備された律令制度が時代を経て日本的に変容しただけではなく、それこそが中世の始まりとするのは、古代的な権力権威が、求心力を失う過程でもある。とそのことに気が付いた。
やがて、朝廷のコントロールを外れて武力を行使するものが現れ成長する長い時間は、なるほど、古代の社会が次第に景色を替えていくことでもあった。
文化もまたしかり。、国風文化と呼ばれるものは、大陸から取り入れた文化と土着の文化が融合し、我が国独特の文化の別名でもある。
ふんふん、分かった。鎌倉幕府ができたのはその最終段階。そう著者は定義づけているのね。
鎌倉幕府ができて、朝廷は政治的実権を全く失ったわけではないけれど、諸制度を整備し、法令に基づいて政治をするののはやがて、全国に広まってと行く。
二重政権と言うのとも違うのかな。阿仏尼の「十六夜日記」は、土地の訴訟で鎌倉へ出かける女性の日記。方丈記の鴨長明も神官の職を安堵してもらうため鎌倉へ下向しているし、京都文化を体現しているような吉田兼好でさえ、鎌倉へ出かけている。
想像しているより、ずっと鎌倉の権力は強かったのかもしれない。それは生産手段としての土地の上に乗る権力構造を整合性のある法律で秩序立てていく、地道な実務の道である。
京都からは荒夷と見下される武士政権が、実はしっかり実力を蓄えている。田舎者の私はそのあたりがとても痛快でした。
承久の変辺りからはハイスピードで話が展開し、あれよあれよと言う間に足利尊氏まで出てくるので、しっかり読まないと振りとばされそうではあるけれど。
後鳥羽院と定家の歌風の違いとか、武士も職人も芸能に携わる人も、天皇さえ、身体性の自覚と獲得という視点で括るのはちょっとわかりにくかった。
とは言え、なかなか面白く読みました。シリーズ次作も楽しみです。

こちらずいぶん前、福山市鞆の浦のひな祭りで。
うつぶせ寝の赤ちゃん。




















