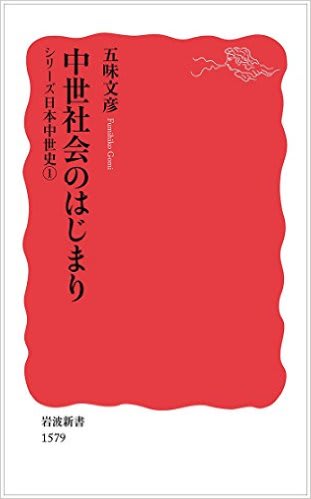大学を出で実家のある群馬県に戻り、親戚の神社を手伝いながら、夏は高原野菜の取り入れをする主人公宇佐川静生。
東京から移住してきた木工職人、鹿谷の工房に行くうち、そこに集まる人と言葉を交わすようになる。
高校時代の後輩の女の子は名古屋から帰っているし、温泉のアルバイトで知り合った女性とはいい感じで付き合っている。
深くかかわらず、かといって拒否し合うでもない人間関係が淡々と描かれ、今の時代の空気感というのがよく出ていると思った。
群馬県の地名、道路がよく出てくる。著者は運転上手らしく、会社勤めの時はカローラの営業車に乗っていたと何かのエッセィで読んだけど、この地方の人なら、小説の舞台がくっきりと浮かび上がってより楽しめると思う。
淡々と話が進むように見えて、やがて工房は不審火を出し、部室のようにして集まっていた人たちも散り散りになって行く。恋人と思っていた女性は婚活して、より条件のいい人にあっさり乗り移る。みんな薄情だなあ・・・・と私は思う。
宇佐川は家に帰る気になれずにドライブの途中、高校生のヒッチハイカーを拾い、白河インターまで送って行く。
田舎者ならそれでいいじゃないか、自分を自分が認めずにどうやって前に進んでいけるんだ・・・字にすると固い決意のようになるけれど、小説の中ではもっとソフトな言い方で、主人公の未来が予測される。
一人の心の襞にしっかりと寄り添い、生き方をたどって行く。一見地味に見えるこの作品は、読む人の心を照射し、新たな気付きを与えてくれる。読んで損はなかったです。