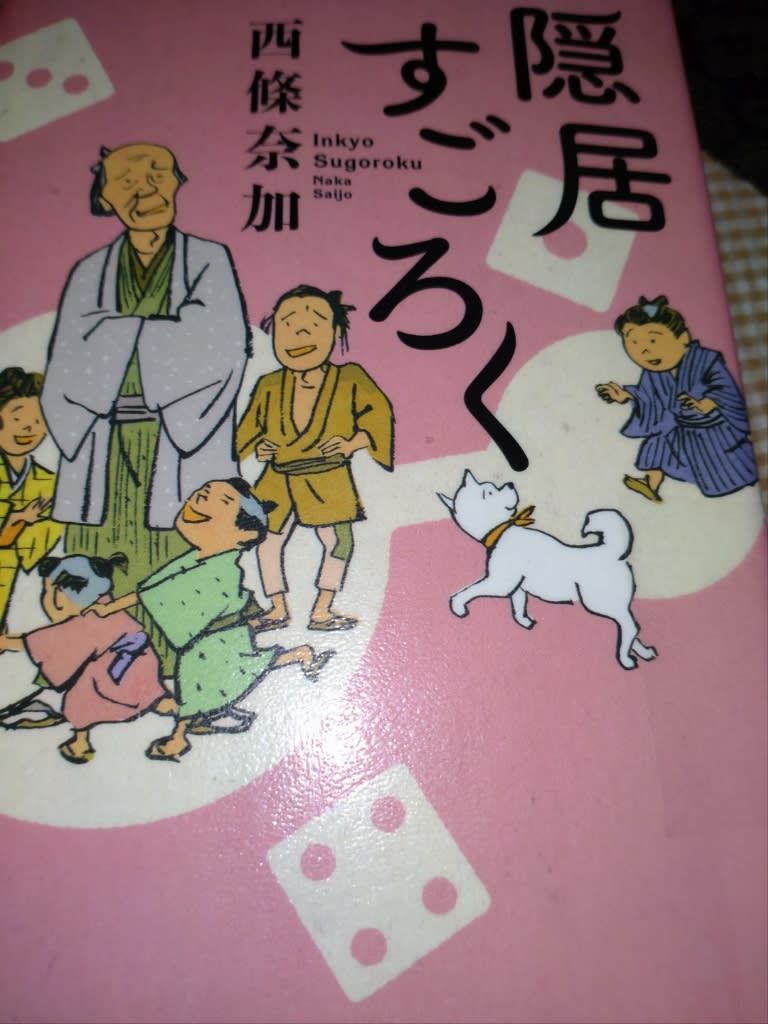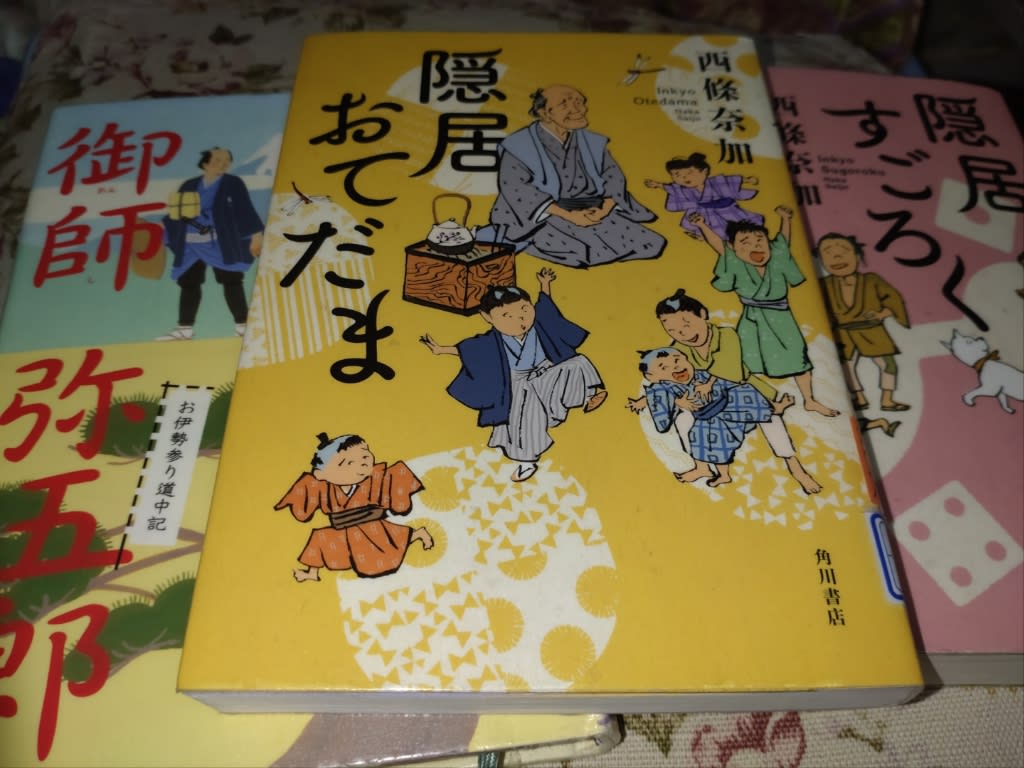室温は、
朝から曇り空で、蒸し暑い日であったが、日差しがないだけで、暑さを感じなかった。
とみよしクリニック皮膚科
9:39のバスでとみよしクリニックに行くと、意外に空いていたのか、早めに名前を呼ばれる。
いつものように男の医師で、優しく足の裏のイボを削り取り、液体窒素を掛けて、痛いというと直ぐに止めてくれる。
小さい方のイボは殆ど治っているが、大きい方は年月が掛かって大きくなっているだけになかなかしぶとい。
まあ気長にキレイになるまで通院しようかな。
丁度11:07のバスに間に合って、午前中に家に到着することができた。
午後からは、西條奈加さんの「六つの村を越えて髭をなびかせる者」をやっと読み上げることができた。
田沼意次の時代に、音羽塾に算術に長けた出羽出身の青年が、蝦夷地見分隊の竿取として、名を最上徳内と改めて、随行することになった。
当時は松前藩が蝦夷地の一部を統括していたが、商人と結託して、原住民のアイヌをこき使い、暴利を我が物にしていた。
やっと松前藩に到着したが、御用船がなかなか来ないので、徳内は松前藩内を歩き、アイヌの姿を見つけて、声を掛けて、たばこ、米、酒を交換しながら、しばらくの間にアイヌ語を少しづつ覚えていった。
2ヶ月後、見分隊は東と西と留守居役の3組に分かれて、アッケシにむかう。
コタンを探しに出掛けると、少年フルウに出会い、トクとフルウと呼ば合う仲となり、
毎日のように松前藩の小者に内緒に、コタンに通うようになり、アイヌ語を覚え、フルウに和語を教えるようになる。
徳内一人で陸路で、フルウやコタンのアイヌに助けられながら、クナシリに向かう。
東の見分隊の様子を見に行くと、何と5人が霧の病に罹り死んでいた。
将軍家治が亡くなり、田沼意次の権威がなくなると、松平定信はことごとく蝦夷地見分隊を解散させ、蝦夷地見分隊の成果を潰し、見分隊の役職をことごとく左遷させる暴挙に出る。
上役である青島は徳内と共に捕らえられ、徳内は音羽塾の面々に助けられ、釈放されるが、青島は獄死してしまう。
しかし、時代が代わり、徳内の蝦夷地での知識を活かすために再び蝦夷地に舞い戻ることが出来た。
西條奈加さんの時代小説をずっと読んできたが、題名のように蝦夷地を「六つの村を越えて髭をなびかせる者」が探検しながら、渡り歩いた歴史的実在する人物を描いた時代小説は異色であった。
今までとは違った時代小説を楽しく読めました。
今日の万歩計は、6,165歩でした。