このところ秋雨前線が居座っていたのですが、今日は久しぶりのいい天気 。
。
10時から中電ホールで名証主催の株式投資サマーセミナーがあったので行ってきました。

10時ぎりぎりに入ったのですが、会場はほぼ満員。時間が過ぎても入場者が結構いて席が埋まっていきます。
それにしても高齢者が多い。女性も結構いて会場はじいさん・ばあさんばかり…
第1部は2社の企業説明。
ちなみにこういった名証主催のセミナーは予定が許せば参加しているのですが、ここで取り上げられる会社は名証としてもそれなりに将来性に自信がある会社だと思います。買っておいて損はないと思いますし、以前説明を聞いた何社かは買って今のところ現実に儲かっています。
最初の会社は「ダイコク電機」です。
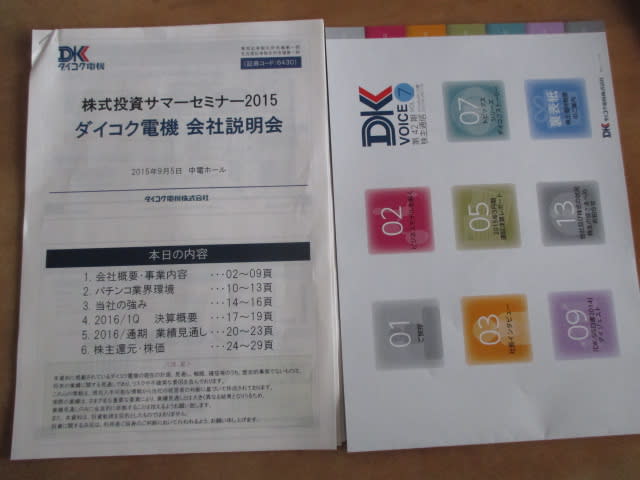
柏森社長自らが説明します。社長は2代目の御曹司。あまり大勢の人の前で話すことには慣れていないのかパワーポイントの使い方もイマイチでした。でも社長自らが汗をかきながら一生懸命話す姿は好感が持てます。

計画は結構強気ですが、それというのもパチンコ会社向け会員制情報システムサービスが伸びていて、この売り上げ総利益率は80%を超えているから。ここでの利益を研究開発投資に回せるので業界第1位の有利な位置を守れるとか。
パチンコ業界自体はマックス4.5兆から3兆円に市場規模が落ちているのですが、ここから4兆円に回復するという予想。アベノミクスもあってデフレを脱却できればサラリーマンのお小遣いも上がるのではという希望的観測。ちなみにサラリーマンのお小遣いは名目でバブル期のマックス7万円台から今は3万円台とか。
配当もそこそこですし、今年からポイント制の株主優待を行うそうで魅力が増してきているのでこれはお買い得…
でもパチンコ業界の行方は法規制にも左右されることもあって、そこは不透明な部分ですし、ためらいがありますね。
続いての会社は「三菱重工」
さすがにここは社長が来ることなく経営・財務企画部IRグループ長が説明。
さすがに能弁でさわやかに説明していきます。
でも能弁に話しても担当者だとどうしても調子に乗ってしゃべっていると思ってしまい、たぶん40代ぐらいかと見えるのですがすでにリタイアした身としては生意気に感じてしまいます。

三菱重工としてはこの程度の説明会に取締役が出ることもないと思っているのでしょう。
三菱重工は日本を代表する企業ですし、その事業範囲も多岐にわたっています。ですから概括として話すだけでも結構時間がかかります。もう少しポイントを絞ってみたらどうでしょうか。未だと本当にМRJは飛ぶのかとか原子力をどうするのかということはみんな関心あると思うのですが当然ながら淡々とした説明で踏み込んだ説明はありませんでした。
この会社はもう少し様子見でしょう。
第2部は株式講演会。
この人は全く知らなかったのですが、業界では有名?SBI証券のシニアマーケットアナリストの藤本誠之さんです。

とにかく声の大きな明るい人です。
開口一番、株をやるなら日経新聞と会社四季報ぐらいは買って読みましょうと。どちらも買っていない私はどうもすいません。

ただしそれはみんな読んでいるので、新聞に出た好材料はすでに株価に織り込み済み、悪材料は出尽くしと考えて対応すべし。もっとも売り先行でやるには信用取引しないといけないんですけどね。
ちなみに今アナリストという人が分析しているのは上場3500社のうち500社くらい。個別企業として好業績の割に株価があがらないのはアナリスト予想がないからとか。わかったようなわからないような。
今は11月のJP上場に備えて上値が遅いのでせいぜい19000円から17000円のレンジ、というか国策として何としても高値上場したいので時価総額の高いトヨタとか金融株は資金手当てのために売られる?
無事上場した11月過ぎたら業績によってあがっていくとか。となると年末2万円超えも…
でも中国経済はどうなるかだし、アメリカの利上げの影響はといろいろ考えないと…しばらくは様子見?
 。
。10時から中電ホールで名証主催の株式投資サマーセミナーがあったので行ってきました。

10時ぎりぎりに入ったのですが、会場はほぼ満員。時間が過ぎても入場者が結構いて席が埋まっていきます。
それにしても高齢者が多い。女性も結構いて会場はじいさん・ばあさんばかり…
第1部は2社の企業説明。
ちなみにこういった名証主催のセミナーは予定が許せば参加しているのですが、ここで取り上げられる会社は名証としてもそれなりに将来性に自信がある会社だと思います。買っておいて損はないと思いますし、以前説明を聞いた何社かは買って今のところ現実に儲かっています。
最初の会社は「ダイコク電機」です。
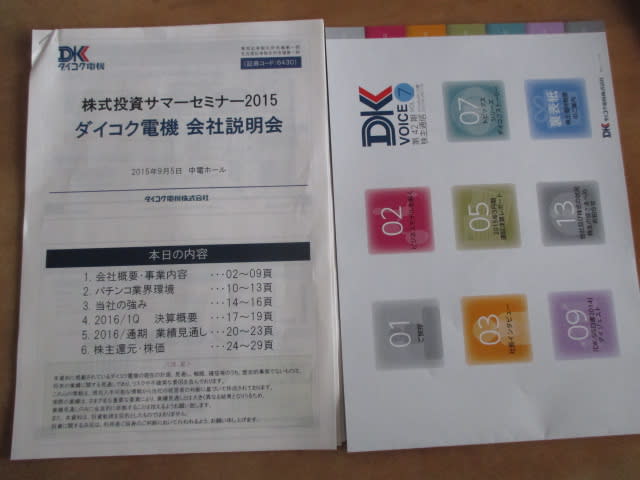
柏森社長自らが説明します。社長は2代目の御曹司。あまり大勢の人の前で話すことには慣れていないのかパワーポイントの使い方もイマイチでした。でも社長自らが汗をかきながら一生懸命話す姿は好感が持てます。

計画は結構強気ですが、それというのもパチンコ会社向け会員制情報システムサービスが伸びていて、この売り上げ総利益率は80%を超えているから。ここでの利益を研究開発投資に回せるので業界第1位の有利な位置を守れるとか。
パチンコ業界自体はマックス4.5兆から3兆円に市場規模が落ちているのですが、ここから4兆円に回復するという予想。アベノミクスもあってデフレを脱却できればサラリーマンのお小遣いも上がるのではという希望的観測。ちなみにサラリーマンのお小遣いは名目でバブル期のマックス7万円台から今は3万円台とか。
配当もそこそこですし、今年からポイント制の株主優待を行うそうで魅力が増してきているのでこれはお買い得…
でもパチンコ業界の行方は法規制にも左右されることもあって、そこは不透明な部分ですし、ためらいがありますね。
続いての会社は「三菱重工」
さすがにここは社長が来ることなく経営・財務企画部IRグループ長が説明。
さすがに能弁でさわやかに説明していきます。
でも能弁に話しても担当者だとどうしても調子に乗ってしゃべっていると思ってしまい、たぶん40代ぐらいかと見えるのですがすでにリタイアした身としては生意気に感じてしまいます。

三菱重工としてはこの程度の説明会に取締役が出ることもないと思っているのでしょう。
三菱重工は日本を代表する企業ですし、その事業範囲も多岐にわたっています。ですから概括として話すだけでも結構時間がかかります。もう少しポイントを絞ってみたらどうでしょうか。未だと本当にМRJは飛ぶのかとか原子力をどうするのかということはみんな関心あると思うのですが当然ながら淡々とした説明で踏み込んだ説明はありませんでした。
この会社はもう少し様子見でしょう。
第2部は株式講演会。
この人は全く知らなかったのですが、業界では有名?SBI証券のシニアマーケットアナリストの藤本誠之さんです。

とにかく声の大きな明るい人です。
開口一番、株をやるなら日経新聞と会社四季報ぐらいは買って読みましょうと。どちらも買っていない私はどうもすいません。

ただしそれはみんな読んでいるので、新聞に出た好材料はすでに株価に織り込み済み、悪材料は出尽くしと考えて対応すべし。もっとも売り先行でやるには信用取引しないといけないんですけどね。
ちなみに今アナリストという人が分析しているのは上場3500社のうち500社くらい。個別企業として好業績の割に株価があがらないのはアナリスト予想がないからとか。わかったようなわからないような。
今は11月のJP上場に備えて上値が遅いのでせいぜい19000円から17000円のレンジ、というか国策として何としても高値上場したいので時価総額の高いトヨタとか金融株は資金手当てのために売られる?
無事上場した11月過ぎたら業績によってあがっていくとか。となると年末2万円超えも…
でも中国経済はどうなるかだし、アメリカの利上げの影響はといろいろ考えないと…しばらくは様子見?

















