
恥ずかしながらウィーン国立劇場には行ったのだが、よく覚えていない。演目は「眠れる森の美女」。奮発してボックス席をとったのだが、手前のボックス席の男性がかなり身を乗り出していて、こちら側からは舞台がよく見えなかったので、注意しようと思ったがドイツ語もできないし、泣いた覚えだけがある。そして幕前のシャンペンも高かった。
そのウィーン国立劇場バレエ団のおかぶ「こうもり」がやってきた。もともとはオペレッタ作品が本家だそうであるが、バレエになっても単純明快、他愛もない喜劇であることに変わりはない。倦怠期の夫婦は5人の子どもに恵まれ、幸せなファミリーを演じているが、夫ヨハンは妻ベラのベッドを抜け出し、夜な夜なこうもりとなって華やかな世界へ。ヨハンの愛を取り戻すべく共通の友人ウルリック(実はベラを愛している)のけしかけで、美しく変身したベラは、夫の入れ込む酒場で他の女性らを出し抜いて男性客を魅了する。ヨハンもベラとは知らずに求愛するが。
こうもりに変身するための羽をベラに切り取られたヨハンは、妻の尻に敷かれる哀れな夫になり、家族の平穏は保たれ、めでたし、めでたし。はたしてウルリックはそれを望んでいたのか難しいところだが、彼とて、ベラの家族の崩壊を望んではいないだろう。貴族社会はあくまで建前的にはすべて平穏無事、うまくいっていことが前提。ウルリックにとっては、ヨハンとベラがうまくいっていること、すなわち、ベラが幸せであることは望んだことだから。
ストーリーはさておき、ウィーン国立劇場バレエ団のパフォーマンスはどうか。同団のプリンシパルもソリストもロシアや東欧出身が多い。概して大柄である。今回西宮公演のベラ役はマリア・ヤコヴレワ。貞淑な妻、善き母から妖艶なレディ、悩殺女(悪女)に変身する様は、ジゼルや白鳥の湖などと同じく、両極端・好対照な女性像を演じる恰好の題材で、ダンサーの実力が問われる難しい役柄。貫録十分のヤコヴレワは長いスカートの主婦姿から太もも露わのピスチェのいでたちへ。そのピスチェ姿を覆っていたのはこうもりを想起させる黒いマント。悪女のマントにかかれば子どもじみたヨハンなどひとたまりもない。であるが、ヤコヴレワも見れば、ロシアはマリンスキー出身。決して小柄とは言えない迫力が、大きな衣を脱いだところで明らかになり、この魔女をどう遇せばというところで、やはり東欧はスロバキア出身のヨハン役、ロマン・ラツィクがこれまたかなりの体躯。ヤコヴレワをひょいとのリフトのシーンが幾度もあるが、貞淑、妖艶、蠱惑、欲情を自在に変化(へんげ)するベラに合わせたラツィクのパフォーマンスもとても高い。
そして、身体能力の高さを見せつけたのがギャルソンを演じた面々。さすがに難度の高い早いダンスの後は肩で息をしていたが、今回の演目そのものが、貴族が出入りする酒場や舞踏会を中心になされていることもあり、衣装が通常のバレエより重たく、複雑であったのにそれをものともせず踊り切るのはすごい。
楽しく、変化に富んだ演目の根底にあるのは観る者を「楽しませたい」との基本に徹した先ごろ亡くなったローラン・プティの振り付けによるところが大きいという。本家のオペレッタのエッセンスを欠かすことなく、バレエというサイレンスの世界に「粋」と「洒脱」を練りこんだプティの振り付けは、座ったままのボディラングエッジですべてを表現してみせる落語にも擬せられる。
先にあげたジゼルや白鳥といった演目は、有名ではあるがダンサーの実力を測り窺うにはそれなりの経験と審美眼がいるという。オペレッタがオペラという形式主義、重厚な芸術から庶民のものとして尊ばれるならば、オペレッタを起源とする本作も軽く、分かりやすいものがいい。その素人好みを満足、満喫させるのがウィーン国立劇場の「こうもり」である。
そのウィーン国立劇場バレエ団のおかぶ「こうもり」がやってきた。もともとはオペレッタ作品が本家だそうであるが、バレエになっても単純明快、他愛もない喜劇であることに変わりはない。倦怠期の夫婦は5人の子どもに恵まれ、幸せなファミリーを演じているが、夫ヨハンは妻ベラのベッドを抜け出し、夜な夜なこうもりとなって華やかな世界へ。ヨハンの愛を取り戻すべく共通の友人ウルリック(実はベラを愛している)のけしかけで、美しく変身したベラは、夫の入れ込む酒場で他の女性らを出し抜いて男性客を魅了する。ヨハンもベラとは知らずに求愛するが。
こうもりに変身するための羽をベラに切り取られたヨハンは、妻の尻に敷かれる哀れな夫になり、家族の平穏は保たれ、めでたし、めでたし。はたしてウルリックはそれを望んでいたのか難しいところだが、彼とて、ベラの家族の崩壊を望んではいないだろう。貴族社会はあくまで建前的にはすべて平穏無事、うまくいっていことが前提。ウルリックにとっては、ヨハンとベラがうまくいっていること、すなわち、ベラが幸せであることは望んだことだから。
ストーリーはさておき、ウィーン国立劇場バレエ団のパフォーマンスはどうか。同団のプリンシパルもソリストもロシアや東欧出身が多い。概して大柄である。今回西宮公演のベラ役はマリア・ヤコヴレワ。貞淑な妻、善き母から妖艶なレディ、悩殺女(悪女)に変身する様は、ジゼルや白鳥の湖などと同じく、両極端・好対照な女性像を演じる恰好の題材で、ダンサーの実力が問われる難しい役柄。貫録十分のヤコヴレワは長いスカートの主婦姿から太もも露わのピスチェのいでたちへ。そのピスチェ姿を覆っていたのはこうもりを想起させる黒いマント。悪女のマントにかかれば子どもじみたヨハンなどひとたまりもない。であるが、ヤコヴレワも見れば、ロシアはマリンスキー出身。決して小柄とは言えない迫力が、大きな衣を脱いだところで明らかになり、この魔女をどう遇せばというところで、やはり東欧はスロバキア出身のヨハン役、ロマン・ラツィクがこれまたかなりの体躯。ヤコヴレワをひょいとのリフトのシーンが幾度もあるが、貞淑、妖艶、蠱惑、欲情を自在に変化(へんげ)するベラに合わせたラツィクのパフォーマンスもとても高い。
そして、身体能力の高さを見せつけたのがギャルソンを演じた面々。さすがに難度の高い早いダンスの後は肩で息をしていたが、今回の演目そのものが、貴族が出入りする酒場や舞踏会を中心になされていることもあり、衣装が通常のバレエより重たく、複雑であったのにそれをものともせず踊り切るのはすごい。
楽しく、変化に富んだ演目の根底にあるのは観る者を「楽しませたい」との基本に徹した先ごろ亡くなったローラン・プティの振り付けによるところが大きいという。本家のオペレッタのエッセンスを欠かすことなく、バレエというサイレンスの世界に「粋」と「洒脱」を練りこんだプティの振り付けは、座ったままのボディラングエッジですべてを表現してみせる落語にも擬せられる。
先にあげたジゼルや白鳥といった演目は、有名ではあるがダンサーの実力を測り窺うにはそれなりの経験と審美眼がいるという。オペレッタがオペラという形式主義、重厚な芸術から庶民のものとして尊ばれるならば、オペレッタを起源とする本作も軽く、分かりやすいものがいい。その素人好みを満足、満喫させるのがウィーン国立劇場の「こうもり」である。











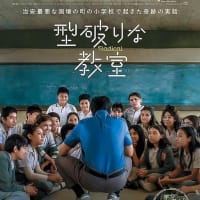













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます