
印象派の展覧会であるとか、フェルメールのそれであるとかに観客がわっと押し寄せるのは見慣れた光景であるが、ロシア美術となるとどうか。筆者の含めて多くの美術好きも詳しくはないのではないか。であるからかもしれない。本展はBunkamura ザ・ミュージアム以外は山形、岡山、愛媛とわりと地方の美術館ばかりの巡回展である。ところがこれがなかなかの見応えである。
「ロマンティック・ロシア」。なぜロマンティックなのか。それは膨大なトレチャコフ美術館の収蔵品の中から帝政ロシア末期の「移動派」を中心とした風景画、肖像画、風俗画にスポットを当てて集中的に集めているからだ。ロシア美術、それもロシア美術だけを集めるトレチャコフ美術館であればビザンツ美術の名品も展示されていて当然であろうが、今回は上記に絞っているからだ。狭い島国の日本 ―と言っても、行ったことのない土地が圧倒的に多いことから十分に広いと感じてはいるがー からすればあまりにも広大なロシアの大地を描くとはどういうことか。長い冬のイメージで春や夏などあるのか、といった偏見を超えて、彼らは描き続けた。それはおそらく狭いアカデミズムの一側面、と彼らが見なした、のとは違うロシアの自然、環境、人々の営みをリアリズムの視点で描きたかったからに違いない。イワン・ニコラエヴィチ・クラムスコイ、イワン・イワーノヴィチ・シーシキン、イサーク・イリイチ・レヴィタン、イリヤ・エフィーモヴィチ・レーピンといった「移動派」の画家らは、革命前後を通じてロシア画壇の重鎮を占めることになるが、それ以前はアカデミーに反発するかのごとく各地を移動展示せざるを得なかったのである。恥ずかしながら、肖像画の名手レーピン以外の名はよく知らなかったのだが、そこに描かれている風景画は冬の厳しさを迎えるまでの春や夏、秋の柔らかで静寂な断面を言わばフォトジェニックに切り取ったように見る者を安寧の心持ちに誘う。
本展の目玉であるクラムスコイの「月明かりの夜」(1880)と「忘れえぬ女(ひと)」(1883)は、モデルが変更になったり(月明かり)、不明であったり(忘れえぬ。ちなみに本作の原題はUnknown Lady)と必ずしもこの人の肖像画という扱いではないが、その魅力が減じることはない。クラムスコイはトルストイら著名人の肖像を数多く描いている画家であるが、この2点についてはもちろん著名人を描いたものではないし、「月明かり」については何か妖精でも棲みそうな空間にたゆたう、現実には存在しない女性を、一方「忘れえぬ」では観る者を逆にきりりと見据える女性は西洋画の伝統であるファム・ファタルさえ思わせる。
「移動派」が結成されたのが1870年。ペテルブルク美術アカデミーを追放された学生であったクラムスコイらが社会主義思想に影響を受け、リアリズム作品を各地で巡回したのち、革命後はソヴィエト社会主義リアリズムの権威化されるが、画家の表現形式と現実政治が一体化した成功例と言える。しかし、美術は現実世界の矛盾を追及したり、より新しい発想で現実を変えていこうとする表現者の試みの発露でもあるはずだ。そうすると「権威化」された時点で、「移動派」の絵を純粋に美しい、素晴らしいと思い込んでいたものが途端に有名作品になった“いわく”を粗探ししたくなる感性は邪魔者だろうか。
ところで筆者はトレチャコフ美術館に一度だけ行ったことがあるが、それまでの旅程の疲れとあまりにも広いので(併設の現代美術館もすごい)クタクタになってよく覚えていないのが情けない。












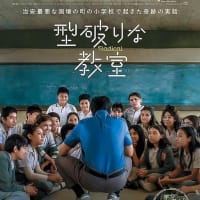












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます