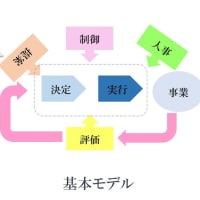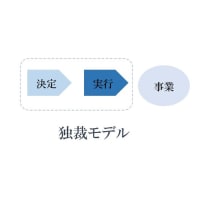本日1月12日の讀賣新聞オンラインには、大変興味深い寄稿文が掲載されていました。寄稿文と言うよりも、今日まで全世界に多大なる影響を与えてきた一グローバリストの告白と言ってもよいかも知れません。何故ならば、同グローバリストは、グローバリズムというものの正体を自らの言葉で語っているからです。
あるグローバリストとは、世界経済フォーラムの創設者として知られるクラウス・シュワブ会長です。今年もスイスでは同会議が主催する年次総会(通称ダボス会議)が開かれ、フランスのマクロン大統領やアメリカのブリンケン国務大臣の出席が予定されています。グローバリズムへの批判が高まったため、‘ダボス詣で’とも称されたほどの一時期の賑わいはないものの、未だに一定の影響力を保持していることが窺えます。同会議の代表者とも言えるシュワブ会長のことですから、日本国の新聞に寄稿文を寄せた目的は、おそらくグローバリズムへの賛同を得るためであったのでしょう。
しかしながら、何故、会長自らによる宣伝活動が逆効果となってしまったのかと申しますと、寄稿文の内容が、理路整然とした論理的な主張ではなく、一種のファンタジーであったからに他なりません。しかも、ファンタジーであればどこか微笑ましいのですが、その行く先を見据えますと、ディストピアへと言葉巧みに誘っているようにも思えるのです。それでは、同会長の寄稿文には、どのような‘マジック’が仕組まれているのでしょうか。
第一に、同会長は、今日の人類が直面している危機の特徴を「分断の拡大、敵意の高まり、紛争の急増」の三者として表現しています。その上で、根本的な原因を追及すべきとしています。ここまでは、誰もが納得する文章の流れです。ところが、‘根本原因’として同会長が挙げているのは、国家による‘時代遅れの解決策’なのです。言い換えますと、同会長は、真の原因を追及するのではなく、‘根本原因’から発生した問題に対する解決策が‘根本原因’であるとする一種のトートロジーに読者を誘い込むことで、根本原因の探求から逃げてしまっているのです。
こうした逃避的な態度は、おそらく、根本原因を追及すれば、自らに行き着くからなのでしょう。上述した分断、敵意、戦争の多くは、グローバリズムがもたらしてきたからです。例えば、先進国の産業の空洞化による中間層の崩壊、国境を越えたマネーの自由移動による富の偏在と集中、外資や先端技術の導入による中国の軍事大国化、移民の増加による社会的亀裂や対立の激化・・・など枚挙に暇がありません。なお、同会長は、グローバリズムが人類の多くを貧困から救ったとして評価しておりますが、そもそもの貧困の原因は、苛烈な植民地支配であったり、社会・共産主義体制の導入に求められますので、ここにも、根本原因からの逃避という問題が見られます。
第二に、同会長が提示している‘時代に即した解決策’も、首を傾げざるを得ません。同寄稿文では、要約すれば(1)経済のグリーン・デジタル化による雇用創出・購買力の向上、(2)再生エネルギーの拡大による気候変動並びに紛争の解決、(3)AIの人類再生の触媒化、の三者が解決策として提言されているのですが、何れもが説得力に乏しく、ファンタジーの域を出ていないのです。強いて言えば、エネルギー技術の発展が資源争いを原因とした紛争の発生を消滅させる可能性はありますが、何故、提案した解決策が‘望ましい結果’をもたらすのか、その詳細なメカニズムについては空白なのです。
第三に指摘し得るのは、これらの解決方法を実行するのは、グローバル、国家、地域としており、とりわけ、国家に対しては障害物と見なしています。国家の存在に紛争や戦争の原因を押しつけたいのでしょうが、現実を見ますと、大多数の国民が戦争を望まずともこれに引き込まれるのは、グローバルな戦争ビジネスや戦争利権が存在しているからです。今般の能登半島地震のような災害等が発生した場合、責任をもって国民を救助できるのは国家の政府を置いて他にありません。今日の人類が直面している危機とは、国家の統治能力の低下や政治家の‘グローバル化’にあり、むしろ、国民自治の精神を表す民主主義の価値に照らしますと、国家機能の強化の方が問題解決には相応しいとも言えましょう。
そして、極めつけが最後の一文です。「危機に主導される力関係から脱却し、協力と信頼、そして、明るい未来に向けた共通のビジョンを育むには、この歴史的な転換点がもたらす機会を解き放つ、前向きなストーリーを創造しなければならない。」とする一文で結んでいるのですから。告白、あるいは、自白と言えるのは、‘前向きなストーリーの創造’、この一言に尽きます。この一言、グローバリズムとは、人々に夢を抱かせるような物語を創ることで自らが描く世界支配の未来ヴィジョンを実現するための、特定の金融・経済財閥、即ち世界権力とも称される私的団体によるプロパガンダであったことを、図らずも吐露しているように思えるのです。