
ウソをつかないこと、おのれの力量を見極めること、限界を知ること、頃合いをはかること、どれも私の苦手なことです。いやぁ、みんな苦手なんだけど、それぞれ自分の判断で上手にやっているのです。私はそれが面倒で、ぼんやり時間を過ごすことがあります。だから、一つ何かを始めると、ダラダラいつまでもやってしまう。判断することも一つの才能です。
わりと好きなお弟子さんの子路さんに、先生が積極的に声を掛けました。なかなかめずらしいことです。というか、子路さんには先生も気を許してあれこれ話したくなるんでしょう。それは子路さんの魅力です。私はそんな魅力ありますか? 近ごろはみんなから声を掛けられなくなっている気がします。それだけ私全体から放置しておいて欲しいオーラを出しているのかもしれない。
もっとみんなに声を掛けてもらえるオッチャンにならなくてはいけません。私は、積極的なアホーなオッチャンなんですから、抜けているところだらけなんだから、みんなに助けてもらわなくちゃいかんのですから、変なオーラを出さず、みんなに声を掛けてもらえる子路さんを見習わなくては!
そのためには、どうせアホーなのは仕方がないのだから、それをみんなにちゃんとわかってもらうようにしなくちゃいけません。まあ、明日からせいぜい努力しようと思います。

さあ、子路さんに先生がおしえてくださいましたよ。
21【知らざるを知らずと為すこれ( )るなり】……知ったかぶりをせず、知らなければ知らない、知っていれば知っているとはっきりさせる、これが真に「……る」ことだ。やや独断的な性格の弟子の子路を諭した言葉。〈為政〉→禅問答のようですが、先ず自分の無知を認める所から始めようとしたものでしょうか。
先生はどうしてそのようなことを子路さんに話したんでしょう。そっちが気になりますね。とてもありふれた事実のような気がするんですが、とても深遠な気もします。
まさか子路さんが知ったかぶりをする人だったわけではないでしょう。わりとドッチラケの子路さんは、何もかも投げ出してしまうし、思わせぶりとか、知ったかぶりとか、そんなまわりくどいことはしない人だと思われます。
とても素直で、実行力があって、ガンガン突き進んでいく人だと思うのです。論語の中では「政事には冉有と季路(まつりごとをやらせたら、ぜんゆうと季路・子路さんのことです)」と言われていたくらい実行力のある人でした。
だから、それくらい政治家としては、「わきまえる」ということが大事で、なるべく怪しいものは遠ざけ、危険なもの・知らないものに手も足も出さない。そういう姿勢が大事だと先生は言われます。
子路さんは、好奇心旺盛で、どんなところでも突っ込んでいく人だから、あぶない目に遭う可能性はあったでしょう。だから、そうした素直で、黙っちゃおれない正義感、それは美徳ではあるけれど、知らずともよいことに載っかろうとするのを戒めようとされた。
それくらい注意しておいても、この弟子はどんどん突き進んでいくだろうけれど、せめてことばとして注意しておきたいと、ひとこと、漠然としたことばを与えた。
先生、そんなことわかってますよ、と子路さんは言いません。そこは素直に受け止めた。そこがまた子路さんのいいところです。今の若い人なんか、「何を言ってんだよ、じいさん」と一蹴しそうなことばです。

知るということは、わきまえることです。知らない人が、やさしく、丁寧そうに、熱意を込めているように見せることがあるかもしれない。それは間違った行動です。
自分はそれを知らない、だからゴメンナサイと素直に認めることから、世の中は成り立っていくのです。
その反対に、「すべてこの通りで、間違いはない」と平気で言えるヤツは信用ならない。
これはだれもが知っていることなのです。「さあ、新しい未来に進もう」なんていうことはあり得ない。
問題だらけ、矛盾だらけ、不平だらけの世の中を、調整しまくり、それでもアンバランスは生まれ、天変地異は起こり、人はとんでもないことをしでかすものなのです。
それにフタをして、「この道が正しい道だ」なんて、とても言えない。そんなことは言えなくて苦虫をかみつぶしたような顔の人が、信頼できる(かもしれない)人です。ストレスで倒れる人こそ、人らしい人です。……ああ、グチになりました。昔のあの人は、まだ信頼できたのかも……。今は完全にみんなを小バカにしている?
ちゃんと「知らない」と言える人間になれるように努力していきたいです。
それが言えない人がまわりにいたら、私はそれこそそんな人を知らんぷりしていきますか。いや、ダメですね。「どうしたの?」と声をかけられる努力もしなくてはいけない。
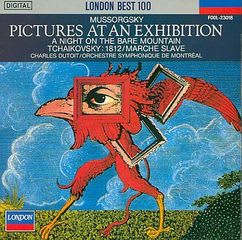
★ 答え 21・知 これ知るなり! です。
★『論語』では、「おしえる」を「教」と「誨」を使い分けています。
「教」は厳しくおしえるの意味で、「誨」は一対一的でねんごろに教え諭す場合に用いられています。
わりと好きなお弟子さんの子路さんに、先生が積極的に声を掛けました。なかなかめずらしいことです。というか、子路さんには先生も気を許してあれこれ話したくなるんでしょう。それは子路さんの魅力です。私はそんな魅力ありますか? 近ごろはみんなから声を掛けられなくなっている気がします。それだけ私全体から放置しておいて欲しいオーラを出しているのかもしれない。
もっとみんなに声を掛けてもらえるオッチャンにならなくてはいけません。私は、積極的なアホーなオッチャンなんですから、抜けているところだらけなんだから、みんなに助けてもらわなくちゃいかんのですから、変なオーラを出さず、みんなに声を掛けてもらえる子路さんを見習わなくては!
そのためには、どうせアホーなのは仕方がないのだから、それをみんなにちゃんとわかってもらうようにしなくちゃいけません。まあ、明日からせいぜい努力しようと思います。

さあ、子路さんに先生がおしえてくださいましたよ。
21【知らざるを知らずと為すこれ( )るなり】……知ったかぶりをせず、知らなければ知らない、知っていれば知っているとはっきりさせる、これが真に「……る」ことだ。やや独断的な性格の弟子の子路を諭した言葉。〈為政〉→禅問答のようですが、先ず自分の無知を認める所から始めようとしたものでしょうか。
先生はどうしてそのようなことを子路さんに話したんでしょう。そっちが気になりますね。とてもありふれた事実のような気がするんですが、とても深遠な気もします。
まさか子路さんが知ったかぶりをする人だったわけではないでしょう。わりとドッチラケの子路さんは、何もかも投げ出してしまうし、思わせぶりとか、知ったかぶりとか、そんなまわりくどいことはしない人だと思われます。
とても素直で、実行力があって、ガンガン突き進んでいく人だと思うのです。論語の中では「政事には冉有と季路(まつりごとをやらせたら、ぜんゆうと季路・子路さんのことです)」と言われていたくらい実行力のある人でした。
だから、それくらい政治家としては、「わきまえる」ということが大事で、なるべく怪しいものは遠ざけ、危険なもの・知らないものに手も足も出さない。そういう姿勢が大事だと先生は言われます。
子路さんは、好奇心旺盛で、どんなところでも突っ込んでいく人だから、あぶない目に遭う可能性はあったでしょう。だから、そうした素直で、黙っちゃおれない正義感、それは美徳ではあるけれど、知らずともよいことに載っかろうとするのを戒めようとされた。
それくらい注意しておいても、この弟子はどんどん突き進んでいくだろうけれど、せめてことばとして注意しておきたいと、ひとこと、漠然としたことばを与えた。
先生、そんなことわかってますよ、と子路さんは言いません。そこは素直に受け止めた。そこがまた子路さんのいいところです。今の若い人なんか、「何を言ってんだよ、じいさん」と一蹴しそうなことばです。

知るということは、わきまえることです。知らない人が、やさしく、丁寧そうに、熱意を込めているように見せることがあるかもしれない。それは間違った行動です。
自分はそれを知らない、だからゴメンナサイと素直に認めることから、世の中は成り立っていくのです。
その反対に、「すべてこの通りで、間違いはない」と平気で言えるヤツは信用ならない。
これはだれもが知っていることなのです。「さあ、新しい未来に進もう」なんていうことはあり得ない。
問題だらけ、矛盾だらけ、不平だらけの世の中を、調整しまくり、それでもアンバランスは生まれ、天変地異は起こり、人はとんでもないことをしでかすものなのです。
それにフタをして、「この道が正しい道だ」なんて、とても言えない。そんなことは言えなくて苦虫をかみつぶしたような顔の人が、信頼できる(かもしれない)人です。ストレスで倒れる人こそ、人らしい人です。……ああ、グチになりました。昔のあの人は、まだ信頼できたのかも……。今は完全にみんなを小バカにしている?
ちゃんと「知らない」と言える人間になれるように努力していきたいです。
それが言えない人がまわりにいたら、私はそれこそそんな人を知らんぷりしていきますか。いや、ダメですね。「どうしたの?」と声をかけられる努力もしなくてはいけない。
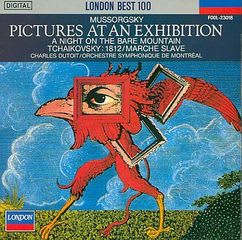
★ 答え 21・知 これ知るなり! です。
★『論語』では、「おしえる」を「教」と「誨」を使い分けています。
「教」は厳しくおしえるの意味で、「誨」は一対一的でねんごろに教え諭す場合に用いられています。

















