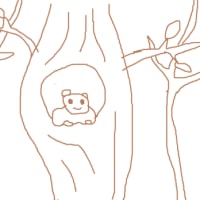全国の古本ファンのみなさま、私の古本探しを報告いたします!
あまりたいしたことではないですけど、書いてみて自分のこだわりを確認する作業ですね。
奥さんと大阪に出て、私だけ上本町で降りました。そこから四天王寺まで歩くのです。今は秋だから、道路をクルマが走っていても、日差しが降り注いでても、あまり気にならなくて、平気でスイスイと歩きました。上町通りを南下して、突き当たると右折しなきゃいけないのです。そして谷町通りに出なくちゃいけない。
四天王寺さんの境内はすぐそこまで広がっているはずなのに、そこへたどり着くには大きく回らなくちゃいけませんし、たぶんそんなものなのだと思っていました。工事中の壁やら、細い先の見えない路地があって、ひょっとしてここをいけばいけるかもしれないし、行き止まりだったら引き返せばいいやと、細い路地に入っていきました。

すると、墓地が広がって、予想通り四天王寺さんの北の入り口になっていました。何だか得した感じで、これから四天王寺でイベントがあったら、こんな道があるよと紹介したくなるような路地でした。
地元の人なら当たり前なんだろうけど、私はここではよそ者なので、道がつながった喜びにとにかくひたり、古本市は後回しで、四天王寺観光をしました。
例によって、そのまんまの工夫のない写真を撮り、外国の人たちがたくさんいるけど、それでもやっぱりお参りに来た人たちもいて、それなりにありがたい気分です。
お線香が燃え上がる本堂、亀たちが集団で住んでいる池、間断なく鳴り響く鐘楼、いつもの下世話なというか、庶民的な四天王寺さんの雰囲気です。

ひととおり写真を撮ったので、さて平積み1冊100円のコーナーから冷やかして行こうとザーッと見てみました。するとどうでしょう。
まず松村武雄編『中国神話伝説集』(1976 社会思想社・現代教養文庫)が目に入り、即座に買うことを決定しました。……家に帰って見直してみると、実は1997年の8月に鹿児島の指宿で買ったものがあって、97年お買い上げのものは初版から数えて21年目で41刷になっています。ところが私が今回買ったのは1976年版の初版のものでした。まあ、1997年から18年経っていますが、いまだに読んでいないという事実に気づけた1冊です。ああ、とんでもない私です。何もかも忘れて暮らしているし、何もかもちゃんと読んでいないのでした。
続いて、海音寺潮五郎『田原坂 小説集・西南戦争』(1990 文春文庫)……こちらは海音寺先生の西郷さんものであり、こういうのがあったというのさえ知らないので、すぐに買いました。短編ばかりだから、すぐ読めるというのがお買い上げの動機でもありますが、すぐ読めるということは、なかなか手に取らないということであり、とりあえず買ったけど、いつ読むのか少し不安です。なかなか読まないかもしれない。
さきほどのシリーズで、鈴木了三訳の『中国奇談集』(1984 社会思想社・現代教養文庫)私のベースは中国に少しだけあるので、こちらのお勉強をしたいと思うので、買いました。ベースだと主張するのは勝手だけど、不勉強だから、あまり偉そうなことは言えません。勉強してナンボです。せいぜい頑張りたいです。
ふと目に入った瀬戸内晴美さん『放浪について』(1977 講談社文庫)……折れ曲がってたりしましたが、寂聴さんのエッセイみたいなのを持ってなかったし、旅関連かなと、「エイッ」と手に取りました。少しくたびれているからカバーをつけて、いつか読みたいです。
峯村文人著『十訓抄(じっきんしょう)』(1956年初版で、私のは1980年の13刷 学燈文庫)……珍しい文庫なので興味本位で買いました。
それから1982年の中部版時刻表・文庫サイズを買いました。1982年の北陸線とか中央線の電車を見たかったんです。無駄遣いだとは思いましたが、何かの資料になるかなと買いました。
6冊一気に手に取りました。ああ、こんなことではダメだと思いつつ、チラッと岩波新書に目をやると、

許広平著・安藤彦太郎訳『暗い夜の記録』(1955に第1刷で、私のは1974年の第8刷 岩波新書・青版)……タイトルにひかれて、内容は、「許広平女史は、……「わたしのこのような書物が要らなくなりますように、印刷しなくてもいい日がきますように、これが著者の心からの願いなのです」といってこられた。19年たった今、残念ながらこの本はまだ「要らなく」なっていないようである」と第8刷の改訂版でも書かれていて、日本が中国で行った行いについての本らしいのです。
こういう本があったなんて、全く知らなかった私は、もうたまらなくなって買うことにしました。なかなか読まないと思いますが、今も読みたい気持ちはいっぱいです。すぐにでも読みたいです。
その横に、中村亮嗣著『ぼくの町に原子力船がきた』(1977 岩波新書・青版)……青森に住む画家の中村さんが、原子力船むつがやってきたことを書いているらしいので、東北と原子力についても知りたいので、買いました。たぶん、庶民は無条件に国家の意思を飲み込まされる形なのだとは思うのですが……。読んでないから、よくわからないけど、買いました。
立命館の学長さんだった人で、法律が専門のはずの末川博さんの『彼の歩んだ道』(1965 岩波新書・青版)……名前だけはかろうじて知っていた末川先生が、若い頃を「彼」という形で語る自伝で、興味本位で買いました。これは読まない率は高そうです。
亀井節夫著『日本に象がいたころ』(1967 岩波新書・青版)……これも読まない率は高いですけど、ミエゾウ関連で、いつか開くときがあるかなと、ついでに買っちゃいました。無駄遣いですね。
ああ、一気に1000円のお買い上げです。最初の十分くらいで荷物をしょいこみました。これで動きがとれなくなって、あとは2冊文庫を買っただけでした。その2冊はおいおい書いていくことにします。

まだまだ連休はつづきますし、阪神は今日は勝つのでしょうか。勝っても負けても、あまり心が動きませんね。どうしたんでしょう。阪神ファンじゃなくなったのかなあ。おかしいです。
あまりたいしたことではないですけど、書いてみて自分のこだわりを確認する作業ですね。
奥さんと大阪に出て、私だけ上本町で降りました。そこから四天王寺まで歩くのです。今は秋だから、道路をクルマが走っていても、日差しが降り注いでても、あまり気にならなくて、平気でスイスイと歩きました。上町通りを南下して、突き当たると右折しなきゃいけないのです。そして谷町通りに出なくちゃいけない。
四天王寺さんの境内はすぐそこまで広がっているはずなのに、そこへたどり着くには大きく回らなくちゃいけませんし、たぶんそんなものなのだと思っていました。工事中の壁やら、細い先の見えない路地があって、ひょっとしてここをいけばいけるかもしれないし、行き止まりだったら引き返せばいいやと、細い路地に入っていきました。

すると、墓地が広がって、予想通り四天王寺さんの北の入り口になっていました。何だか得した感じで、これから四天王寺でイベントがあったら、こんな道があるよと紹介したくなるような路地でした。
地元の人なら当たり前なんだろうけど、私はここではよそ者なので、道がつながった喜びにとにかくひたり、古本市は後回しで、四天王寺観光をしました。
例によって、そのまんまの工夫のない写真を撮り、外国の人たちがたくさんいるけど、それでもやっぱりお参りに来た人たちもいて、それなりにありがたい気分です。
お線香が燃え上がる本堂、亀たちが集団で住んでいる池、間断なく鳴り響く鐘楼、いつもの下世話なというか、庶民的な四天王寺さんの雰囲気です。

ひととおり写真を撮ったので、さて平積み1冊100円のコーナーから冷やかして行こうとザーッと見てみました。するとどうでしょう。
まず松村武雄編『中国神話伝説集』(1976 社会思想社・現代教養文庫)が目に入り、即座に買うことを決定しました。……家に帰って見直してみると、実は1997年の8月に鹿児島の指宿で買ったものがあって、97年お買い上げのものは初版から数えて21年目で41刷になっています。ところが私が今回買ったのは1976年版の初版のものでした。まあ、1997年から18年経っていますが、いまだに読んでいないという事実に気づけた1冊です。ああ、とんでもない私です。何もかも忘れて暮らしているし、何もかもちゃんと読んでいないのでした。
続いて、海音寺潮五郎『田原坂 小説集・西南戦争』(1990 文春文庫)……こちらは海音寺先生の西郷さんものであり、こういうのがあったというのさえ知らないので、すぐに買いました。短編ばかりだから、すぐ読めるというのがお買い上げの動機でもありますが、すぐ読めるということは、なかなか手に取らないということであり、とりあえず買ったけど、いつ読むのか少し不安です。なかなか読まないかもしれない。
さきほどのシリーズで、鈴木了三訳の『中国奇談集』(1984 社会思想社・現代教養文庫)私のベースは中国に少しだけあるので、こちらのお勉強をしたいと思うので、買いました。ベースだと主張するのは勝手だけど、不勉強だから、あまり偉そうなことは言えません。勉強してナンボです。せいぜい頑張りたいです。
ふと目に入った瀬戸内晴美さん『放浪について』(1977 講談社文庫)……折れ曲がってたりしましたが、寂聴さんのエッセイみたいなのを持ってなかったし、旅関連かなと、「エイッ」と手に取りました。少しくたびれているからカバーをつけて、いつか読みたいです。
峯村文人著『十訓抄(じっきんしょう)』(1956年初版で、私のは1980年の13刷 学燈文庫)……珍しい文庫なので興味本位で買いました。
それから1982年の中部版時刻表・文庫サイズを買いました。1982年の北陸線とか中央線の電車を見たかったんです。無駄遣いだとは思いましたが、何かの資料になるかなと買いました。
6冊一気に手に取りました。ああ、こんなことではダメだと思いつつ、チラッと岩波新書に目をやると、

許広平著・安藤彦太郎訳『暗い夜の記録』(1955に第1刷で、私のは1974年の第8刷 岩波新書・青版)……タイトルにひかれて、内容は、「許広平女史は、……「わたしのこのような書物が要らなくなりますように、印刷しなくてもいい日がきますように、これが著者の心からの願いなのです」といってこられた。19年たった今、残念ながらこの本はまだ「要らなく」なっていないようである」と第8刷の改訂版でも書かれていて、日本が中国で行った行いについての本らしいのです。
こういう本があったなんて、全く知らなかった私は、もうたまらなくなって買うことにしました。なかなか読まないと思いますが、今も読みたい気持ちはいっぱいです。すぐにでも読みたいです。
その横に、中村亮嗣著『ぼくの町に原子力船がきた』(1977 岩波新書・青版)……青森に住む画家の中村さんが、原子力船むつがやってきたことを書いているらしいので、東北と原子力についても知りたいので、買いました。たぶん、庶民は無条件に国家の意思を飲み込まされる形なのだとは思うのですが……。読んでないから、よくわからないけど、買いました。
立命館の学長さんだった人で、法律が専門のはずの末川博さんの『彼の歩んだ道』(1965 岩波新書・青版)……名前だけはかろうじて知っていた末川先生が、若い頃を「彼」という形で語る自伝で、興味本位で買いました。これは読まない率は高そうです。
亀井節夫著『日本に象がいたころ』(1967 岩波新書・青版)……これも読まない率は高いですけど、ミエゾウ関連で、いつか開くときがあるかなと、ついでに買っちゃいました。無駄遣いですね。
ああ、一気に1000円のお買い上げです。最初の十分くらいで荷物をしょいこみました。これで動きがとれなくなって、あとは2冊文庫を買っただけでした。その2冊はおいおい書いていくことにします。

まだまだ連休はつづきますし、阪神は今日は勝つのでしょうか。勝っても負けても、あまり心が動きませんね。どうしたんでしょう。阪神ファンじゃなくなったのかなあ。おかしいです。