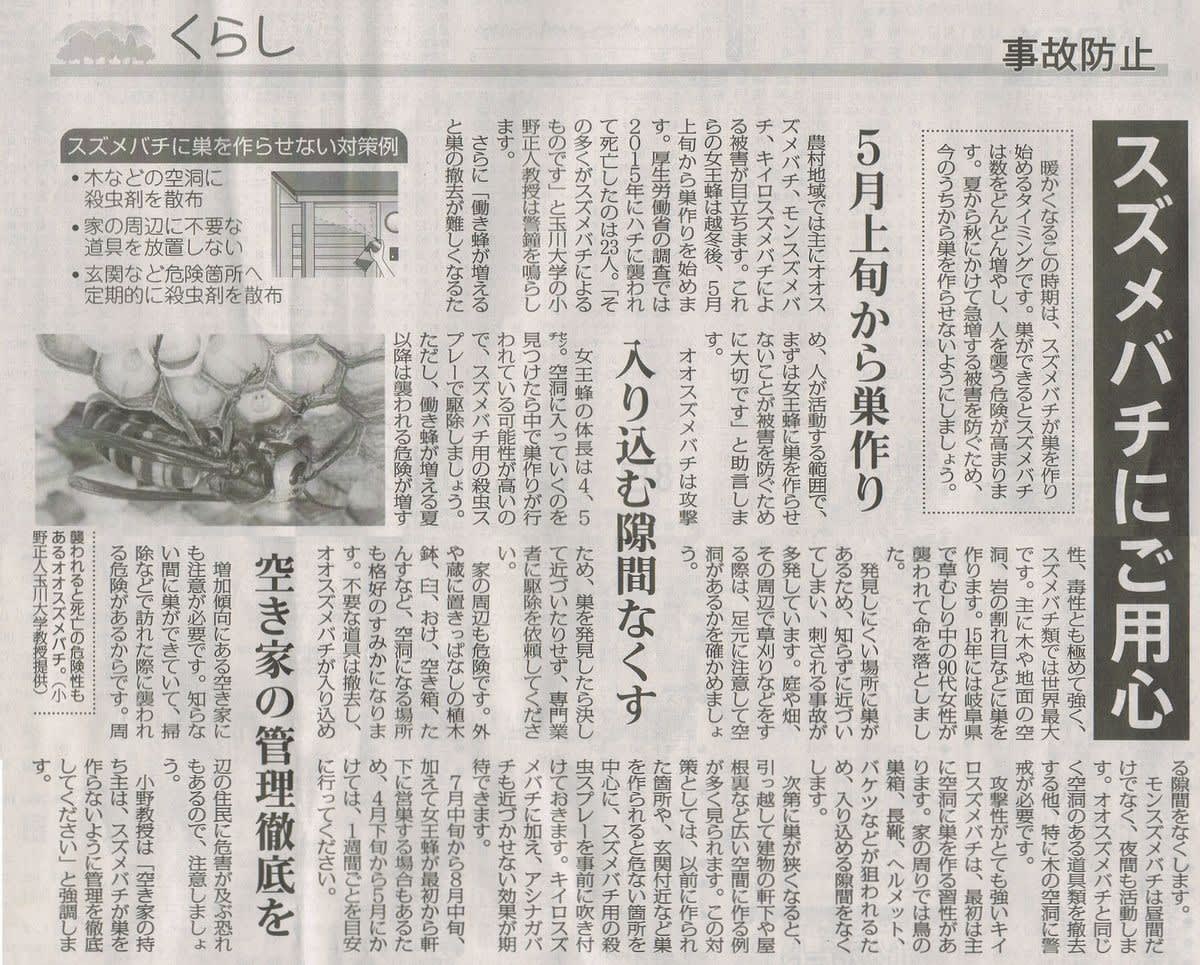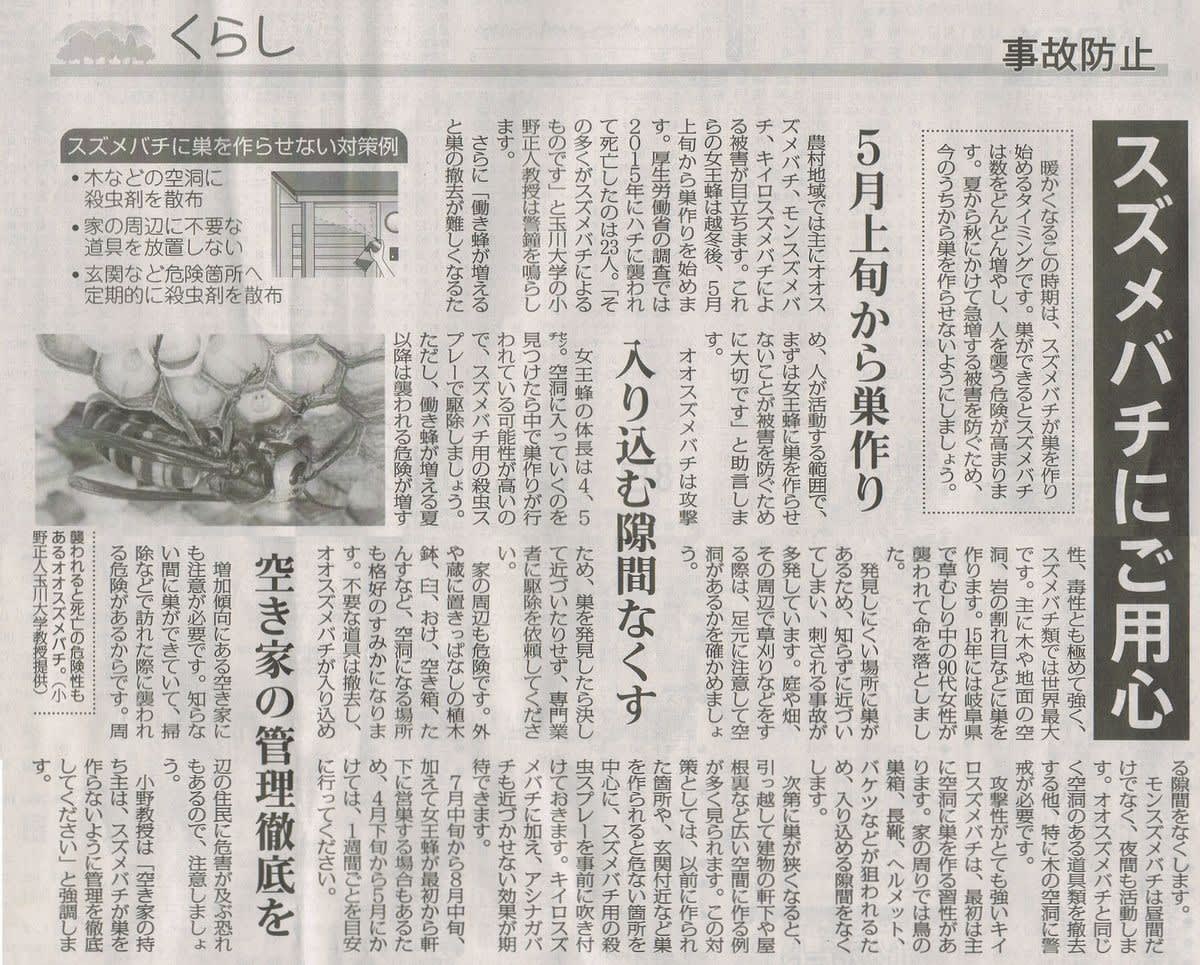■ 2016年4月12日
この辺りでは「あまこ」というが、「アリマキ」のこと。
灰を振ったように、びっしりと着いている。
これをガムテープで引っ付けて捕ること1時間以上。(-_-;)
↓ これは カリフローレだが、F1ジェットドームや晩抽プチヒリにも
少し着いていたのでガムテープで吸着捕獲した。

↑ この隣にあるカーボロネロの新芽に着いているあまこを、
前に見ていたのを放置したのが悪かったのかも?
隣の畝に移動したようだ。

 ( 写真をクリックすると拡大画像になります )
( 写真をクリックすると拡大画像になります )
イワタニ(IWATANI)CB-TC-BZ(カセットガス式 カセットガストーチバーナー)を使用し、
新芽に着いたあまこを燃やしてみた。(^^ゞ
相当な荒療治だが、菜花ももう食べたいだけ食べたし、
この株がダメにならなければそれで良しとしようか。
これからの、他の野菜には出来ない。

 ( 写真をクリックすると拡大画像になります )
( 写真をクリックすると拡大画像になります )
「アリマキ」という虫は、草花の花や茎にびっしりと群れを成してとりついている
透き通るような薄い緑色をした小さな虫。
このアリマキは、基本的には雌しか存在せず、誰の助けも借りずに自力で子どもを作り産み、
生まれた子どもは全て雌で、雌だけで世代を紡いでいく。
その子どもは、卵ではなく哺乳類のように「できあがった形」で産まれ、
自らのクローンを自らの力によって作り出すことで世代を紡ぎ続けている。
そんなアリマキにも、一年に一度だけ繁殖の仕組みを変える時期が訪れる。
冬に向かって気温が低下し始める頃、アリマキの母は雄を産み出し、
そのオスは、秋が終わるまでにできるだけ多くの雌と交尾をし、
作り出された受精卵は、草木の隙間やコケの下などの安全な場所に産み付けられ、
厳しい冬をくぐり抜けて春を迎え、孵化する。
この秋に産み出す雄を見つけて捕獲しないと、我が家のあまこ(アマキリ)は
永遠に世代を紡いでいくことだろう。(-_-;)