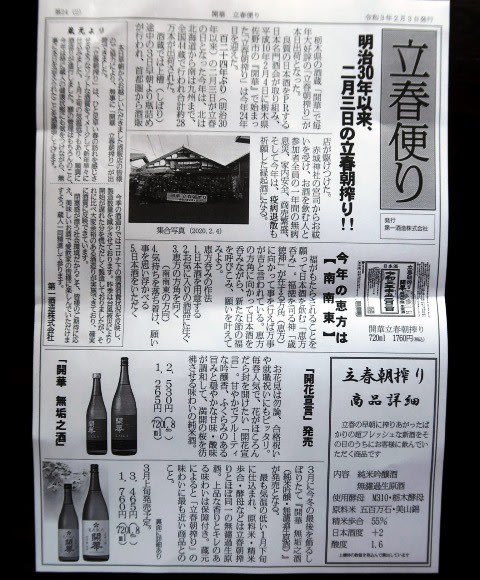取材したのは少し前になりますが、
今の時代だから飲みたい、不安定なコロナ禍だから飲みたい、と思うワインを紹介したいと思います。
スイスはヴァレー州の「Domaine de Beudon」(ドメーヌ・ドゥ・ブドン)で、レマン湖の南東約40km、ローヌ川の右岸に位置するワイナリーです。
ワイナリーの創業は1971年で、創業者はジャック・グランジュさん。
現在は3人の娘さんたちの世代に引き継がれています。
その3姉妹のひとり、セブリンさんが2019年11月に初来日し、ワイナリーとワインの紹介をしてくれました。

セブリン Séverine さん ーDomaine de Beudon (Swiss)
セブリンさんたちの父ジャックさんは、チューリッヒの大学に通い、1968年にはスイス最年少で作物栽培技術者となり、アメリカにも渡りました。
1971年、25歳の時にドメーヌを購入し、Domaine de Beudonのオーナーとなります。
若くして購入できたのは、安く売りだされていたからだそうです。
ブドンのブドウ畑は急斜面の崖の上にあります。
そのため、畑に行くには、険しい崖の道を歩いていかねばなりません。
それでは大変だということで、個人用のケーブルカーを敷いたそうです。
そんな崖の上の畑のドメーヌは、たしかに当時は安かっただろうと想像できます。

彼らのワインのラベルに崖の絵が描かれていますが、かなりの急斜面!
多少は強調していると思いますが、これはスゴイ!
崖の上の畑は標高740~890mの場所にあり、6haほどの広さです。
畑の向きは真南で、ローヌ川沿いの平野を見下ろしています。
土壌は、結晶塊と石灰岩が混ざり、ローヌ川から流れてきた砂利、花崗岩、ルス(粘土質)などなど、多様性に富む地質です。
1999年に大きな土砂崩れがあったそうで、すべてが流れ、他のものが運ばれてきたため、さらに土壌の多様性が深まったといいます。
また、急斜面の崖は風が強く吹き、ブドウ畑の湿気を吹き飛ばしてくれる利点があります。
しかしながら、急斜面の崖の上の畑には危険も伴い、2016年、崖の上から落ちたトラクターの事故で、ジャックさんが亡くなってしまいました。
家族の哀しみは非常に深かったそうですが、ジャックさん亡き後のドメーヌは、1972年に結婚した妻のマリオンさんと3人の娘たちが継いでいます。
ジャックさんの妻であり、セブリンさんたち姉妹の母であるマリオンさんは、実はもの凄いバックグラウンドを持つ方です。
マリオンさんの父(アルノ・フェス氏)が、ビオディナミの礎となる農業方法を提唱したルドルフ・シュタイナー氏(1861-1925)の友人で、スイスのドルナハ(バーゼルの南部)に住んでいた時に家族ぐるみで付き合いがあったというのです。(シュタイナー氏はドルナハで死亡)
その後、アルノ氏はValiasに移り、ビオディナミの農業を始めました。マリオンさんは小さな頃からビオディナミのエッセンスを感じる環境で育ったわけです。
マリオンさんはジュネーブで庭師、作物を育てる仕事に従事し、同時にフルートを吹く音楽家でもありました。
ジャックさんと結婚し、子どもが生まれると音楽の方は引退しましたが、ジャックさんと一緒に子育てをしながら、ブドウ栽培に取り組んでいきます。

夫妻が考えたのは、どのように多様性をもってブドウを育てていくべきか?でした。
ビオディナミでやりたいけれど、実際にするのは難しく、それでも、1974年から試行錯誤し、それを繰り返していくうちに、1989年に完全に有機農法での栽培に移行し、1992年からビオディナミに取り組むようになりました。

現在は、デメターとBIOスイスの認証を取得しています。
(ちなみに、ここはフランス語を話す地域です)
「必要じゃないものはいらない」というのがジャックさんの生き方で、自給自足できるものは、水力発電所で畑および家庭用水をつくったりしました。
彼らの考えるビオディナミとは、ライフスタイルに関しての考え方、でした。
天空と地上の土壌の間にある植物は、両方からエネルギーを受け取ります。
それゆえ、大切なのは「環境」です。
たとえば、雑草をすべて取り除いてしまうように、何かを殺すと全体の調和が崩れます。
ほかの生物との調和を強めること、生きている生物をより強めることが大事で、そうしたことによりエネルギーを蓄えたブドウはもっともっと力を持つようになる、と考えたのです。
実際、彼らの畑は非常に険しい急斜面の崖の上にあるため、春先の剪定作業にしても大変で、下草(いわゆる雑草)もたくさん出てしまいます。
下草が元気すぎると、エネルギーが下草の方に行ってしまいます。
それを自然な方法で解決してくれるのが「羊」だそうです。
羊たちは下草を食べ、環境改善をしてくれる上、排泄物を土に残していきます。
実は、野生のヤギも多頭すみついているそうで、彼らは実を付けたブドウを狙ってくるため、ネットをかけて守っているとのことでした。
でも、あまりに多くなりすぎたヤギを、2019年に少し狩ってもらったそうです。
というように、周囲の環境と調和をとりながらつくるブドンのワインは、現在、4アイテムが日本に輸入されています。

左より)Domaine de Beudon
Fendant VV 2012 / Riesling × Silvaner VV 2009 / Cuvee Antique VV 2017
Gamay VV 2013 / Fendant VV 2004(参考品)
※Fendant はシャスラ種のことです
Fendant VV 2012 は、崖の上の樹齢30年の畑のブドウ(凝縮感しっかり)と、崖の下の樹齢50~60年の畑のブドウ(ジュースたっぷり)を混ぜています。
色は濃いが、香りは控えめ。フルーツの厚みがあるが、甘みは少なめで、ややストイック。ミネラリーでキレのある、繊細なスタイルの辛口。
輸入元希望小売価格:5,050円(税抜)
Riesling × Silvaner VV 2009 は、ミュラー・トゥルガウ100%。これも色濃いです。アロマが華やかで、やわらかな甘みのあるアタック。ボディに丸み、コクがあり、アプリコットの果肉を思わせる厚み、ふくよかさを感じました。
輸入元希望小売価格:5,600円(税抜)
Cuvee Antique VV 2017 は、シャスラ100%。アンティークとは、ヴァレー州の伝統手法でつくられた、という意味です。かつては、崖の下でブドウを育て、崖の上に住んでいたため、収穫したブドウを背負って崖を昇る間にブドウが自然に潰れたそうです。
このワインは8日間スキンコンタクト、マセレーションしたオレンジワインで、ハチミツのように非常に濃い色合いです。果皮からのタンニンを感じ、独特の風味を感じました。
輸入元希望小売価格:5,550円(税抜)
Gamay VV 2013 は、黒ブドウのガメイを使った赤ワインです。ステンレスタンク(イノックス)でピュアに仕上げています。
が、外観はやや濁った淡い赤。タンニンはキレイで、フレッシュ!しなやかでうまみたっぷりな、非常にバランスの取れた赤ワインに仕上がっていると感じました。
輸入元希望小売価格:6,050円(税抜)
参考品の Fendant VV 2004 は、かなり古めのヴィンテージです。
今回はどれもややヴィンテージが古めですが、フレッシュさを保てています。
その秘訣は、急激なアクションを起こさないように造ると安定し、長期熟成が可能なワインに仕上がるとのことでした。

1971年の創業以来、ジャック&マリオン夫妻が二人三脚でワイン造りを行なってきたブドンですが、2007年から、ジャックさんの友人(自身もワイナリーを持っている方)が醸造家として入っています。
セブリンさん曰く「なにか起こった時にすぐに対応できるよう、ワインに寄り添っている。ただし、最低限の介入です」。
セブリンさんが父ジャックさんから言われてきたのは、
「ワインは食物であり、薬でもあるから、身体に取り込んだ時に良いものを造りたい」ということ。
「わたしたちのワインを飲んだ時に、ブドウ、ワインが身体に統合してほしい、足の先から何かの効果を感じてほしい」とセブリンさん。
彼らの声を思い出し、ワインが造られている土地やブドウが栽培されている畑の風景を改めて想像した時に、いま、心を落ち着けて飲みたいのは、国がどうかとか、肩書云々とか関係なく、ドメーヌ・ドゥ・ブドンのようなワインなのかも、と思い、紹介したいと思いました。
ちなみに、ドメーヌ・ドゥ・ブドンは、ビオディナミを牽引するニコラ・ジョリー氏のグループ「Renaissance des Appellation」のメンバーでもあります。
輸入元:ヴァンドリーヴ
https://vinsdolive.com/
輸入元のHPでは、キュヴェ・アンティーク以外、すでに完売になっていますが、小売店の方で在庫を持っているところもあると思いますので、欲しい方は、造り手の名前+ワイン名で探してみてください。
(追記)2021.2.9
輸入元より連絡があり、品切れになっていたDomaine de Beudonのワインが2月8日に入荷したとのこと。
なんというタイミング!



































 に準備するとしたら、さすがに業務スーパー直輸入のチョコレートは、選びにくいかも?
に準備するとしたら、さすがに業務スーパー直輸入のチョコレートは、選びにくいかも?