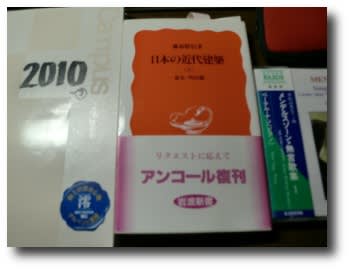岩波新書で、藤森昭信著『日本の近代建築(上)~幕末・明治篇』を読みました。著者の講演を、ごく最近お聞きしたこともあり、だいぶ前に購入して積ん読していた本書を、ようやく通読した次第です。当地には、明治期に建てられた多くの西洋風建築が残されていますが、その評価なども興味深く、たいへんおもしろく読むことができました。
本書の構成は、次のようになっています。
はじめの二つの章では、グラバー邸のようなヴェランダコロニアル様式が、南方系の植民地に適応したものであることと、札幌の開拓使本庁舎のような下見板コロニアル様式が、自然の厳しさに対応した北方系の植民地ふう建築であることを示します。幕末から明治初期に渡来した冒険技術者たちの建築をモデルに、日本の棟梁たちが擬洋風建築を作りますが、これも松本の開智学校のような漆喰系擬洋風と、山形の済生館のような下見板系擬洋風、そして木骨石造系の擬洋風などに分類できるとのこと。とくに山形県は、済生館のほか鶴岡の朝暘学校、西田川郡役所、鶴岡警察署など、下見板系擬洋風の震源地であったと評価します。
後半は、御雇外国人に学びつつ、日本人建築家が誕生していく経緯をたどります。
当地に下見板系擬洋風建築が多く残されている理由は、そもそも三島通庸のもとでたくさん建てられたということと、戦災に遭わずに日常的に使われ続けたことで維持管理されてきたということが大きいでしょう。実際に住んでみて住みやすいかどうかは別として、雪国の風土に適した様式だったために、独特の美しさを保ったまま残ることができたのだろうと思います。
以下、機会あるごとに撮影してきた、山形の西洋風建築物の写真を掲載します。まずは、三島通庸が建てた旧西田川郡役所です。現在は、鶴岡市の致道博物館内にあります。

次は、元山形県立病院で後に市立病院となった済生館(明治9年)。山形市の霞城公園内に移築されています。


鶴岡市内、藤沢周平記念館に隣接している建物は、「大宝館」といい、以前は市立図書館として使われておりました。

鶴岡市に合併した旧藤島町にある、旧東田川郡役所です。


天童市には、旧東村山郡役所がありますが、ちょうどよい写真がありませんので、機会を見て撮影したいと思います。
本書の構成は、次のようになっています。
1. 地球を東に回って日本へ~ヴェランダコロニアル建築~
2. 地球を西に回って日本へ~下見板コロニアルと木骨石造~
3. 冒険技術者たちの西洋館~洋風工場~
4. 棟梁たちの西洋館~擬洋風・その1~
5. 文明開化の華~擬洋風・その2~
6. 御雇建築家の活躍~歴史主義の導入~
7. 日本人建築家の誕生~歴史主義の学習~
はじめの二つの章では、グラバー邸のようなヴェランダコロニアル様式が、南方系の植民地に適応したものであることと、札幌の開拓使本庁舎のような下見板コロニアル様式が、自然の厳しさに対応した北方系の植民地ふう建築であることを示します。幕末から明治初期に渡来した冒険技術者たちの建築をモデルに、日本の棟梁たちが擬洋風建築を作りますが、これも松本の開智学校のような漆喰系擬洋風と、山形の済生館のような下見板系擬洋風、そして木骨石造系の擬洋風などに分類できるとのこと。とくに山形県は、済生館のほか鶴岡の朝暘学校、西田川郡役所、鶴岡警察署など、下見板系擬洋風の震源地であったと評価します。
後半は、御雇外国人に学びつつ、日本人建築家が誕生していく経緯をたどります。
当地に下見板系擬洋風建築が多く残されている理由は、そもそも三島通庸のもとでたくさん建てられたということと、戦災に遭わずに日常的に使われ続けたことで維持管理されてきたということが大きいでしょう。実際に住んでみて住みやすいかどうかは別として、雪国の風土に適した様式だったために、独特の美しさを保ったまま残ることができたのだろうと思います。
以下、機会あるごとに撮影してきた、山形の西洋風建築物の写真を掲載します。まずは、三島通庸が建てた旧西田川郡役所です。現在は、鶴岡市の致道博物館内にあります。

次は、元山形県立病院で後に市立病院となった済生館(明治9年)。山形市の霞城公園内に移築されています。


鶴岡市内、藤沢周平記念館に隣接している建物は、「大宝館」といい、以前は市立図書館として使われておりました。

鶴岡市に合併した旧藤島町にある、旧東田川郡役所です。


天童市には、旧東村山郡役所がありますが、ちょうどよい写真がありませんので、機会を見て撮影したいと思います。