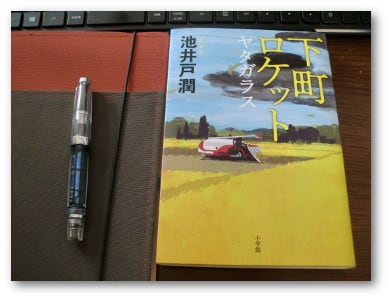小学館から2018年10月に刊行された単行本で、池井戸潤著『下町ロケット〜ヤタガラス』を読みました。前作『ゴースト』が前編、この『ヤタガラス』が後編という位置づけのようで、実際、物語の始まりは「濃い夕景に塗れ、(中略)佃の前からその姿を消した」はずの天才エンジニア島津裕が、応接セットのソファの足元にクマのプリントのトートバッグを置き忘れたことから、話は再開されます。作者は、前作の「ICレコーダーを忘れちゃった作戦」がよほど気に入ったらしく、またこの手を使ったようです(^o^)/
帝国重工内の社内抗争のあおりで、宇宙航空部の主役を外れ脇役にまわることになった財前道生は、今までのGPSに比して画期的な精度を誇る準天頂衛星ヤタガラスの能力を活かし、社会に貢献できるものとして、無人農業ロボットを発想し、まず無人自動運転トラクターの開発を企画します。エンジンとトランスミッションは佃製作所に外注し、トラクター本体は帝国重工で作るという案でした。そのための自動運転のプログラムは、佃社長の学生時代の仲間で、今は北海道農業大学の教授となっている野木博文のものです。ギアゴースト社を離れ、佃製作所に迎えられた島津裕は、自分の設計した小型トランスミッションの不具合に気づき、その解決法として特許を取得します。しかし、ライバル会社ダイダロスのエンジンとギアゴーストのトランスミッションに、以前、野木研究室から盗んだプログラムをもとに企業化したキーシンの通信制御システムという組み合わせの「ダーウィン」が華々しくデビュー、帝国重工側も的場俊一の誤った舵取りのおかげで迷走を余儀なくされます。
しかし、結局は現場で実際のニーズに向き合う開発か否かがポイントになるわけで、水害に會った殿村の実家の田んぼが実験ほ場の役割を果たし、帝国重工の「ランドクロウ」も着実に改良されていきますが…というお話。
○
前作『ゴースト』に続く『ヤタガラス』。いや、実に面白かった。最初の『下町ロケット』で宇宙航空技術に始まった物語が、ついに準天頂衛星による無人農業ロボットとして結実するのですから、なかなか考えられた構成です。テレビ番組が人気シリーズとなるのも納得の面白さです。
ただし、いざ自分の世界に置き換えて、「ランドクロウ」は農業を救うかと問われれば実は疑問符が付いてしまいます。そうですね、たしかに誤差が数センチの精度を持つ無人農業機械が普及すれば、農業の担い手不足の問題はだいぶ緩和されるかもしれません。でも、高額な農業機械を導入できるのは、平坦な農地を確保した大規模農家や農業法人に限られ、農業法人も担い手の病気やリタイアで、徐々に一人に集積してしまうことになり、それを突き詰めれば戦前の大地主の姿を変えた復活にほかならないのでは? 別の言い方をすると、戦後の農地改革はマチガイでしたということになるでしょう。農業の大規模専業化という方向が本当に日本の農業を救うことになるのかは、いささか疑問に感じられてなりませんけどね〜(^o^)/
帝国重工内の社内抗争のあおりで、宇宙航空部の主役を外れ脇役にまわることになった財前道生は、今までのGPSに比して画期的な精度を誇る準天頂衛星ヤタガラスの能力を活かし、社会に貢献できるものとして、無人農業ロボットを発想し、まず無人自動運転トラクターの開発を企画します。エンジンとトランスミッションは佃製作所に外注し、トラクター本体は帝国重工で作るという案でした。そのための自動運転のプログラムは、佃社長の学生時代の仲間で、今は北海道農業大学の教授となっている野木博文のものです。ギアゴースト社を離れ、佃製作所に迎えられた島津裕は、自分の設計した小型トランスミッションの不具合に気づき、その解決法として特許を取得します。しかし、ライバル会社ダイダロスのエンジンとギアゴーストのトランスミッションに、以前、野木研究室から盗んだプログラムをもとに企業化したキーシンの通信制御システムという組み合わせの「ダーウィン」が華々しくデビュー、帝国重工側も的場俊一の誤った舵取りのおかげで迷走を余儀なくされます。
しかし、結局は現場で実際のニーズに向き合う開発か否かがポイントになるわけで、水害に會った殿村の実家の田んぼが実験ほ場の役割を果たし、帝国重工の「ランドクロウ」も着実に改良されていきますが…というお話。
○
前作『ゴースト』に続く『ヤタガラス』。いや、実に面白かった。最初の『下町ロケット』で宇宙航空技術に始まった物語が、ついに準天頂衛星による無人農業ロボットとして結実するのですから、なかなか考えられた構成です。テレビ番組が人気シリーズとなるのも納得の面白さです。
ただし、いざ自分の世界に置き換えて、「ランドクロウ」は農業を救うかと問われれば実は疑問符が付いてしまいます。そうですね、たしかに誤差が数センチの精度を持つ無人農業機械が普及すれば、農業の担い手不足の問題はだいぶ緩和されるかもしれません。でも、高額な農業機械を導入できるのは、平坦な農地を確保した大規模農家や農業法人に限られ、農業法人も担い手の病気やリタイアで、徐々に一人に集積してしまうことになり、それを突き詰めれば戦前の大地主の姿を変えた復活にほかならないのでは? 別の言い方をすると、戦後の農地改革はマチガイでしたということになるでしょう。農業の大規模専業化という方向が本当に日本の農業を救うことになるのかは、いささか疑問に感じられてなりませんけどね〜(^o^)/