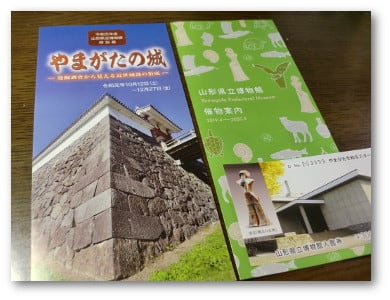
用事で山形市内に出かけた際に、始まったばかりの山形県立博物館(*1)の特別展「やまがたの城」(*2)を見学して来ました。「発掘調査から見える近世城郭の形成」と題した展示は、県内四地区の中心となった城を取り上げたもので、
の発掘調査によって得られた出土資料、城絵図、古写真などを展示しています。幸いに、学芸員氏の解説を聞くことも出来、興味深いものでした。

特に、個人的に興味深かった事柄としては、
などがありました。
県内に城が1500もあったというのは驚きです。戦乱により築かれ、焼かれ、あるいは不要として破却されたのでしょうが、支配者の住居というだけでなく、役所の役割も果たしていたのでしょうか。果たしてどういった性格のものだったのか、興味深いところです。
(*1):山形県立博物館
(*2):山形の城〜山形県立博物館2019年度特別展
- 山形城(別名:霞城、霞ヶ城)
- 鶴ヶ岡城(別名:大宝寺城)
- 米沢城(別名:松ヶ岬城、舞鶴城)
- 新庄城(別名:鵜沼城、沼田城)
の発掘調査によって得られた出土資料、城絵図、古写真などを展示しています。幸いに、学芸員氏の解説を聞くことも出来、興味深いものでした。

特に、個人的に興味深かった事柄としては、
- 城の石垣は近世以降に西日本から伝わったもので、最上義光の時代には土塁が基本であった。山形城も、石垣は鳥居家が治めた時代に築かれた。
- 米沢城の出土品からは、屋根瓦が見つかっていない。米沢城は板葺き屋根で、瓦は積雪地帯には必ずしも向いていないことと、経済的な理由もあろうが、瓦職人を育成しないという方針があったのでは。
- 天守があったのは、沼田城のみ。最上義光は周囲の出城の強化を重視し、本城に立てこもるという戦を考えていなかったと推測される文書が残されている。
- 県内には約1500の城があったと考えられているが、その中で小田島城(東根)の面積は鶴ヶ岡城に匹敵する規模。一国一城の定めにより、鳥居家の時代?に破却された。
などがありました。
県内に城が1500もあったというのは驚きです。戦乱により築かれ、焼かれ、あるいは不要として破却されたのでしょうが、支配者の住居というだけでなく、役所の役割も果たしていたのでしょうか。果たしてどういった性格のものだったのか、興味深いところです。
(*1):山形県立博物館
(*2):山形の城〜山形県立博物館2019年度特別展
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます