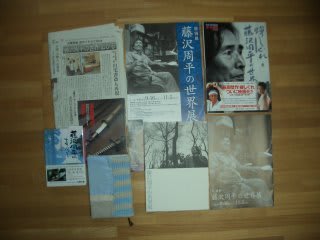文春文庫で『藤沢周平のすべて』を読みました。内容は、次のとおりです。
1 別れ 弔辞など 丸谷才一、井上ひさし、遠藤展子
2 周平さんと私 黒岩重吾、無着成恭、田辺聖子、宮城谷昌光、佐野洋、杉本章子、清水房雄、太田経子、倉科和夫、井上ひさし
3 藤沢周平が遺した世界 向井敏、川本三郎
4 半生を紀行する 土田茂範他座談会、福澤一郎、植村修介、金田明夫、高橋義夫、杉山透
5 藤沢周平作品と私 中野孝次、涌谷秀昭、丸元淑生、関川夏央、寺田博、吉田直哉、秋山駿
6 藤沢周平を語りつくす 吉村昭・城山三郎、秋山駿・中野孝次、皆川博子・杉本章子・宮部みゆき、仲代達矢・竹山洋・菅野高至
7 藤沢さんの頁 インタビュー「なぜ時代小説を書くのか」、エッセイ傑作選、小菅留治全俳句、他
8 藤沢さんへの手紙 出久根達郎、水木楊、鴨下信一、渡部昇一、黒土三男、辻仁成、佐藤雅美、ねじめ正一、落合恵子、小林陽太郎、小林桂樹
いずれも心に残るものばかりで、藤沢周平自身やその作品が、いかに多くの人に多面的に愛されたかがわかります。
私が関心を持ったのは、演出家の鴨下信一さんの「文章のカメラワーク」という一文です。ここでは、藤沢周平の風景描写の特徴として、「物語の背景となる風物の描写は、主人公の五感に触れるものに厳密に限られ」ており、「ちょうどカメラが移動しながら主人公の目に映り、身体に感じるものを次々に写しとってゆくように風景は描写されてゆく」と指摘されています。藤沢さんのエッセイ「わが青春の映画館」などで、山形師範学校時代に洋画に没頭したことが回想されていますが、この風景描写の特徴などは、洋画やミステリーの手法を意図的に時代小説に持ち込んだのではないか、と想像させてくれます。
また、とりわけ印象深いものに、福澤一郎「仰げば尊し 湯田川中学校教師時代」という一編があります。学校の先生あがりの作家はおおぜいいるけれど、藤沢周平はどうもちょっと違うような気がします。たった二年間の教員生活、しかも結核によって中断されてしまったものでした。ところが、教え子たちがずっと小菅先生のことを慕っている。藤沢周平自身が、小菅先生として、教え子たちとの交流を続けている。しかも、単に儀礼的なものではなく、かけがえのないものとして大切にしていたように思えます。こういう作家は、きわめて珍しいのではないだろうか。実は、こんな記事がBBSに投稿されていました。
藤沢周平インタビューより~たぶん未発表?~
もしかすると、元同僚や教え子の人たちが、もっといろいろな出来事をネット上に書き残してくれているのかもしれないと思うとき、インターネットの時代が、書籍出版とは無縁な人にも、記録と公表の手段を提供していることを感謝せずにはいられません。
1 別れ 弔辞など 丸谷才一、井上ひさし、遠藤展子
2 周平さんと私 黒岩重吾、無着成恭、田辺聖子、宮城谷昌光、佐野洋、杉本章子、清水房雄、太田経子、倉科和夫、井上ひさし
3 藤沢周平が遺した世界 向井敏、川本三郎
4 半生を紀行する 土田茂範他座談会、福澤一郎、植村修介、金田明夫、高橋義夫、杉山透
5 藤沢周平作品と私 中野孝次、涌谷秀昭、丸元淑生、関川夏央、寺田博、吉田直哉、秋山駿
6 藤沢周平を語りつくす 吉村昭・城山三郎、秋山駿・中野孝次、皆川博子・杉本章子・宮部みゆき、仲代達矢・竹山洋・菅野高至
7 藤沢さんの頁 インタビュー「なぜ時代小説を書くのか」、エッセイ傑作選、小菅留治全俳句、他
8 藤沢さんへの手紙 出久根達郎、水木楊、鴨下信一、渡部昇一、黒土三男、辻仁成、佐藤雅美、ねじめ正一、落合恵子、小林陽太郎、小林桂樹
いずれも心に残るものばかりで、藤沢周平自身やその作品が、いかに多くの人に多面的に愛されたかがわかります。
私が関心を持ったのは、演出家の鴨下信一さんの「文章のカメラワーク」という一文です。ここでは、藤沢周平の風景描写の特徴として、「物語の背景となる風物の描写は、主人公の五感に触れるものに厳密に限られ」ており、「ちょうどカメラが移動しながら主人公の目に映り、身体に感じるものを次々に写しとってゆくように風景は描写されてゆく」と指摘されています。藤沢さんのエッセイ「わが青春の映画館」などで、山形師範学校時代に洋画に没頭したことが回想されていますが、この風景描写の特徴などは、洋画やミステリーの手法を意図的に時代小説に持ち込んだのではないか、と想像させてくれます。
また、とりわけ印象深いものに、福澤一郎「仰げば尊し 湯田川中学校教師時代」という一編があります。学校の先生あがりの作家はおおぜいいるけれど、藤沢周平はどうもちょっと違うような気がします。たった二年間の教員生活、しかも結核によって中断されてしまったものでした。ところが、教え子たちがずっと小菅先生のことを慕っている。藤沢周平自身が、小菅先生として、教え子たちとの交流を続けている。しかも、単に儀礼的なものではなく、かけがえのないものとして大切にしていたように思えます。こういう作家は、きわめて珍しいのではないだろうか。実は、こんな記事がBBSに投稿されていました。
藤沢周平インタビューより~たぶん未発表?~
もしかすると、元同僚や教え子の人たちが、もっといろいろな出来事をネット上に書き残してくれているのかもしれないと思うとき、インターネットの時代が、書籍出版とは無縁な人にも、記録と公表の手段を提供していることを感謝せずにはいられません。