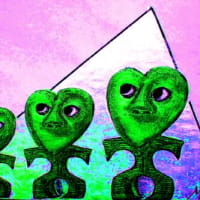二人の会話は意外な方面に移る、彼らの原点になった学生時代である、
「昭和の50年代から60年代の終り頃まで、早稲田大学の近辺には、インテリの老人・やや左翼系の老人がいた」
「いたね」
「そこに出かけて、いろいろな話しを聞いた、これが、貴重な経験になった」
「大学の、あの連中よりもだろう」
「ふふふ、まあね」
「プロテスタントのひとりよがりの理解も困ったものだが、それ以上に、左がかった教授たちが、ひどかったね」
「どっちもどっちだ」
「ニッポンのインテリは、ひどいね」
「まったく、自分が正しいと思いこんでいる、上から目線の小ばかにした態度は、どうにかならないもんかね」
「ほんとーにね、受験勉強のエリートということ、その本質は暗記力、東大だって暗記力で入れる、見てごらんよ、あのハニワヅラを」
「こまったもんだ、精神の輝きのある若者がいなくなってしまった」
「さて、当時の早稲田の教授‣助教授、左側の者が多く、教授会の内容が学生運動家につつぬけといったことがあったね」
「みょーにものわかりがよくて、共産中国の肩をもつのがいた」
「いたいた、人類の理想の社会だっていうんだ」
「それで、左翼運動に走った学生も多かった」
「あの国の現実を知ろうとしない、自分の理想像を押しかぶせる、悪いトコロは見ても見ない」
「ところで早稲田周辺の老人たち、
『あの戦争で負けて良かったんだ』
そんなことを言っていたなあー 」
「その理由は」
「軍人がふんぞりかえり、えばり散らし、権力をカサに着て、わがものガオ、それは、ひどかった」
「もし勝っていたらどうなっていたかと言うんだ、マッカサーのあの異常な人気は、その反動だったという意見だったね」
「そんなことを言っていたのか」
「ああ、だから、それが、昭和史理解のヒントになった」