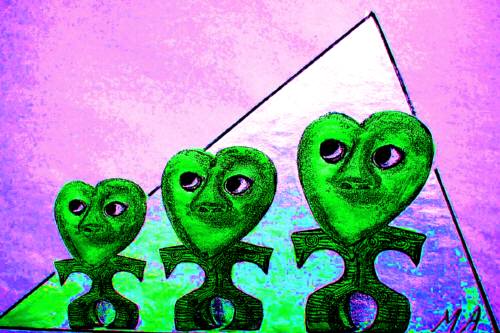今はどうなっているのか分からないが、以前は、土器や深鉢の説明に、
「これは新嘗際に使われたものです」
さらに、月夜見尊(つきよみのみこと)が使用したとかどうとかと明記されていた、月夜見尊は記紀神話に登場する神のひとりで、天照大神の弟である。
私は、その説明を見てびっくりしてしまった、ちょっと考古学をやったものなら、そんなことは書けないはずだ。
その後、2、3年して、再び訪れたら、やはり同じ説明、だから、若い館員に、
「中学生に笑われるよ」
どうして、こんなことになっているのであろうか、かつて縄文中期に農耕が行われたことを発表して学会に叩かれたことがある、それにしてもである、新嘗祭を持ってこられては開いた口が塞がらない。
今はどうなっているのだろう、まさか…
時々、こういうことがある、お分かりになるでしょう。