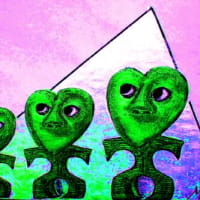「だから、ここで究極のドラマが展開した、若い女性が、
『どうぞ母親といっしょにさせてください、高齢で足が不自由で、世話をする者が必要なんです』
母親といっしょとはビルケナワ収容所で、そのままガス室に直行なのだが、それは、知らされていない」
「すごいね」
「ある母は、
『この子は身体は大きいんですが、まだ12歳なんです、強制労働はかわいそうです、どうぞ、そちらの収容所にさせてください』 」
これを聞いた収容所の役人は、
『まあ、すきなようにするさ』
『・・・』
『結局、おなじことなんだけどな』 」
「数時間後、若い母親は胸騒ぎにおそわれる、むこうのエントツからモクモクとケムリが出ている、古くからいる収容所のオンナにたずねると、
『あんたの息子は、あのケムリだよ』
その後の記憶は、ない、という 」
「なかなか、だな」
「ああ、凄惨なもんだ、大きなメカニズムが動くと、止めることができない」
「ヒトラーは、それを知っていたのかな」
「どうだろう、ヨダレがダラダラのパーキンソーだからな、知らされていたかどうか、知っていたとしても」
「知っていても」
「止められなかっただろうね、日に日に追いつめられている、なによりも食料が逼迫(ひっぱく)していた、そうそう、アウシュビッツで、ある時、大きなソーセジの配給があった」
「ソーセジね」
「ふだんはギリギリで、若いおんなが、鬼のような警備兵に、ジャガイモ2個でカラダをまかせることもあった、ようだ」
「そのソーセジの原料は…」
「まあ、それは、なかったようだがね」