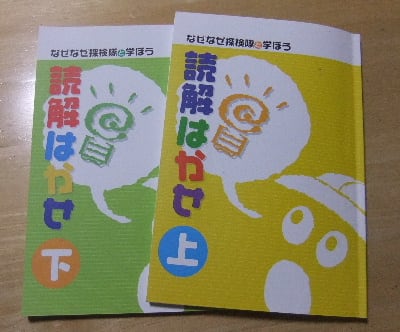螻蛄(おけら)についてネットで調べてみました。
“おかさん”と同じように、なぜ昆虫の「螻蛄」が不名誉にも「一文無し」の意味で使われるようになったのか、疑問に思う人が他にもいました。そして、質問箱に投稿していました。
いくつかの説が回答されていました。その中で、“おかさん”は次の2つがいいなと思いました。
1.螻蛄(ケラ)を前から見ると万歳をしているように見えるため、一文無しでお手上げ状態になった姿に見立て、「おけらになる」とする説が有力とされます。(クリオネという人が回答していました。)
2.昆虫のオケラは、昔、良く脱皮した後の皮が見つかる事が多かったそうです。当然、中身は空です。
オケラ→中身が空の皮だけ、→、財布の中が空の連想から、今、財布がオケラ=一文無し という風に成ったと聞いた事が有ります。(ケンタさんという方の回答です。)
ふむふむ、なるほど!

実際の螻蛄は、上から見るとこんな感じに見えます。
<追記>
螻蛄が一文無しという意味に使われている話もそうですけど、世の中には調べてみたり、聞いてみたりすると「へぇー!面白い。」というようなことがいっぱいあります。
「国語」でも「理科」でも「社会」でも「算数」でもない、いわゆる何処の分野にも分類できない「雑学」とでも言う分野の知識がこれにあたると思います。
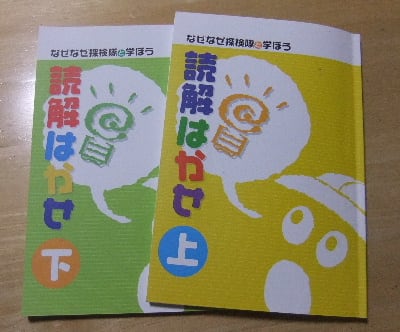
そんな「雑学」を題材にした小学生向けの国語テキストがあります。都麦出版という会社が塾向けに出している「なぜなぜ探検隊と学ぼう! 読解はかせ」というものです。↑
☆「きんちょうすると、オシッコがしたくなるのはなぜ?」、
☆「がまんしたオナラは、どこへいくの?」、
☆「温度の感じ方は何で決まるの?(気温30度は暑く感じるのに、お風呂の30度はぬるく感じるのはなぜ?)」、
☆「一週間の曜日の順番は、どうやって決めたの?」、
☆「どうしてウマは顔が長いの?」etc.
(ちなみに学舎には「どうして“おかさん”の顔は長くなったのか?」という漢字書き取り用の教材があります。夏休みなどに、臨時で使用していますが、子ども達に、人気の高い教材となっています。そこには、もともと丸顔だった“おかさん”の顔が今のように長くなってしまった秘密が書かれています。)
などなど、“おかさん”や子ども達の好奇心を満足させるような話題ばかりです。今年の4月時点では「上巻」だけしかできていなかったので、とりあえず教材としての採用を見送っていましたが、夏くらいに「下巻」も出揃いました。
下巻も内容を見てみると、とても面白いものとなっています。上下あわせ全部で90ものミニ知識が探検しながら習得できるようになっています。現在これを子ども達の「国語」教材に出来ないものかと考えています。
もともと、このテキストは「国語」の読解用教材と開発されているので、そのまま使えばよいというものなのですが・・・。今現在使っている、国語教材とのすみわけをどうするかを現在検討中です。