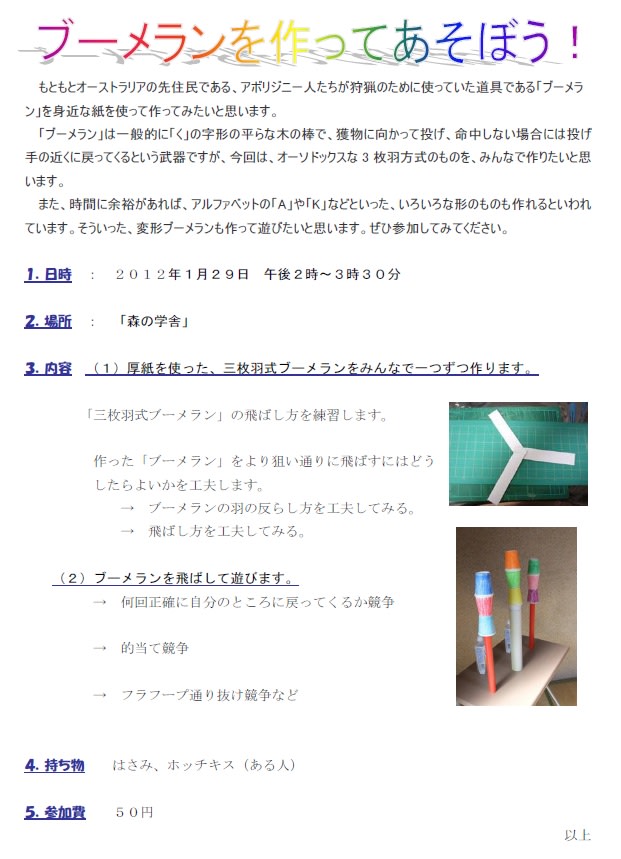お風呂で佐藤勝彦さん監修の「相対性理論を楽しむ本」を読んでいます。
そしてそれなりにこの本を楽しんでいます。
「相対」と「絶対」の違い、「相対」は「どれも正しい」、光に関する考察、時間に関する考察、実際には実験できないことを頭の中で組み立て実験する「思考実験」などなど、面白いことがたくさん書かれています。
ただ、部分部分では、その適切な説明のお陰で、「なるほどね!」と合点がいったような気になるのですが、さて「相対性理論って何?」と聞かれると、読んだばっかりのことすらうまく説明することができません。
要は、よくわかっていないのです。
これと似たようなことが、学舎でも日常茶飯事に起きています。
生徒たちが新しい理論を学ぶ時に生じています。
昨日の中学1年生を対象にした数学の「作図の応用」の勉強の時にも起きました。
“おかさん”としては、「作図」はもう既に2回も学習しているので簡単な復習を行なって、次の単元に進もうと思っていたのですが、復習のための簡単な問題を出したら、ほとんどの生徒ができませんでした。
彼らにとっての「作図」は“おかさん”にとっての「相対性理論」に匹敵するようです。
なので昨日は、“おかさん”が新しいものを理解する時によく行なう「反復学習」をたくさん行ないました。
体育会系の練習の乗りで、何度も何度も、手を変え品を変え、類似問題を繰り返し解いてもらいました。
お陰でみんな「作図」に少しだけなじんでくれたような気がします。
ただ、これが一週間経つとまたもとの木阿弥になってしまいます。
ですので、毎回宿題を出し、その定着を図ることにしています。
いきなりの絶大なる効果は期待できませんが、みんな真面目なので着実に効果を上げています。
そのよい例が、半年以上続けている「10問の計算問題」全員全問正解キャンペーンです。
後一歩で実現できそうです。
最初の一歩が踏み出せれば、加速度的に力が付いてくるものと思われます。
<追記>
今日はこれから雪かきです。
朝一番で行なうか、昼行なうかを迷いましたが、通信教育の添削をとにかく仕上げなくてはならなかったこと。
また、朝一番の凍った雪を除くのは大変なので、少し温まり解け始めた頃に雪かきをした方がよいと考えたからです。
お隣さんの分もしなければならないので、大変ですが、頑張ります。

学び舎に行く途中にある公園です。↑

逆光の太陽に照らされてとてもきれいです。