駿河紀行 02
10月12日 原駅から東田子の浦駅まで 天気 晴れ
朝8時頃にはホテルを出てJRローカル線で清水駅から原駅まで。
電車は比較的すいていて、都会の通勤の光景ではない。
清水駅→原駅は30分ほど。車窓から付近の光景を見ながら電車の到着を待つ。
原駅に着き、駅を出て見上げると富士山が冠雪していて驚く。
昨日の11日は天気が良くなく、でも山頂は雪だったということだ。この秋の初冠雪とのこと。
新鮮である。しかし、カメラを向けても建築物や電線が写って不満である。

駅を出てからしばらくは東海道を歩いていたのだが、地図を見て近いのを確認して
駿河湾の湾岸道路に出る。東海道を歩きたかったので、思いを残すが仕方ない。
風はなく天気も晴れ。気温もちょうど良い。海と空が青い。
この辺りの駿河湾の、ゆるやかな湾曲は優美である。立派な湾岸道路は長く
続いているものと思える。私の眼では遠くまでは見えない。
道路の北側は素晴らしい松林が道路に添うように続いている。
防風林の役目を負っているのだろう。松の幹がおしなべて斜めになって
北の方を向いている。
これだけの規模の松林が今も残っていることは素晴らしい。
歌人の若山牧水なども松林保全の運動に関わっていたとか、何かで読んだ記憶がある。
多くの人たちの尽力によって現在の松林が保たれているのだろう。
道路を歩きながら富士山に向けて盛んにシャッターを切る。




湾岸道路だけで5キロほどを歩いたものと思う。
東田子の浦駅の北側に広がる「浮島が原自然公園」に行くべく、湾岸道路に思いを残しながら
進路を北に採る。JRの線路を超えるための踏切にまで行く道がややこしくて、
少し遠回りをしたりする。
「浮き島ヶ原」は湿地帯として知られている。でも平安歌人たちの詠んだ「浮き島ヶ原」歌は
10首ほどと少ない。その中に西行歌もあるが、歌は情感があまり伝わってこない。
西行の富士の歌と浮き島ヶ原の歌。
01 いつとなき思ひは富士の烟にておきふす床やうき島が原
(岩波文庫山家集161P恋歌・新潮1307番・西行物語)
02 けぶり立つ富士に思ひのあらそひてよだけき恋をするがへぞ行く
(岩波文庫山家集153P恋歌・新潮691番・夫木抄)
あづまの方へ修行し侍りけるに、富士の山を見て
03 風になびく富士の煙の空にきえて行方も知らぬ我が思ひかな
(岩波文庫山家集128P羈旅歌・新潮欠番・
西行上人集・新古今集・拾玉集・自讃歌・西行物語)
ア 清見潟月すむ夜半のうき雲は富士の高嶺の烟なりけり
(岩波文庫山家集73P秋歌・新潮319番・
続拾遺集・玄玉集)
イ 思ひきや富士の高嶺に一夜ねて雲の上なる月を見むとは
(源平盛衰記巻八)
ウ 富士みてもふじとやいはむみちのくの岩城の山の雪のあけぼの
(諸国里人談)
アイウの三首は西行歌というだけの確証がありません。
ともあれ、沼沢地だった名残を残した「浮き島ヶ原自然公園」として、
付近の人たちに親しまれているようです。構造物をできるだけ排して、
しかし自然の運動のままに放置しているわけではなく、きちんと管理されて
いるように感じました。
富士見の名所らしく浮き島ヶ原からは富士がよく見えました。




公園の植物です。最後の画像は(東田子の浦駅)。




JR原駅から清水のホテルまでは35キロほどあります。写真を撮りもっての、あるいは名所を見ながらでは
長すぎると考え、東田子の浦駅で電車に乗車。残念だけど途中を端折って由比駅下車。
赤人の田子の浦も近くですが当時の田子の浦と現在の田子の浦では位置が違うとの説もあり、
かつ古い時代の情趣などは望むべくもないので断念。了以の開削した富士川も渡りたかったけど、
これも断念。
次の03では由比駅から清水までのレポートです。











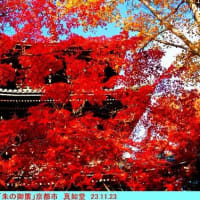
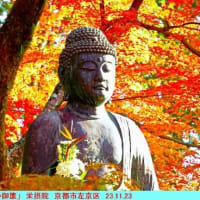







今も昔も憧れの富士山、ずっと噴火などしてほしくないですね。