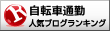自分の住む海士剥には、月山神社がある。つきやまじんじゃと呼ばれている。地域の神社なので、正月には、お詣りに行く。うちには神棚があり、月山神社のお札が祀っている。その月山神社は、以前御月森にあった。




明治までは御月築山と呼ばれ、標高30mで海から300mほどに所にぽつんとある山だ。今は植林されているので神社跡からは海は見えないが、江戸時代はほぼハゲ山で風がまともにあたる場所だ。

康正2年(1456年)に加賀の国より遷宮とある。不毛の地に室町時代には、人が住んでいた事が分かる。
その後、文化元年(1801年)に現在地のおさ袋に移築されている。
この事から分かる事は、加賀の国では富樫正親が一向門徒を弾圧した頃であり逃れてきた人たちが日本海側の北部に居住地を求めている。

石川県に海士埼というところがあるが、海士剥の由来なのかもしれない。更に、海士剥の方言と石川県の方言が一部一致しているのである。
月夜命は、ツクヨミ命は海や船、あるいは生命の源泉である水や不老不死の生命力とも関係が深い神さまである。
『古事記』ではこの神が父神のイザナギ神から「滄海原を治めよ」と命じられとある。これは海を主な生産の場とする海人族と月神との結びつきをうかがわせる。おそらく、月の引力が潮の満ち引きと関係することから、海を支配する神として海人に信仰されていたのである。実際に古くから海の神を祀る神社にはツクヨミ命が祭神として祀られていて、海士剥の月山神社も同様である。
鳥海の笹子の月山神社は、修験者との関わりが強く山形の月山信仰に由来しているので、こことは若干違う事が分かる。