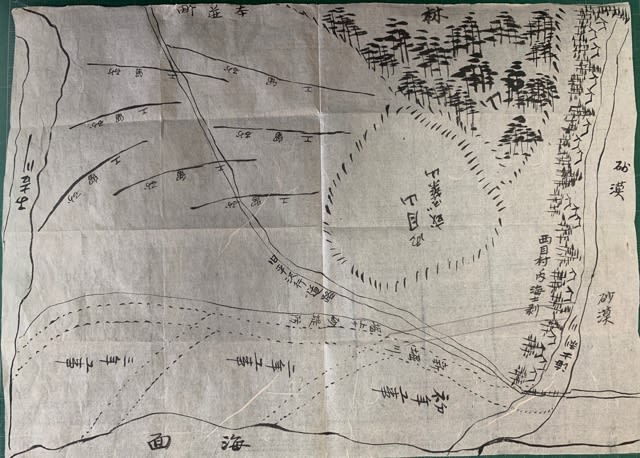「馬鞍山市は中華人民共和国安徽省東部に位置する地級市。工業が発達しており、中国十大鉄鋼基地の一つである。また、香港証券取引所に上場している馬鞍山鋼鉄の本社がある。 同じく製鉄都市である鞍山市と名前が似ているが、別の都市である。」とあった。

見た目はソロストーブライトと全く同じに見える。燃焼方式は全くのパクリなので問題ない。

早速松ぼっくりを燃やしてみた。2次燃焼が確認できる。また、遊び道具を増やしてしまった。今まで使っていたウッドストーブは廃棄しようと思う。






『古事記』ではこの神が父神のイザナギ神から「滄海原を治めよ」と命じられとある。これは海を主な生産の場とする海人族と月神との結びつきをうかがわせる。おそらく、月の引力が潮の満ち引きと関係することから、海を支配する神として海人に信仰されていたのである。実際に古くから海の神を祀る神社にはツクヨミ命が祭神として祀られていて、海士剥の月山神社も同様である。
鳥海の笹子の月山神社は、修験者との関わりが強く山形の月山信仰に由来しているので、こことは若干違う事が分かる。





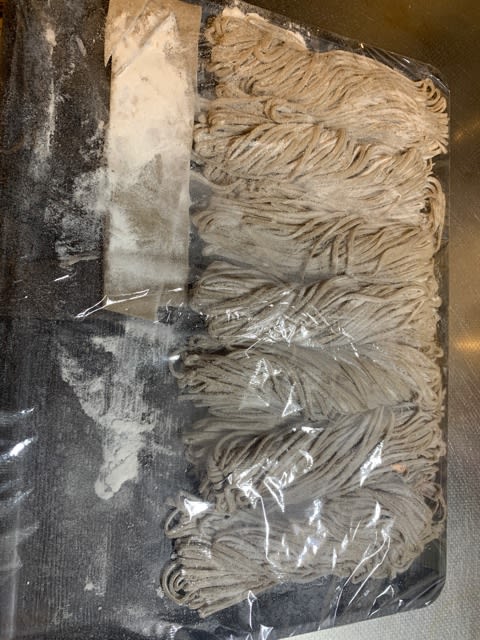


自宅より4kmほど南下した出戸集落に聖徳太子神社があります。とても閑静な場所で駐車エリアもありません。地域密着の神社で、余り知られていないところです。昨日は、小春日和だったので出かけてみました。
ここは、文永10年創設とされています。鎌倉時代で、北条時宗が蒙古襲来で戦わずして勝利した文永の役の1年前のことです。鷹島という方が勧請したとあります。



聖徳太子はもともと職人の祖神として信仰されていたわけではありません。太子のイメージはその死後、時代とともに神格化していき、様々な伝説が生まれました。中世以降、仏教家によって太子は日本の仏教の開祖と崇められ、太子信仰が大いに広まっていきました。神仏習合の風潮のなかで、太子を始祖とする太子流神道なども登場するほどでした。そうした太子信仰が民間に広がる中、近世になり大工、屋根色、石屋、畳屋、表具師、瓦製造、桶屋、鍛冶屋などの職人が、太子講を組織し、太子を祖神として祀る習慣が生まれました。これが中世期です。
出戸には幕府の田んぼはほとんどありません。もちろん武士でもありません。職人の居住地で有れば聖徳太子神社を勧請したのももうなずけけます。出戸では、戦前、出戸ムシロと言ってムシロを編んで生計を立てていた人がたくさんいたのです。

日本の八百万の神は多彩であるから、一般にそれぞれの職業に応じた守護神が祀られています。もともとはそれぞれ職種ごとに守護神を祀っていましたが、それとともなってしだいに聖徳太子も祖神としてまつられるようになったと言われます。
ちなみに山の神やお地蔵さんも祀られています。仏教とも深く関係をもった神社である事が伺えます。







鶏の卵の色はさまざまあり、親鶏の種類によって色が違いますが、たまごの色を決める色素は「プロトポルフィリンprotoporphyrin」という名前の物質で、卵殻が形成されるときに「プロトポルフィリン」色素が沈着し、色素の配合具合で色がつきます。アローカナは青色になるポリフィリン色素の割合が、ほかの種よりも強いため、色素の働きにより、青色の卵が作られます。アローカナの卵は、「青色」という色の特異さが消費者に珍しがられていますが、青色というのは、本来、食欲を減退させてしまうもです。ところが、アローカナの卵は、見た目のユニークさよりも、実際に、黄身が濃厚でとても美味しいため、栄養面でもウコッケイ以上に注目されていて、1個で150円もするのです。