前回(→こちら)の続き。
「ダラダラしながら初段になりたい!」
という、スカタンきわまりない将棋ファンのため、「定跡書」「詰将棋」といったトレーニングと無縁なまま、茫洋と二段になった私が、アドバイスしてみることにした。
わけだが、自分はかなり特殊というか、長い将棋ファン歴で、
「ほとんど実戦を指さない」
というタイプなので、その上達のプロセスを説明するのが、少々ややこしい。
そこで、まず根本から話してみようということで、将棋自体をおぼえたのが、前回言ったように小学生のころだった。
初めて買った『将棋マガジン』に載っていた、順位戦C級2組の表の最後尾に
「四段 羽生善治」
という表記があって、6回戦で小阪昇五段に敗れて、昇級戦線から脱落した将棋が紹介されていたから、1986年の半ばくらいだったのだろう。

一番下にデビュー1年目の羽生善治の名が。
父親に、なんとなく町の道場に連れていかれたのだが、それが「南波クラブ」(仮名)というところ。
今は知らねど、昭和のころの将棋道場というのは基本的に「オッチャンの社交場」であり、女子供にはすこぶる敷居が高かった。
気はいいが、ガラッパチでブルーカラーのおじさんたちが、煙草の煙モウモウの場所で、軽口や鼻歌まじりに指している場には、入ることすら、ちょっとした度胸がいるもの。
当然、子供が入ったところで「指導する」という文化も、ノウハウもない。
せっかく道場に行っても、気の知った仲間と指したいオジサンは、愛想のない私などにかまうわけもなく、ひとりぽつねんと取り残されるわけである。
さすがに、それで席料は取れないということで、マスターがひとりの先生を用意してくれた。
それがアオバさんという、30代後半くらいの男性。
棋力はアマ五段。
作家の沢木耕太郎さんのような、ダンディーな雰囲気を漂わせており、この人がこれから指導してくれると。
そんな強いうえに、物腰もやわらかな紳士に教えてもらえるとはと、期待は高まったが、残念なことに棋力向上の手助けにはならなかった。
理由は簡単で、この人が勝負に関してはマジの大マジで、対局がすべてガチだったから。
まずガチなところが、手合いがすべて平手戦であったこと。
当時、こちらの棋力が、アマ6級程度。
それとアマ五段となれば、二枚落ちですら、まず勝てないほど差があり、六枚落ちとか、それくらいからはじめていいほどであろう。
それがオール電化ならぬオール平手。
こちらが何連敗しようが、手直り(勝敗ごとにハンディのレベルを変えていくシステム)はなく、延々と平手。
飛車落ちや角落ちのような、軟弱なハンディ戦など望むべくもなく、すべて互角の条件でのファイト。
文字通りの「大人と子供の戦い」である。
こんなもん勝てるはずもないというか、ほとんどの勝負が仕掛けの時点でついてしまうほどだが、ガチレベル2として、さらにこんなものもついてきた。
「戦型は全部、アオバさんの右四間飛車」
将棋を多少かじった方ならわかると思うが、右四間というのは破壊力のある戦法である。
プロレベルだとそう簡単ではないが、アマ級位者クラスなら△62飛、△73桂、△54銀の形から、△65歩。
とか仕掛けられれば、もうそれだけで防戦困難で、早指しの将棋なら、そのまま無抵抗で、つぶされてしまうことも多いだろう。
私の場合も、まさにそれ。
ただでさえ、アマ五段と6級という、絶望的な体格差があるのに、そこに右四間でバリバリ攻められては、こちらもなにもできない。
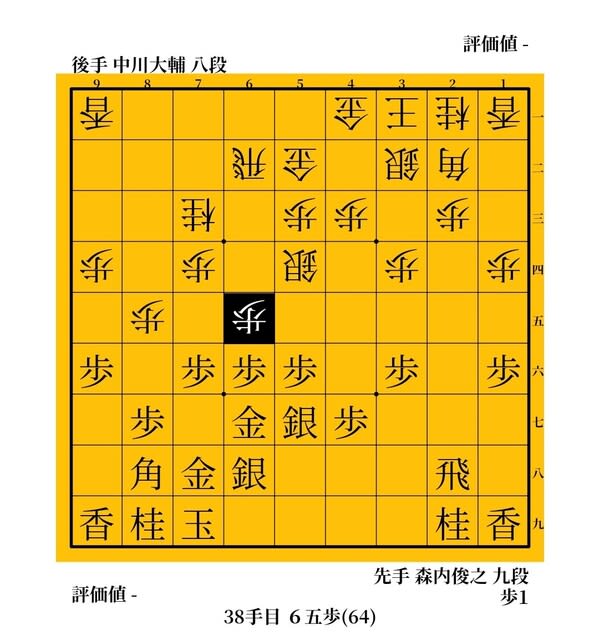
五段のこの攻めを受け切れる6級など、地球上には存在しません。
しかも、居飛車でいこうが、振り飛車にかまえようが、かまわず△62飛から△65歩。
そのまま、タコなぐりにされて終了である。鬼か。
これでは指導対局もへったくれもなく、ただただ、なにもできずに負け続けることに。
途中から、ちょっと数えてみたのだが、結局アオバさんとは最低50局。
下手すると、100局近く教えてもらったが、勝てたのはわずか2回。
その数少ない勝利も、アオバさんが、自陣の詰みをウッカリする「トン死」であり、まったくのマグレである。
これもまた、ガチのポカであり、その証拠に2回とも、投了後のアオバさんは鬼のような形相。
感想戦でもきびしい口調で、
「なんてバカな! こんなひどい見落としがあるものか!」
「油断した。でなければ、こんな錯覚などするはずがない!」
頭をかかえてボヤきまくりで、メチャクチャに悔しがる。
あまつさえ、こちらをキッとにらむと、
「こんな結末は、めったにあることじゃない。これを実力と過信したら、とんでもない落とし穴に落ちることになるぞ!」
そんなん思てませーん(苦笑)!
どんだけマジなんや。こっちは素人の子供なんだよー。
まあ、アオバさんは指導に関しては素人の「勝負師」だし、まったく悪意がないのは子供心にもわかった。
とにかく、アオバさんは将棋にマジメで、その証拠に感想戦などは、すごく丁寧に(レベルが高すぎてついていけないことも多いけど)教えてくれる。
ただ、実戦となるスイッチが入ってしまい、相手を見て「ゆるめる」みたいなことはできない人なのだ。
高倉の健さんですね。「自分、不器用なんで」。
だからまあ、別にイヤな思いはしないというか、途中からはもう半分おもしろがってたんだけど、これでは上達の一助にならないのは、ハッキリしている。
「子供や彼女(妻)に、将棋のおもしろさを知ってほしいんですけど、どうすればいいですか?」
男性将棋ファン永遠の願いには、羽生善治九段の言う通り、
「簡単です。100回対局して、100回とも負けてあげてください(笑)」
これしかないんだけど、なかなか、むずかしいもんであるなあ。
(続く→こちら)

























