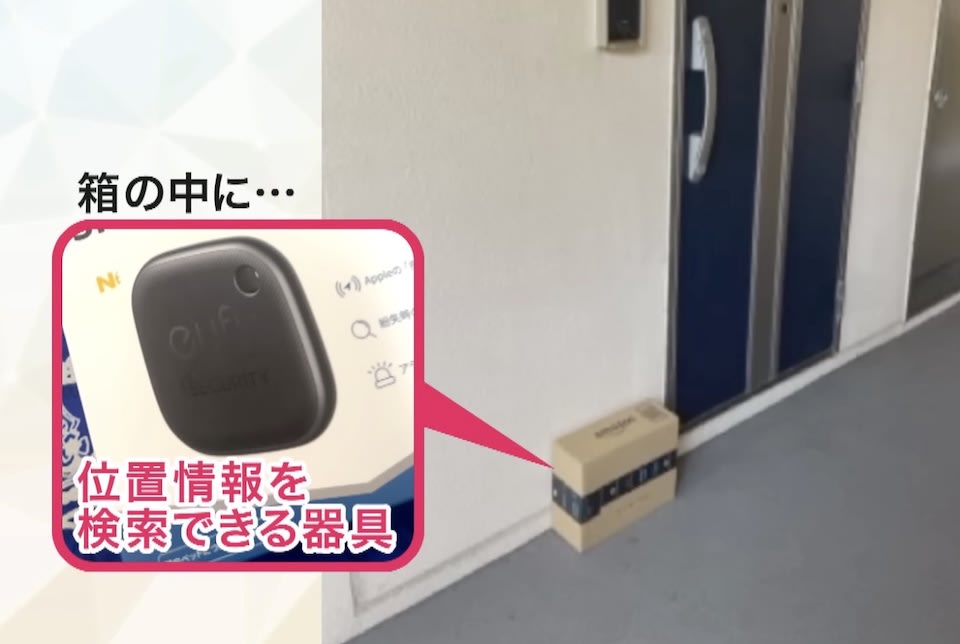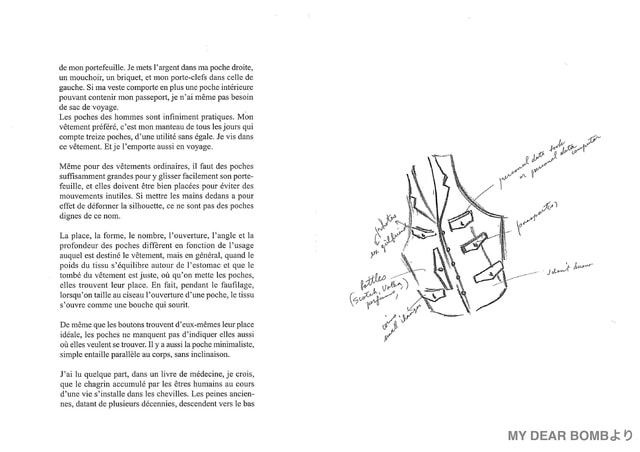1月20日、米国でトランプ大統領が就任し、第二次政権がスタートした。就任前から米国第一主義を唱える政権が世界、そして日本にとってはどんな影響を及ぼすのか。業界各界では識者諸氏が様々な持論を展開している。その中で、アパレル&小売業にとっては日米の金利差が縮まらない限りは円安基調が維持され、インバウンド効果が持続するとの見方が主流だ。
2024年、訪日客数は3686万9900人と、前年を47%上回り過去最高となった。全国百貨店(70社、178店)の24年1~12月売上高は、前年比6.8%増の5兆7722億円。コロナ禍前の19年比では3.6%増で4年連続のプラス。国内客売り上げは1.4%増の5兆1234億円と、19年比では2%減となったが、札幌、京都、大阪、福岡が2ケタ増を確保した。インバウンドは売上高、買い上げ客数ともに過去最高となった。東京や大阪など大都市の百貨店で、ラグジュアリーブランドや化粧品などの高額品が好調だったことによるものだ。客層はコロナウィルスが感染拡大する19年までは中国の富裕層が8割を占めたが、コロナ禍明けの23年からは台湾、香港、欧米が増加している。
福岡のインバウンドは韓国からが主流で、中国、台湾、香港が続く。博多と釜山を結ぶ高速船のクイーンビートルが運航休止に追い込まれたものの、LCCがその穴を埋めている。彼らは若者を中心に急速に成熟しているようで、高額なブランドにはほとんど目もくれない。買い物のメーンは地元セレクトショップや古着、雑貨などで日本、福岡ならではのアイテムを購入する。ショップの中には、品揃えを韓国人の好みに合わせるより、日本人向けの商品をいかに韓国人にアピールするかに主眼を置くところが目立つ。地理的な利点を生かしてリピーターや顧客化に力を入れる狙いだ。また、福岡では半導体産業の隆盛から台湾人の訪日客も増えてはいるが、円安基調が続く当面は、韓国人が主力のお客になりそうだ。

東京や大阪の百貨店で高額品の人気が高いのは、免税売上げを見てもわかる。2024年度は2年連続で過去最高を上回る見通しだ。免税売上高は三越伊勢丹が1800億円に迫る勢いで、大丸松坂屋も1300億円を超える見込み。阪急阪神は目標の1000億円から1200億円超に上方修正した。中でも、高島屋は24年9月~11月期は最高益を更新した。ただ、すでにインバウンドの売上げは高止まりしており、今後の伸びは限定的との見方もある。そのため、百貨店全体ではインバウンド効果を俄景気で終わらせてはダメとの意識が醸成されつつある。外国人客も日本人と同じく顧客管理をしっかりしていかなければならないのは確かなようだ。
懸念される点はトランプ新政権がとる経済政策が為替変動にどう影響するかである。米国はドル高基調が続けばいいが、トランプ大統領には米国の輸出を促進したい思惑もある。ドル安を進めて円が10円、20円と高騰すればインバウンドも左右されかねない。為替は変動するものという前提で捉えれば、それでも外国人の富裕層にもっと買い物してもらえるように各業態がどう魅力を打ち出すか。要は日本人のお客と同様に「買い物するならあの店、接客してもらうならあのスタッフ」という感じで、リピートしてもらうことが重要になる。滞在中または再来日のたびに何度も買い物してもらえるようにいかに顧客化していくか。各社の戦略が訪日外国人の購買拡大には欠かせないと言える。

百貨店のトップが述べた2025年の年頭所感で目立ったのは、外国人向けのアプリとスマートフォンによる決済サービス。アプリは店舗での利用客を識別できるため、購入者に商品やサービスの情報を提供することで顧客化につなげることができる。スマートフォン決済もいろんなブランドが登場しているため、バリエーションを揃えることが顧客の利便性向上や顧客満足度のアップに貢献する。さらに大手百貨店では海外のVIP客に対応するために外国語が話せるアテンドスタッフを配置するようになった。地方百貨店でも主力の中国や台湾、香港からの旅行者に対応するために、北京語や広東語が喋れる社員の採用が始まっている。

ただ、外国人を顧客化するカギは、商品(ブランド)やデジタル(アプリや決済手段)の次の段階に移行していると思う。例えば、各地の名産品をブランド化したよりプレミア感を持つ商品の開発である。商品そのもののレベルアップを図ることはもちろんだが、日本では失われつつあるパッケージや包装紙などをグレードをアップすること。各地の名店と百貨店がコラボすれば、不可能ではないだろう。外国人に対しても自ら購入するだけでなく、ギフトにした時のホスピタリティまで意識したモノづくりが不可欠になる。心から歓待されることを自らのステイタスと位置付けるのは、万国共通のはずだからだ。
お客が求める商品は1点から取り寄せるか!?
資本力のある大手百貨店は、日本人客もインバウンドも多面的な施策で捕捉することができる。だが、地方百貨店は足元の市場が少子高齢化で縮小し、インバウンドも大都市の百貨店ほど恩恵はない。テナントビルに業態転換して生き残りを図れるところは少数派で、八方手詰まりの店舗は営業終了や閉店せざるを得ないのが実情だ。熊本のようにTSMC(台湾積体電路製造)の工場進出で旅行から居住へ切り替える訪日外国人が増え、地元の百貨店がタナボタ需要に恵まれているところもある。地方百貨店としてはこれを追い風にMDを充実させ、サービスも拡充して一気呵成に出たいところだろう。
ただ、熊本に台湾の富裕層が居住しているなら、むしろ福岡の百貨店にとって顧客化のチャンスではないか。優しい言い方をすれば、熊本の百貨店は地方型の品揃えに過ぎないから、それに富裕層が満足するとは限らないからだ。厳しく言えば、小売業界は弱肉強食。富裕層のマーケットが隣県にあるのに、上級百貨店が指を咥えて眺める必要はないことになる。関東圏に例えるなら、千葉に住む外国人の富裕層が欲しい商品を求めて東京・新宿の伊勢丹まで買い物に行くことはあり得る。福岡と熊本の距離もこれとほぼ同じだから、買い物に出かけるケースはあるだろう。ならば、掴まえない手はない。

福岡・天神には三越伊勢丹系列の岩田屋、Jフロントリテイリング系列の福岡大丸がある。これらの品揃えは県境を超えた富裕層の争奪にも有利なはずだから、積極的に開拓してもいいのだ。福岡の百貨店にも外国人の富裕層を呼び込む戦略があって当たり前だ。
では、ハンディがある地方百貨店はどうすればいいか。三越伊勢丹、高島屋、大丸松坂屋などの系列ではあっても、リーシングできるブランドは限られる。外国人の富裕層を顧客化する上で、そうした問題にどう対応していくのか。例えば、こういうケースが考えられる。外国人の顧客がネットでは販売されていない「あのブランドが欲しいんだけど」とのウォンツを示した時。外商スタッフは「あいすいません。そのブランドは当店では扱いがないんですよ」と答えるのか。それとも「扱いはないのですが、入手できるように手を尽くしてみます」と答えるのとは外国人の印象も違ってくるだろう。
ブランドの入手ができる、できないは別にして、日本の流通事情を知らない外国人を顧客化していくには、そういう姿勢を示すことも必要ではないか。もちろん、購入額など顧客のレベルで、対応できる内容も変わってくると思うが、お客のわがままに真摯に応える姿勢を見せるのも、顧客化の第一歩になる。単なるブランド販売ならテナントビルでも可能だが、百貨店の独自性は顧客の思いに寄り添うところにもある。海外店舗などの相互送客に乗り出すところも出てきているが、究極は利益が折半になっても、系列を超えてブランド(商品)を融通し合えること。もう百貨店の敵は百貨店ではなく、ネットなど他のチャンネルなのだ。地方百貨店にとっても生き残るヒントの一つになるかもしれない。

外国人の富裕層を顧客化するブランドやサービス。だが、その先にどんな施策があるのか。局面は大手百貨店と同じ過程に移行しつつあると思う。日本人と同じで外国人もブランドだろうが高級食材だろうが、メジャーなものが手に入るようになると、やがては飽きてくる。そう考えると、日本の埋もれた名品を知ってもらうのはもちろん、そこでしか体験できない「コト消費」にも目を向ける。さらにモノやコンテンツの新たな運用や組み合わせを行う「トキ消費」も注目される。体験型の消費に外国人も積極的に参加してもらうことだ。別に難しく考え、ハードルを上げることはない。要は「日本でどんなことを楽しみたいですか」と聞けばいいのだ。
すでに東京などでは、インバウンド向けに日本の伝統芸能や文化を体験したり、自然や四季を満喫したりするなどの活動が行われている。例えば、レンタルした着物での街歩き、茶道や日本舞踊、和菓子作りなどの体験、伝統的な祭事への参加などだ。さらに訪日外国人が日本に定住するようになると、地域とのつながりは欠かせない。当然、コト消費が促進されていく。従来は旅行企画の一部だった娯楽や余暇を日々のライフスタイルに組み込んでいけばいいのだ。日本の各地にはいろんな「コト」がある。日本人には当たり前でもあっても、外国人にとっては未体験。それを掘り起こして消費に結びつけることも顧客化の一つになる。

一地方百貨店では難しいだろうから、自治体や商工会議所などと組んで実施していくことが必要になる。もちろん、外国人のウォンツを引き出すには、百貨店の外商スタッフが御用聞き的な形で、積極的にコミュニケーションをとっていくことが不可欠だ。これは大都市、地方を問わず、百貨店が外国人の需要を喚起する上では重要なはず。そうして声を集めて精査し、できるかどうかの検討を進める。全てが実現可能ではないと思うが、外国人を顧客化する上では各自に対するマーケティングが不可欠になる。地方百貨店が生き残る上でも重要だ。
地方百貨店が外国人を顧客化できれば、地域の専門店や個店も続いていけるのではないか。アプリやスマートフォン決済などインフラ整備には限界があるが、QR決済くらいのサービスは地方でも進んでいる。あとは個店レベルで訪日外国人にどうアピールしていくか。韓国人のように自らいろんな店舗や業態を探し歩く外国人もいるが、中国や台湾、香港などの人々はそこまで成熟してはいない。だから、百貨店ほどの知名度がなければ、業種、業態ごとの店舗情報を網羅したアプリの開発が必要だろう。「こんなテイストの商品を扱っているお店は」「このブランドが買いたいけど、どこに行けばいい」「外国人にも気軽に対応してくれるところは」「この街らしいカルチャーは」等などと、検索機能を充実させていく。
個店レベルでのアプリ制作は厳しいから、自治体や商工会議所などが支援していくことも必要だ。ブランド購入、サービス拡充、モノからコト消費へ。さらにコト消費からトキ消費へ。モノやコンテンツを買って、どうやって生かすか。モノを使っていく背景・過程を楽しむストーリーを消費することに置き換わっている。なんて意見も散見されるが、居住外国人はまだそこまで成熟はしていないだろう。ただ、百貨店を利用してきた日本人と同じ道を外国人が辿るのは想像に難くない。しかも、コトやトキの消費は、思い出や記憶という資産を生む。
つまり、何を提供すれば、顧客としてキープできるのか。地元の隠れた魅力を掘り起こし、それを外国人にも伝えていくという視点が地方の百貨店、小売業に課されたテーマだと考える。エトランゼをお得様にするためにも。