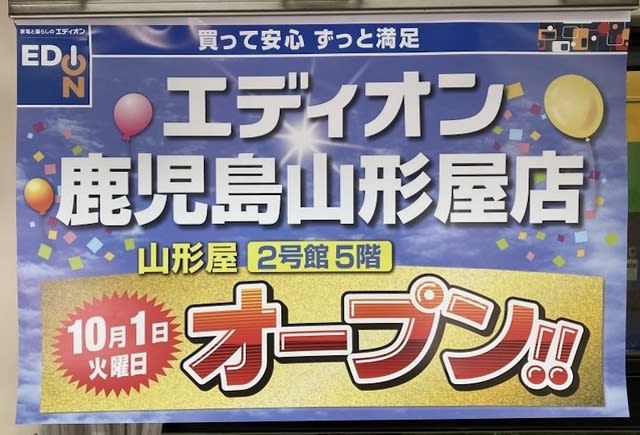すでにご存知の通り、MLBの2024年ワールドシリーズは、LAドジャーズがNYヤンキースを4勝1敗で下した。一連のポストシーズンに出場する選手は、ディビジョンシリーズやリーグチャンピオンシップの段階から、胸元に各シリーズのタイトルロゴがプリントされた「フーディ」を着ている。広大な国土をもつ米国では相手チームの球場に長距離移動を強いられるから、これらのアイテムも急激な気温変化に対応しなければならない。そのため、フーディの素材や混紡率はどうなっているのかということだ。
今年のナショナルリーグのリーグチャンピオンシップは、ドジャーズとNYメッツが対戦した。チームはそれぞれロサンゼルスとニューヨークが本拠地だから、米国の西と東約4000kmほどを行き来したわけで、試合を観戦するファンの服装を見ても両本拠地の気候の違いがはっきりと見て取れた。ワールドシリーズもドジャーズとヤンキースの対戦になり、ロサンゼルスで観戦するファンが至って軽装なのに対し、ニューヨークではしっかりアウターを着込んでいた。ファンの服装を見ると、気温差があるのが明らかだった。

ロサンゼルスの10月の平均気温は19.5℃で、11月は同16.7℃。リーグチャンピオンシップが開催される10月末は間をとって18.1℃とした場合、体感的には肌寒いとまではいかない。ファンの格好も薄着の人はTシャツ、重ね着した人でも応援用のユニフォーム程度だった。ところが、ニューヨークは10月の平均気温が18.9℃だが、試合が開催される夜間は気温が約10℃程度まで下がる。ファンがフーディの上にスタジャンなどを重ね着していたのも、それだけ寒いからだ。むしろ、選手の方が体温調整は大変ではなかったかと思う。
試合中、ピッチャーは投球で運動量が多いため、トップスは半袖のユニフォーム1枚か、その下にアンダーシャツを着る程度。野手にしてもユニフォームとアンダーシャツと軽装だ。しかし、ベンチで試合を見つめる控えの選手は、ほとんどがフーディ姿だ。これはTVカメラが時々選手の様子を映し出すため、シリーズという興行をアピールするロゴ入りのアイテムを着るレギュレーションだからというのは理解できる。だが、選手自体がアウターを着込るのは、いつでも試合に出られるよう体を冷やさないためだと思われる。
そこでフーディの素材や混紡率についてである。あくまでテレビを通じて見た印象なのだが、表面には光沢があり、素材も柔らかそうなのでコットン100%というより、ポリエステルがかなり混紡されているのではないかと感じた。厚みは10~12オンスくらいか。スポーツウェアなので裏パイルか、裏起毛の処理が施され、吸汗と保温の両方の機能を備えているはずだ。選手各自に何枚支給されているかはわからないが、着用後に洗濯し翌日の試合に備えることを考えると、速乾性も必要になる。

サプライヤーは胸元のロゴマークからナイキだとわかった。サイトで調べると、「Los Angeles Dodgers 2024 World Series Authentic Collection」「Men’s Nike Therma MLB Pullover Hoodie」という、選手が着ているものと同じアイテムがヒットした。価格は$85で、日本円に換算すると11月2日のレートで1万3000円程度だから、レプリカではなく選手と同じものだろう。ドジャーズ用は優勝が決まった時点でSold Out。ディテールを見ると、素材はポリエステル100%と表記されていた。

商品説明には、「フーディは汗を逃がすテクノロジーと高性能素材を組み合わせて、チームがコミッショナーズ トロフィーを目指して競い合うときに暖かく快適に過ごせるようにします」とある。メリットには、「Nike Therma ファブリックが暖かさを保ちます。Nike Dri-FIT テクノロジーが肌から汗を逃がして蒸発を早め、ドライで快適な状態を保ちます」と記されている。ナイキが開発した素材「Therma(therm=熱の意)」が保温性を高め、汗をかいても水分を逃がしてすぐに乾く機能を持つと謳われている。

実際にフーディを着た選手の印象はどうだったのか。多分、無償提供を受けているはずだから悪くは言えないのは割り引いても、ナイキが素材開発や機能アップに注力した以上、試合でベストパフォーマンスを上げるためのウォームアップ用としては十分だったと思う。ちなみにヤンキースバージョンも、チームのカラーとロゴが違うだけで、素材も機能も同じ。こちらは11月2日現在で、完売はしていない。優勝できなかったことも要因の一つだろう。ただ、Big Kids=年長の子供向けは、素材がコットン80%、ポリエステル20%の混紡になっている。ポリエステルの比率を2割まで下げたのは、子供を含め敏感肌には合繊オンリーは厳しいと認めているようなものだ。
かつて「米国人は冬場でも綿製品を好んで着る」という話を聞いたことがある。確かに筆者がニューヨークにいた1990年代半ば、真冬のマンハッタンでもコットン素材で厚手のスウェットフーディの上にダウンジャケットを羽織る人々を数多く見かけた。日本のようにインナーにウールのセーターを着ることはなかったようだった。ウールを着ている人でも、それはアウターのジャケットか、コート。米国では肌に近いまたは直接触れるアイテムは、天然素材のコットンを好んで着る、そんな服飾文化が浸透していたのかもしれない。

と言っても、極寒のニューヨークではそうはいかない。真冬はマイナス20℃くらいまで気温が下がるからだ。いくら肌触りのいいコットンが好きと言っても、下着にも何らかの保温効果のあるものが必要になる。昭和世代の日本人なら誰もが知っている「ラクダのももひき」だ。実を言うと、米国にもラクダの毛を使用したものではないが、肌に優しい天然繊維のカシミア素材などを使った保温性下着があった。1990年代、このシーズンになるとニューヨークポストのようなタブロイド紙には、保温性下着の通販チラシが折り込まれていた。
チラシにはファミリー役の男性、女性、子供が下着を着た写真が掲載されていたが、下着は上に着るシャツの襟やパンツの裾から見えないよう首周りを大きく裾を短くした仕様で、デザイン的にも野暮ったくならないよう工夫されていた。保温性を保ちながら、ファッション性にも配慮する。当時はヒートテックといった合繊素材で格安かつ保温機能を持つ下着はなかった。だから、カシミアのような高級素材が使われた下着は価格も高く、購入者もマンハッタンのオフィスに勤務するホワイトカラーの家族が主体だったと思われる。
低所得のブルーカラーが高額な下着に手が届くはずもない。厚手のコットンを使ったフーディの上にダウンを着ながらも寒そうにしていたのは、米国の社会階層からわかる気もする。ただ、ビジネスとして考えると低所得者の方が圧倒的に多いのだから、素材が豊富に入手できて価格が抑えられる素材が主力になるのは当然だ。1990年代は綿糸が今ほど高騰してはいなかったため、スウェットのフーディは手頃なアイテムだった。コットン素材の裏側を起毛させた厚みのある生地にし、空気を取り込み保温性を高める裏起毛、いわゆる裏毛によって冬場でも着られるようにしていたのである。
綿100%でも保温性は高められる
あれから約30年、日本はずっと暖冬が続いている。ただ、寒冷地では重ね着せず一枚ものでも寒さを凌げる衣類が必須だ。極寒にはコットンの裏毛くらいではとても保たない。スポーツメーカーがスキーなど冬季競技のインナーウエアとして保温性のある下着を開発していたが、販売先はスポーツ店に限られたことから、メジャーにはなり得なかった。そこに目をつけたのがユニクロだった。素材メーカーと共同で機能性下着を開発し自前の店舗で売り出せば、価格も下げられきっとメジャーになるはず。思惑は的中した。それがヒートテックだ。
コットンの裏毛はアンダーウエアにはなり得ない。アイテムはスウェットのフーディやトレーナーだから、防寒にはアウターが必須になり、どうしても着膨れして見えてしまう。ヒートテックは薄手の下着にもかかわらず保温力があるため、上の厚着を抑えられる。ファッション的にもすっきり見える。それもヒットした要因だろう。もちろん、ナイキのようなスポーツメーカーも機能性ウエアを見逃すはずはない。契約選手のモニタリングを通じて様々な機能を付加するために商品開発に注力したわけだ。
2000年代はスウェット素材、コットンの裏毛に代わる保温性をもつ素材がトレンドになったと言える。特にスポーツウェアでは、選手がかいた汗をを蒸発させて、素材を素早く乾かす機能が求められる。また、冬場のウェアには汗を逃すが、熱は逃さないことも条件となった。各メーカーで素材の名称は異なるが、機能性ウェアはユニフォームの枠を外れたジャージなどにも取り入れられていった。

今年のMLBワールドシリーズで、ナイキが提供したNike Therma MLB Pullover Hoodieも、その一つと言える。選手が試合中に着るのだから、Nike Dri-FITの汗を逃がして蒸発を早め、ドライで快適な状態を保つことが最優先される。もちろん、サプライヤーとして両チームに提供した応分のコストは、一般に量販することで回収する。それが2024 World Series Authentic Collectionだったわけだ。優勝したドジャーズ版はSold Outしたのだから、十分に元は取れたと思う。
ただ、一般のファンがWorld Series Authentic Collectionのフーディを購入したのはドジャーズ優勝が理由で、機能性素材に惹かれたわけではないだろう。米国人の好みからすれば、ポリエステルよりもコットンではないのか。それとも、コットン嗜好も素材トレンドの変化とともに変わってしまったのか。一般の人々がカジュアルウェアとして着る分には、Dri-FITのような機能が必要なのか。また、Nike Thermaよりコットンスウェットの裏毛で十分な気もするが、どうなのだろう。
ここからは個人的な意見として述べてみたい。この10年ほどでスウェットのフーディやトレーナーにも、合繊の比率が高まっている。これは果たして機能性素材のトレンドをくんだものか。それとも、価格ダウンとコスト圧縮のために使用する綿糸を減らす、またはカットする目的からか。各社がこの秋冬に販売するスウェットアイテムから混紡率を比較してみよう。


ユニクロ スウェットプルパーカ 本体: 100% 綿 スウェットパンツ 本体: 88% 綿, 12% ポリエステル
無印良品 スウェットプルパーカ 本体: 52% 綿, 48% ポリエステル スウェットワイドパンツ 本体: 52% 綿, 48% ポリエステル
グローバルワーク 上品スウェットパーカー ポリエステル90% ポリウレタン10% 上品スウェットパンツ 本体:ポリエステル90% ポリウレタン10%
ギャップ Athleticロゴ パーカー コットン 77%, ポリエステル 23% GAPロゴ ジョガーパンツ コットン 77%, ポリエステル 23%
大手SPAではざっとこんな感じだ。ユニクロはスウェットのパーカこそボディは綿100%だが、パンツでは合繊の比率が12%になる。無印良品はさらに増えて綿と合繊はほぼ半々。アダストリアのグローバルワークは完全に合繊オンリーだ。逆にグローバルブランドでコットン100%はH&Mが一部で投入しているが、レビューを見ると「生地が薄い」との書き込みがあった。ファストファッションだけにこれはコスト削減が理由と見られる。
他では「ユナイテッドアスレ」や「プリントスター」がコットン100%を採用するフーディやパンツを揃えている。両ブランドはプロモーションやイベントなどのプリントに対応するため、生地の薄厚や色のバリエーションが売りになっている。一方、ファッション性を優先し、値頃感のあるブランドではコットン100%の裏毛素材は、企画するところが少なくなっているようだ。ただ、合繊混紡の方が冬場の保温性がアップするかと言えば、一概には言えないような気がする。


筆者が10年前に購入した無印良品のジップアップスウェットは、12オンスほどの肉厚で裏毛仕様。本体は綿100%である。合繊が混紡されていないにも関わらず、ポカポカして非常に保温性が高い。しかも、コットンオンリーだから心地よく、屋外のランニングから室内のトレーニング、街着、室内着とオールマイティに通用し、現在も着用している。購入したのは日本の店舗になるが、商品タグには[US]MUJI U.S.A LIMITED http:www.muji.usと表記されているから、米国企画のアイテムなのかと思う。
この頃までの無印良品では、衣料品には綿などの天然繊維が使われることが多く、質感も非常に良かった。ジップアップスウェットはその典型だ。表示されているように米国向けの商品として企画したのなら、やはり米国人のコットン好きに合わせたのかもしれない。だが、その後の無印良品では素材トレンドの変化や綿糸価格の高騰の影響からか、コットン100%のスウェットはすっかり影を潜めている。そんな変節ぶりを当の米国人はどう思っているのだろう。ポリエステル100%のMLB Pullover Hoodieが売れているところを見ると、米国人も合繊オンリーといった素材変化を許容し始めているのか。
筆者は別にアメカジ心酔派でも、アスレジャーのヘビーユーザーでもない。ただ、かつての米カジュアルに使用されていたコットンのざらっとした風合いや、洗う度に粗野になっていく感じは嫌いではない。あれこそアメリカンコットンの良さなのだ。さらにコットン100%はリサイクルもしやすく、SDGsの流れにも合致する。かたや日本は夏日が3シーズンにもわたるほどの異常気象が続いている。コットン100%のスウェットはもう通年で求められるのではないだろうか。変に機能性ウエアに固執するよりも、綿オンリーの方が受け入れられる環境になっているような気がするが。
今年のナショナルリーグのリーグチャンピオンシップは、ドジャーズとNYメッツが対戦した。チームはそれぞれロサンゼルスとニューヨークが本拠地だから、米国の西と東約4000kmほどを行き来したわけで、試合を観戦するファンの服装を見ても両本拠地の気候の違いがはっきりと見て取れた。ワールドシリーズもドジャーズとヤンキースの対戦になり、ロサンゼルスで観戦するファンが至って軽装なのに対し、ニューヨークではしっかりアウターを着込んでいた。ファンの服装を見ると、気温差があるのが明らかだった。

ロサンゼルスの10月の平均気温は19.5℃で、11月は同16.7℃。リーグチャンピオンシップが開催される10月末は間をとって18.1℃とした場合、体感的には肌寒いとまではいかない。ファンの格好も薄着の人はTシャツ、重ね着した人でも応援用のユニフォーム程度だった。ところが、ニューヨークは10月の平均気温が18.9℃だが、試合が開催される夜間は気温が約10℃程度まで下がる。ファンがフーディの上にスタジャンなどを重ね着していたのも、それだけ寒いからだ。むしろ、選手の方が体温調整は大変ではなかったかと思う。
試合中、ピッチャーは投球で運動量が多いため、トップスは半袖のユニフォーム1枚か、その下にアンダーシャツを着る程度。野手にしてもユニフォームとアンダーシャツと軽装だ。しかし、ベンチで試合を見つめる控えの選手は、ほとんどがフーディ姿だ。これはTVカメラが時々選手の様子を映し出すため、シリーズという興行をアピールするロゴ入りのアイテムを着るレギュレーションだからというのは理解できる。だが、選手自体がアウターを着込るのは、いつでも試合に出られるよう体を冷やさないためだと思われる。
そこでフーディの素材や混紡率についてである。あくまでテレビを通じて見た印象なのだが、表面には光沢があり、素材も柔らかそうなのでコットン100%というより、ポリエステルがかなり混紡されているのではないかと感じた。厚みは10~12オンスくらいか。スポーツウェアなので裏パイルか、裏起毛の処理が施され、吸汗と保温の両方の機能を備えているはずだ。選手各自に何枚支給されているかはわからないが、着用後に洗濯し翌日の試合に備えることを考えると、速乾性も必要になる。

サプライヤーは胸元のロゴマークからナイキだとわかった。サイトで調べると、「Los Angeles Dodgers 2024 World Series Authentic Collection」「Men’s Nike Therma MLB Pullover Hoodie」という、選手が着ているものと同じアイテムがヒットした。価格は$85で、日本円に換算すると11月2日のレートで1万3000円程度だから、レプリカではなく選手と同じものだろう。ドジャーズ用は優勝が決まった時点でSold Out。ディテールを見ると、素材はポリエステル100%と表記されていた。

商品説明には、「フーディは汗を逃がすテクノロジーと高性能素材を組み合わせて、チームがコミッショナーズ トロフィーを目指して競い合うときに暖かく快適に過ごせるようにします」とある。メリットには、「Nike Therma ファブリックが暖かさを保ちます。Nike Dri-FIT テクノロジーが肌から汗を逃がして蒸発を早め、ドライで快適な状態を保ちます」と記されている。ナイキが開発した素材「Therma(therm=熱の意)」が保温性を高め、汗をかいても水分を逃がしてすぐに乾く機能を持つと謳われている。

実際にフーディを着た選手の印象はどうだったのか。多分、無償提供を受けているはずだから悪くは言えないのは割り引いても、ナイキが素材開発や機能アップに注力した以上、試合でベストパフォーマンスを上げるためのウォームアップ用としては十分だったと思う。ちなみにヤンキースバージョンも、チームのカラーとロゴが違うだけで、素材も機能も同じ。こちらは11月2日現在で、完売はしていない。優勝できなかったことも要因の一つだろう。ただ、Big Kids=年長の子供向けは、素材がコットン80%、ポリエステル20%の混紡になっている。ポリエステルの比率を2割まで下げたのは、子供を含め敏感肌には合繊オンリーは厳しいと認めているようなものだ。
かつて「米国人は冬場でも綿製品を好んで着る」という話を聞いたことがある。確かに筆者がニューヨークにいた1990年代半ば、真冬のマンハッタンでもコットン素材で厚手のスウェットフーディの上にダウンジャケットを羽織る人々を数多く見かけた。日本のようにインナーにウールのセーターを着ることはなかったようだった。ウールを着ている人でも、それはアウターのジャケットか、コート。米国では肌に近いまたは直接触れるアイテムは、天然素材のコットンを好んで着る、そんな服飾文化が浸透していたのかもしれない。

と言っても、極寒のニューヨークではそうはいかない。真冬はマイナス20℃くらいまで気温が下がるからだ。いくら肌触りのいいコットンが好きと言っても、下着にも何らかの保温効果のあるものが必要になる。昭和世代の日本人なら誰もが知っている「ラクダのももひき」だ。実を言うと、米国にもラクダの毛を使用したものではないが、肌に優しい天然繊維のカシミア素材などを使った保温性下着があった。1990年代、このシーズンになるとニューヨークポストのようなタブロイド紙には、保温性下着の通販チラシが折り込まれていた。
チラシにはファミリー役の男性、女性、子供が下着を着た写真が掲載されていたが、下着は上に着るシャツの襟やパンツの裾から見えないよう首周りを大きく裾を短くした仕様で、デザイン的にも野暮ったくならないよう工夫されていた。保温性を保ちながら、ファッション性にも配慮する。当時はヒートテックといった合繊素材で格安かつ保温機能を持つ下着はなかった。だから、カシミアのような高級素材が使われた下着は価格も高く、購入者もマンハッタンのオフィスに勤務するホワイトカラーの家族が主体だったと思われる。
低所得のブルーカラーが高額な下着に手が届くはずもない。厚手のコットンを使ったフーディの上にダウンを着ながらも寒そうにしていたのは、米国の社会階層からわかる気もする。ただ、ビジネスとして考えると低所得者の方が圧倒的に多いのだから、素材が豊富に入手できて価格が抑えられる素材が主力になるのは当然だ。1990年代は綿糸が今ほど高騰してはいなかったため、スウェットのフーディは手頃なアイテムだった。コットン素材の裏側を起毛させた厚みのある生地にし、空気を取り込み保温性を高める裏起毛、いわゆる裏毛によって冬場でも着られるようにしていたのである。
綿100%でも保温性は高められる
あれから約30年、日本はずっと暖冬が続いている。ただ、寒冷地では重ね着せず一枚ものでも寒さを凌げる衣類が必須だ。極寒にはコットンの裏毛くらいではとても保たない。スポーツメーカーがスキーなど冬季競技のインナーウエアとして保温性のある下着を開発していたが、販売先はスポーツ店に限られたことから、メジャーにはなり得なかった。そこに目をつけたのがユニクロだった。素材メーカーと共同で機能性下着を開発し自前の店舗で売り出せば、価格も下げられきっとメジャーになるはず。思惑は的中した。それがヒートテックだ。
コットンの裏毛はアンダーウエアにはなり得ない。アイテムはスウェットのフーディやトレーナーだから、防寒にはアウターが必須になり、どうしても着膨れして見えてしまう。ヒートテックは薄手の下着にもかかわらず保温力があるため、上の厚着を抑えられる。ファッション的にもすっきり見える。それもヒットした要因だろう。もちろん、ナイキのようなスポーツメーカーも機能性ウエアを見逃すはずはない。契約選手のモニタリングを通じて様々な機能を付加するために商品開発に注力したわけだ。
2000年代はスウェット素材、コットンの裏毛に代わる保温性をもつ素材がトレンドになったと言える。特にスポーツウェアでは、選手がかいた汗をを蒸発させて、素材を素早く乾かす機能が求められる。また、冬場のウェアには汗を逃すが、熱は逃さないことも条件となった。各メーカーで素材の名称は異なるが、機能性ウェアはユニフォームの枠を外れたジャージなどにも取り入れられていった。

今年のMLBワールドシリーズで、ナイキが提供したNike Therma MLB Pullover Hoodieも、その一つと言える。選手が試合中に着るのだから、Nike Dri-FITの汗を逃がして蒸発を早め、ドライで快適な状態を保つことが最優先される。もちろん、サプライヤーとして両チームに提供した応分のコストは、一般に量販することで回収する。それが2024 World Series Authentic Collectionだったわけだ。優勝したドジャーズ版はSold Outしたのだから、十分に元は取れたと思う。
ただ、一般のファンがWorld Series Authentic Collectionのフーディを購入したのはドジャーズ優勝が理由で、機能性素材に惹かれたわけではないだろう。米国人の好みからすれば、ポリエステルよりもコットンではないのか。それとも、コットン嗜好も素材トレンドの変化とともに変わってしまったのか。一般の人々がカジュアルウェアとして着る分には、Dri-FITのような機能が必要なのか。また、Nike Thermaよりコットンスウェットの裏毛で十分な気もするが、どうなのだろう。
ここからは個人的な意見として述べてみたい。この10年ほどでスウェットのフーディやトレーナーにも、合繊の比率が高まっている。これは果たして機能性素材のトレンドをくんだものか。それとも、価格ダウンとコスト圧縮のために使用する綿糸を減らす、またはカットする目的からか。各社がこの秋冬に販売するスウェットアイテムから混紡率を比較してみよう。


ユニクロ スウェットプルパーカ 本体: 100% 綿 スウェットパンツ 本体: 88% 綿, 12% ポリエステル
無印良品 スウェットプルパーカ 本体: 52% 綿, 48% ポリエステル スウェットワイドパンツ 本体: 52% 綿, 48% ポリエステル
グローバルワーク 上品スウェットパーカー ポリエステル90% ポリウレタン10% 上品スウェットパンツ 本体:ポリエステル90% ポリウレタン10%
ギャップ Athleticロゴ パーカー コットン 77%, ポリエステル 23% GAPロゴ ジョガーパンツ コットン 77%, ポリエステル 23%
大手SPAではざっとこんな感じだ。ユニクロはスウェットのパーカこそボディは綿100%だが、パンツでは合繊の比率が12%になる。無印良品はさらに増えて綿と合繊はほぼ半々。アダストリアのグローバルワークは完全に合繊オンリーだ。逆にグローバルブランドでコットン100%はH&Mが一部で投入しているが、レビューを見ると「生地が薄い」との書き込みがあった。ファストファッションだけにこれはコスト削減が理由と見られる。
他では「ユナイテッドアスレ」や「プリントスター」がコットン100%を採用するフーディやパンツを揃えている。両ブランドはプロモーションやイベントなどのプリントに対応するため、生地の薄厚や色のバリエーションが売りになっている。一方、ファッション性を優先し、値頃感のあるブランドではコットン100%の裏毛素材は、企画するところが少なくなっているようだ。ただ、合繊混紡の方が冬場の保温性がアップするかと言えば、一概には言えないような気がする。


筆者が10年前に購入した無印良品のジップアップスウェットは、12オンスほどの肉厚で裏毛仕様。本体は綿100%である。合繊が混紡されていないにも関わらず、ポカポカして非常に保温性が高い。しかも、コットンオンリーだから心地よく、屋外のランニングから室内のトレーニング、街着、室内着とオールマイティに通用し、現在も着用している。購入したのは日本の店舗になるが、商品タグには[US]MUJI U.S.A LIMITED http:www.muji.usと表記されているから、米国企画のアイテムなのかと思う。
この頃までの無印良品では、衣料品には綿などの天然繊維が使われることが多く、質感も非常に良かった。ジップアップスウェットはその典型だ。表示されているように米国向けの商品として企画したのなら、やはり米国人のコットン好きに合わせたのかもしれない。だが、その後の無印良品では素材トレンドの変化や綿糸価格の高騰の影響からか、コットン100%のスウェットはすっかり影を潜めている。そんな変節ぶりを当の米国人はどう思っているのだろう。ポリエステル100%のMLB Pullover Hoodieが売れているところを見ると、米国人も合繊オンリーといった素材変化を許容し始めているのか。
筆者は別にアメカジ心酔派でも、アスレジャーのヘビーユーザーでもない。ただ、かつての米カジュアルに使用されていたコットンのざらっとした風合いや、洗う度に粗野になっていく感じは嫌いではない。あれこそアメリカンコットンの良さなのだ。さらにコットン100%はリサイクルもしやすく、SDGsの流れにも合致する。かたや日本は夏日が3シーズンにもわたるほどの異常気象が続いている。コットン100%のスウェットはもう通年で求められるのではないだろうか。変に機能性ウエアに固執するよりも、綿オンリーの方が受け入れられる環境になっているような気がするが。